秋山 賢次 理事長の独自取材記事
みとよ内科にれクリニック
(観音寺市/本山駅)
最終更新日:2025/09/11

透析治療を続ける患者の間では、「長い時間をかけてしっかりと治療を受けたい」と願う声が少なくない。そんな、一人ひとりの想いに応えているのが、香川県三豊市と観音寺市の両市から通院できるエリアにある「みとよ内科にれクリニック」だ。秋山賢次理事長は透析治療を基軸に、幅広く腎臓疾患の診療を提供。患者からの強い要望に応え、5時間以上の透析治療が可能なクリニックを2011年に開業した。高松市内にも透析治療を専門とする分院を設け、互いに連携しながら、広い視野で診療できる体制を整えている。穏やかな口調でよどみなく言葉を紡ぎ、「ジェネラリストでありたい」と語る秋山理事長の姿からは、患者のQOL向上を願う熱い想いが伝わってきた。
(取材日2025年7月12日)
長時間の透析治療ニーズに対応するクリニックを
珍しいクリニック名だと思いますが、名前の由来は?

このクリニックが、この先も続いていく未来を思い描き、自分の名前などは入れない名称を考えました。「にれ」は、ドイツ語で腎臓を意味する「ニーレ」という言葉から着想を得たものです。もちろん、ニレの木の生命力もイメージしています。透析医療を通じて、地域の皆さんの健康維持に貢献すべく、当院の名称は「みとよ内科にれクリニック」といたしました。
医師を志した経緯を教えていただけますか?
私は小学校2年生の頃に読んだSFホラー漫画から、「そもそも自分はなぜ存在しているのか」と考えるようになりました。その後は古代イスラエルの預言者や、キリスト教の救世主が登場する洋画に感銘を受け、数学や物理学などとともに、哲学、宗教への興味を深めていったのです。自身の存在理由をどうやって突き詰めるのか悩み、最終的には、高校の恩師からの助言を受けて医学の道に進みました。学生時代はやはり、臨床よりも基礎医学に興味を持ちましたが、初期研修先の急性期病院で患者さんと向き合ううちに、臨床にのめり込んでいましたね。専門性についてはいくつかの選択肢がありましたが、それこそイスラエルの民が約束の地カナンへ導かれるように、大学の恩師が私を腎臓内科の道へと導いていました(笑)。
医師になられた後は、腎臓内科一筋で?
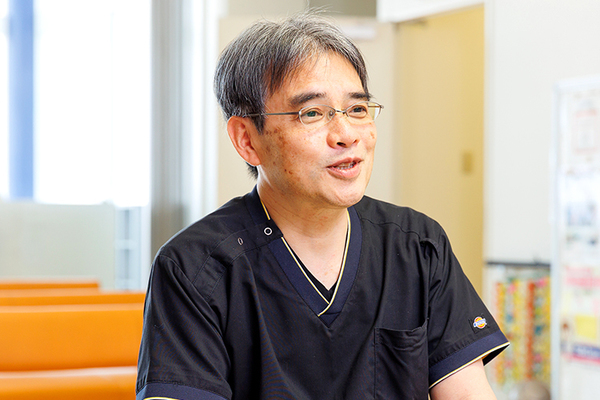
一分野だけを極めるようでは、多角的な視野を得られません。私自身も、三豊総合病院では内科医長として血液内科や膠原病内科領域も診ていましたし、それもまた必要な経験だったと思います。内科医長は10年、その後は香川県立中央病院の内科部長を4年経験し、2011年に開業に至りました。きっかけは、三豊で診ていた透析患者さんからの切実なご要望です。私が席を離れた後は、さまざまな事情から透析治療の時間が短縮され、長く治療を受けられる環境を望む声が増えていったんですね。4時間程度の治療では、体内の老廃物や毒素を十分に排出できません。そこから5時間、6時間の治療に対応する施設を立ち上げたいと考えるようになりました。県立中央病院で、在宅血液透析(HHD)に対応し始めたことも大きな転換点になったと思います。1日おきに7時間半、在宅で実施する透析治療は理想のスタイルだと感じ、長時間治療への思いを強くしていきました。
高松にも、分院を開院されています。
県立中央病院でも、三豊と同様に長時間透析を望む声があり、2015年に「高松にれクリニック」を開設しました。開設にあたっては、泌尿器科が専門の医師との連携体制を整えるという目的もありました。腎臓内科と泌尿器科は近しい関係にあり、血尿などの検尿異常から腎炎を疑うと、実は膀胱がんだったというケースは少なくありません。それぞれの視点から同じ患者さんを診察できればと、私たちは毎週のようにお互いのクリニックへ出向いています。これからも密に連携を取りながら、双方の患者さんへの的確な診療を模索していきたいです。
スタッフ全員が、透析治療の「スペシャリスト」に
クリニックの場所や設計についてもお聞きしたいです。

クリニックにはある程度の広さが必要でしたが、ご縁があり、不動産会社の所持する建物を紹介いただくことができました。ここはもともと、家電量販店が入居していた場所ですので、約270坪と広さも十分です。ちょうど三観地区の両市の中間地点にあり、どちらのエリアからも通いやすいと思います。家族や設計士さんの意見、アイデアをもとに医療機関らしくないクリニックをめざし、皆さんが穏やかな気持ちで過ごせるようにと、院内にはオレンジやブラウンなど、温かみのある色を採用しました。透析ベッドは当初より10床程度増え、現在は37床です。配置を工夫することで、プライバシーにも気を配っています。
患者さんは、健康診断などを機に訪れる方が多いのですか?
腎機能に問題があると診断され、病院からの紹介で来院される近隣の方が大半を占めています。私が日本糖尿病学会糖尿病専門医でもあることから、糖尿病のご相談も多いです。ただ開業当初から振り返ると、CKD(慢性腎臓病)という病名が浸透してきたのか、特定健診で腎臓の数値を指摘された方の受診が増えましたね。今も昔も「しっかり透析」、長時間の透析治療と、オンラインHDF(血液透析ろ過)を軸にする姿勢は変わりません。オンラインHDFは一般的な透析療法よりも、分子量が大きな老廃物の除去に対応します。そうすることで、10年、20年という長期間の透析に伴う合併症の予防や、血圧の変動抑制をめざす。それが主目的となります。当院の患者さんは、ほぼオンラインHDFです。私も月・金曜は泊まり込みで夜間透析に対応し、その他の日も、患者さん全員の透析治療が終わるまでサポートを続けています。
スタッフの皆さんのサポートも欠かせませんね。

スタッフの存在は、とても心強いです。看護師や臨床工学技士、管理栄養士の皆さんにも透析治療への理解を深めてもらうため、当院負担で、専門の知識や技術の習得をサポートしています。私だけでなく、全員がスペシャリストになる体制が目標です。患者さんとのコミュニケーションにおいても、豊富な知識があるほうがプラスになると思いますし、こうしたスキルアップはその後の彼らの人生においても、きっと役に立つことでしょう。
「脳・心・腎連関」を意識し広い視野で診療
患者さんと接する時は、どんなことを心がけておられますか?

外来でも透析でも、相手の立場に立って考える、それが私のモットーです。「自分が同じ病気なら、どんな治療を望むか」。「相手が自分の肉親だとしたら、どんな方向性で治療を進めるか」を必ず考えた上で診療を進めています。例えば血清クレアチニン値の数値が高い場合、患者さんは「腎臓が悪い」「CKDかもしれない」と考えがちです。しかし、実際は脳梗塞や心筋梗塞のほうがリスクが高いため、「全身の血管が傷んでいる」という認識のもとで患者さんを診る必要があります。「脳・心・腎連関」という言葉が生まれるほど、腎臓は脳や心臓と密接なつながりがありますので、さまざまな角度から診断し、そして対等な立場でお話しするようにしています。
クリニックの今後については、どのようにお考えですか?
透析導入に至る原疾患は、約40%が糖尿病、約14%が動脈硬化、高血圧症です。つまり、合わせて50%以上が生活習慣病で、そこから腎不全を起こすというパターンが大半を占めています。糖尿病治療が日進月歩で進化していますので、高確率で透析治療患者さんは減少し、透析医療は先細りになっていくでしょう。透析治療を残しつつ、どのような形態で診療を続けていくべきか、今は一般内科のウエートを含めて思案中です。在宅血液透析や腹膜透析についても、現状は患者さんの希望状況や生活環境などからなかなか実現していませんが、機会があれば取り組んでいきたいと思っています。
最後に、読者へのメッセージをお願いします。

血液検査などの際に患者さんにお話しするのは、「自分のことほどわからないものはない」ということです。自分では大丈夫だと思っていても、実は治療する必要があるケースは少なくありません。できるだけ客観的に、ご自分を見ていただきたいです。自分の心や体の状態を、違った目線から見つめ直すことはとても大切で、私自身も常にそう心がけています。腎臓と透析のスペシャリストであると同時に、内科のジェネラリストとして常に広い視野を持ち、皆さんをより良い医療、より良い人生へと導いていきたいです。






