山本 修 院長の独自取材記事
宇品メンタルクリニック
(広島市南区/宇品三丁目駅)
最終更新日:2021/10/12

広電1号線の宇品三丁目駅から徒歩5分の場所にある「宇品メンタルクリニック」は、山本修院長が2011年に開業して以来、多くの患者が相談に訪れる精神科・心療内科クリニックだ。近年、子どもの発達障害、若い層のうつ病などが社会問題になっている中、早くから子どものメンタルケアや発達障害の診療にも取り組みを続けてきた。開業前に勤務していた広島県立病院では、摂食障害の診療にもあたっており、他院で断られるような患者の受け入れもしている。山本院長に10周年を迎えたクリニックのこれからの展望について話を聞いてみた。
(取材日2021年7月7日)
いつでも気軽にメンタルの相談ができるクリニックに
精神科の医師になったきっかけを教えてください。

何か劇的なエピソードがあったわけではありません。中学や高校で先生の話を聞いていたら医学に興味を持つようになり、医学部に進みました。精神科を選んだのは、大学1年の時に受けた精神科の先生の心理学の授業がユーモアたっぷりでとても面白かったのが最初のきっかけでした。5年生になると進む科目を選ぶために各診療科の病棟を回るのですが、ここでもやはり精神科の教授や准教授の先生の話が面白く、それが決め手となった感じです。しかし私は先生たちと違って冗談も言えない性格です。心配になって先生に「精神科に進みたいんですけど、こんな僕でも大丈夫でしょうか?」と相談したら、「君は君で自分の良いところを伸ばせば良い精神科医になれる」と言われ、精神科に行こうと決めました。
開業をした理由は何ですか?
大学病院に勤務していた時に、私が配属された精神科には毎日大勢の患者さんが来られていました。新規の患者さんは何週間も待たせてしまう状態で、せっかく来られたのに診療時間外だからとお断りすることもあって、それがすごく心残りだったんです。心が苦しくて診てほしいと来られる患者さんに対し、もっと柔軟に対応したい、そういう思いから自分のクリニックを開業することに決めました。開業は2011年です。現在は月曜から土曜まで診療しており、予約制を敷いてはいますが緩やかなので予約なしで来られても大丈夫です。新患の方でもできるだけその日に診るようにしています。何かあって苦しい時に「予約がいっぱいで、新規の患者さんは1ヵ月先」と言われても、それまでに解消していたらいいけれど、本当に苦しい状態で1ヵ月も待たせてしまうことがないように、できるだけスムーズに受診できる体制を整えています。
通院される患者さんの年齢層や、症状などについて教えてください。

近所に新しいマンションができたり、小学校があったりするせいか患者は若い世代が多いですね。年齢でいうと20代から40代くらいが中心ですが、近年は発達障害の子どももいますので小学1年生くらいのお子さんも受診されていますし、上は90代の方もいます。ただ男女差でいうと、7:3の割合で女性のほうが多く通院されています。女性は社会進出でストレスにさらされたり、産後うつなどもあって多いのかもしれません。あと、近年若い世代の間で、インターネットやSNSでの交流が原因や引き金となって、うつ病や自殺が増えてきていますが、当院でも同じ理由で通院される方が以前より多くなっています。
町のかかりつけ医のように、いつでも頼れる精神科医に
診察室とカウンセリングルームと分けているのはなぜですか?
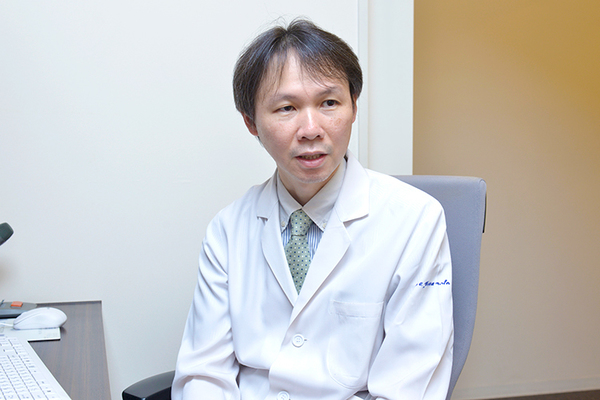
当院では、臨床心理士による心理検査や新しい薬の治験、広島大学病院精神科と共同で行う臨床研究などにも積極的に取り組んでおり、それらの用途に応じて部屋を使い分けています。また、心の病気のため、他の医療機関を受診することが難しい方のため、糖尿病や高血圧などの内科的疾患の治療を行うこともありますので、処置室も広めに取っています。
得意な分野はありますか?
摂食障害の診療ですね。以前、勤務していた県立広島病院では、40~50床あった精神科の入院病棟のベッドのおよそ半分を摂食障害の患者さんが占めていたこともあるほど摂食障害の患者さんが多かったので、私も多くの患者さんの治療に携わってきました。摂食障害には、極端に食事を制限してしまう拒食症と、その反動で一度にたくさんの食物を食べたり、食べた後に嘔吐するという過食症があり、いずれも患者さんの数は年々増加しています。主に若い女性に多い病気ですが、男性や中高年にも見られることもあります。極端に痩せている場合は、体の検査や治療を行わなければ、命に関わる場合もあるため、当院では薬の治療やカウンセリングを組み合わせて治療を行っていきます。
近年はメンタルクリニックを受診するお子さんが増えているそうですが、どのような症状が目立ちますか?

子どもの診療で多いのは、自閉スペクトラム症やADHDなどの発達障害です。最初は小児科に相談されると思いますが、診療できるクリニックが少ないのが現状です。当院では小学校1年生から診療をしているのですが、私自身も診療の引き出しを増やすため、隔週土曜に松田病院という児童思春期専門の病棟で診療をお手伝いしています。あとは、臨床心理士に週に1度来てもらい、お子さんの発達障害の有無を調べるため、心理検査や知能検査、カウンセリングをしてもらっています。
これからも患者の話をよく聞くことを心がける
患者さんの話を聞くときに気をつけていることは何ですか?
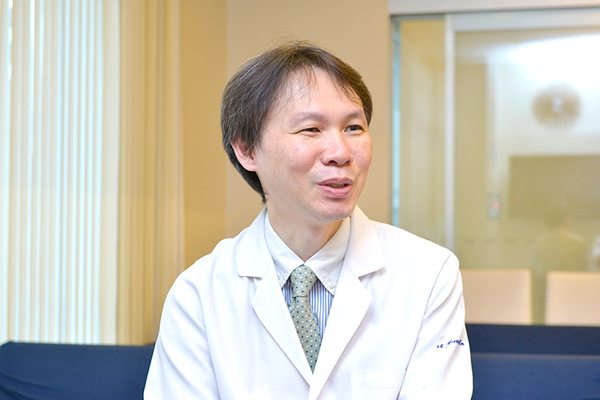
20年以上精神科医をやってきましたが、患者さんによく「先生は否定しない。先に飲み込んでから話してくれる」と言われます。これは無意識のうちにやっているので、ちょっとした癖なのかもしれません。いつもうまくいくわけではありませんが、患者さんの話に耳を傾けるようにしています。人は、心が苦しい状態の時、誰かがただ話を聞いてくれるだけで気持ちが楽になったりするものです。家族にも職場にも学校にも話せないくらい思い悩んでいる人が世の中にはたくさんいます。ですので、心の悩みや不安は話しやすくなるように、院内の雰囲気や環境をつくっていきたいです。
時代の変化とともに、メンタルの不調やのストレスのありようも変わっていますが、どう対処されていますか?
若い人中心に、SNSやゲームへの依存などの問題が発生していますね。例えば、今はオンラインで知らない人とゲームを楽しむことが当たり前の時代です。そういったネット事情に無知だと、医師として患者さんを診療することはできないので、情報収集は欠かせません。カウンセリングする時も「休みの日はゲームをしています」と言う方なら、一人でしているのか、誰かとしている場合それは友達か知らない人なのか、といったように、できるだけ状況を詳細に把握するために踏み込んで尋ねるようにしています。カウンセリングでは、話をしたことで患者さんに満足感や安心感を持ってもらい、また受診しようと思ってもらいたいので、信頼関係をつくることに重きを置いています。あいさつや礼儀、清潔感といった、人と接する時の基本的なマナーはもちろん、忙しいときほどゆっくり話をして患者さんを焦らせないよう気をつけています。
これからどういったスタンスで診療をしていこうとお考えですか?

開業してからこの10年間、「いつでも、誰でも、気軽に来られるクリニック」というスタンスで診療してきたので、これから先もそのスタンスは守っていこうと思っています。メンタル面で少しでも不具合を感じたら、いつでもすぐに相談できる、そんな町のかかりつけ医のようなクリニックであり続けることが私の目標です。少しでも心がつらいと思ったら、お話をするだけでも変わってくるかもしれません。ぜひ気軽にご相談に来てください。






