糖尿病、高血圧などにもつながる
睡眠時無呼吸症候群
みなとみらいクリニック
(横浜市西区/みなとみらい駅)
最終更新日:2024/10/11


- 保険診療
睡眠の質が低下することで、昼間に強い眠気に襲われ、交通事故にもつながる睡眠時無呼吸症候群。最近の知見では不整脈の誘発や、糖尿病など生活習慣病の重症化につながることが明らかになっている。「医療法人みなとみらい」は早くから糖尿病と「睡眠の質」の関連性に着目し、睡眠時無呼吸症候群の診断を重要視した専門クリニックを展開してきた。「みなとみらいクリニック」はその一院で、山川正院長は、大学勤務時代から同法人と連携して、糖尿病と睡眠の関連について数多くの臨床試験に取り組んできた経験を持つ。同院では睡眠時無呼吸症候群の精密検査施設も備え、睡眠時無呼吸症候群、糖尿病など生活習慣病、バセドウ病や橋本病といった甲状腺疾患の診療を行う。今回は山川院長に、睡眠時無呼吸症候群と糖尿病の診療について詳しく聞いた。
(取材日2024年9月25日)
目次
「睡眠の質の向上」を重視した糖尿病など生活習慣病の専門診療。睡眠時無呼吸症候群の精密検査施設も併設
- Q睡眠時無呼吸症候群は、糖尿病と関わりが深いとお聞きしました。
-
A
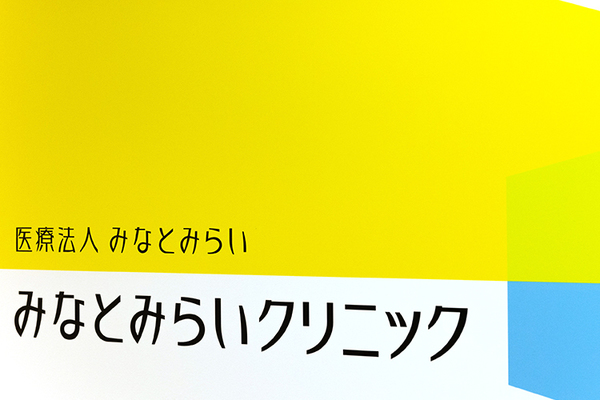
▲みなとみらい駅にあるクリニック
睡眠時無呼吸症候群で睡眠中の呼吸が弱まったり止まったりすると、血中の酸素濃度が低下して全身に酸素が行き渡らず、この状態が続くと脳がストレスにさらされ、血糖を上昇させるホルモンが過剰に出るようになり、糖尿病につながると考えられています。また血中酸素が低下することで交感神経が優位となり、心臓の働きが促進されて血圧や脈拍が上がり心臓や血管に負担がかかり、動脈硬化が促進されます。実際に糖尿病と睡眠時無呼吸症候群を併発する患者さんは多く、睡眠時無呼吸症候群の治療を行うと血糖値や高血圧に変化があることが多いとされています。欧米の糖尿病の治療ガイドラインでは生活習慣の改善として睡眠が重視されています。
- Q睡眠時無呼吸症候群の検査はどのように行うのですか?
-
A

▲宿泊して検査できる設備を整えている
まず、パルスオキシメトリー検査という簡易検査を行います。当院で貸し出した小さな機械を自宅で手首に巻き、一晩睡眠の状態を測定し血液中の酸素飽和度を測定して、検査結果から睡眠時無呼吸症候群の初期診断を行います。その結果により、「終夜睡眠ポリグラフィー検査(PSG検査)」と呼ばれる精密検査を行い、就寝中の脳波、呼吸、心電図、いびき、血液中の酸素飽和濃度などを一晩連続して記録し、詳しい診断を行います。当院では、宿泊して検査が行える専門施設を備えていますが、PSG検査は希望が多く、予約が先になってしまうようになってきましたので、在宅でも行えるPSG検査を導入して、希望される方にはご案内しています。
- Q睡眠時無呼吸症候群の治療について教えてください。
-
A

▲CPAP治療で使用する機器ついても、使用方法を丁寧に説明する
軽症の場合はマウスピースの使用や、横向きに寝る(側臥位)ことなどで睡眠時の呼吸の改善を図ります。中等症以上の場合は睡眠時に鼻にマスクをあてるCPAP(シーパップ)療法を行います。CPAP療法は強制的に空気を送り込み、呼吸が止まったときに気道を広げていく治療です。CPAP療法開始後に、呼吸に変化があるかどうかを確認するために、再度、PSG検査を行います。肥満が原因の睡眠時無呼吸症候群で減量した場合などは、CPAP療法から離脱できることもありますが、骨格などが原因の場合は、加齢によって気道がより狭くなることもありますので、永続的な治療が必要となることが多くなっています。
- Q糖尿病の合併症について教えてください。
-
A

▲処置室では、さまざまな検査が行えるように準備する
合併症として知られているのは、糖尿病網膜症、糖尿病腎症、糖尿病神経障害です。合併症が進行すると、失明や透析治療が必要となる腎不全、足の壊疽などが起こります。ただし、適切な治療の継続や、生活習慣の改善で血糖のコントロールができれば、合併症はそれほど進行しません。最近は、糖尿病網膜症や糖尿病腎症の治療も進展していますので、当院のような専門クリニックでの受診を続けていただくことが重要です。また、糖尿病で動脈硬化が進むことで脳卒中(脳梗塞・くも膜下出血・脳出血)や心筋梗塞など大血管障害のリスクが高まります。このリスクを下げるには、高血圧や脂質異常の治療や、動脈硬化の診療、禁煙治療なども必要です。
- Q糖尿病の検査や治療について教えてください。
-
A

▲患者のライフスタイルに合わせた治療方針を考えていく
血糖値やHbA1c、脂質、腎機能・肝機能の検査に加え、心電図、動脈硬化を調べる頸動脈超音波検査、血管の硬さや血管年齢を調べる血圧脈波検査などを行います。治療の基本は食事・運動療法で、よりよい血糖コントロールを得るために、内服薬やGLP-1製剤、インスリンなどを使うことがあります。合併症の予防や進行抑制の状態を維持するために、患者さんのライフスタイルや状況に応じた治療法をご提案し、管理栄養士による食事や栄養に関する個別のカウンセリングを行います。従来は厳格なカロリー制限を行っていましたが、最近は患者さんの食生活や生活習慣に合わせて、わかりやすく実際に取り組みやすい指導を心がけています。






