中村 雅一 院長の独自取材記事
なかむら内科
(吹田市/北千里駅)
最終更新日:2025/05/16
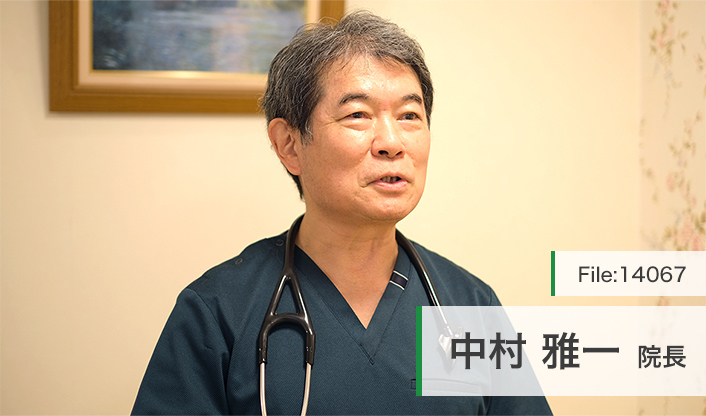
阪急千里線の北千里駅から徒歩1分の北千里医療ビルに「なかむら内科」がある。院長の中村雅一先生は、大阪府内の基幹病院などで長年にわたり脳卒中に代表される循環器疾患の診療にあたってきた。勤務医時代から一貫して、脳卒中にならないための生活習慣病の管理を提唱している。また神経疾患についても豊富な経験を持ち、数多くのパーキンソン病や頭痛の患者を診療している。一人ひとりの患者に見合った適切な処置とわかりやすい説明を心がけているという中村院長に、生活習慣病や神経疾患についての考え方や院長の人柄がうかがえる診療スタイルについて話を聞いた。
(取材日2017年11月16日)
幅広いケアを経験して、診療の裾野が広がった
医師を志したきっかけを教えてください。

中学2年生の時に、地域の耳鼻科で扁桃腺を摘出する手術を受けました。また、アレルギー由来の紫斑病という病気に罹患したこともあり、近所の診療所にずいぶんとお世話になりました。私自身は物理に興味を持っている“科学小僧”だったのですが、お世話になった先生方のように直接人の役に立つ仕事に憧れを持つようになったのがきっかけです。
大学病院では内科を専攻されたのですね。
最初は、心臓外科に憧れていました。その頃、神戸大学から新進気鋭の心臓外科のドクターが赴任してこられ、講義の際のさっそうとした雰囲気に憧れを抱いたのです。しかし、私は心臓外科の医師というキャラクターではないし、親戚の中で最初の医大生なので、親族みんなを診られる医師をめざそうと内科を選びました。心臓への興味は持っていたので循環器内科を専攻したのですが、より広範囲に心血管を診る研究グループに所属して、高血圧や脳卒中などについて学びました。
大阪大学医学部附属病院ではどんな患者さんを主に担当されたのですか?
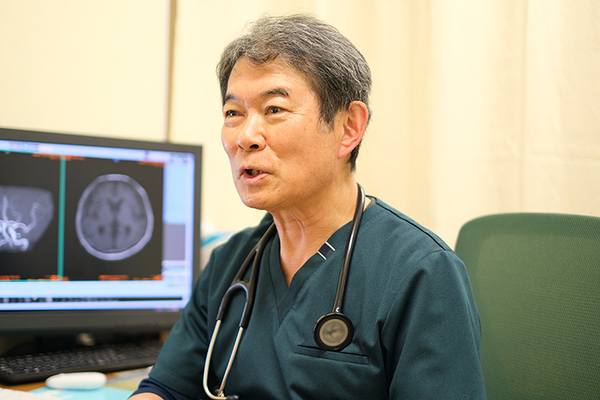
外来では、高血圧の外来、病棟では脳卒中やさまざまな血管の病気を担当しました。研修医の指導係も6年勤めました。内科とはいえ、脳卒中の急患が来られた場合などは、気管内挿管やカテーテルを通して血栓を溶かすよう図るなど、外科的な対応もこなしてきました。当時はまだ私も若かったので、華やかな一面もあり、治療の結果が早くわかる外科的な仕事にやりがいを感じていました。
その後、国立循環器病研究センターに勤務されます。
ここでも脳卒中の患者さんを担当しました。脳卒中にならないために高血圧、糖尿病、高脂血症、心臓の病気などについてケアするという私の診療方針の出発点になった場所でもあります。循環器病の専門機関なので年配の患者が多く、脳卒中以外の病気もケアする必要があるのですが、国立循環器病研究センターには循環器の医師しかいません。他の病院の専門医師に尋ねながら処置を行うか、その医療機関へ連れていくか、転院してもらうしか方法がなく、そういうことをしているうちに診療の裾野が広がります。するとその裾野の中に、自分が勉強すべきエリアがあることに気づきます。私の場合はそれが神経内科でした。国立循環器病研究センターに、7年勤務した後、大阪大学神経内科に転勤し、そこで神経内科の研鑽をしました。
一人ひとりに適した治療、本当に必要な治療を行う
どんな患者さんが多く来られますか?

開業当初は、国立循環器病研究センターに通院される患者さんで、地域の医療機関に戻っても、大丈夫だろうという方々を紹介していただきました。このため、現在も循環器疾患の患者さんが多く受診されます。また、高血圧をはじめとする生活習慣病に力を入れていることを知って、お越しくださる方も多くいらっしゃいます。神経内科についてはクリニックの数自体が少なく、パーキンソン病や頭痛、あるいは手足のしびれや動きの不調などを訴える患者さんが、地域のさまざまなクリニックからのご紹介で受診されます。
生活習慣病についての先生ご自身の考え方を聞かせてください。
遠い将来に心筋梗塞や脳卒中になるリスクが高くなるので、できるだけ早い段階から生活習慣病を管理しましょうというのが基本姿勢です。しかし実際は、多くの方が血圧やコレステロール、血糖値などの数値を見て受診されます。私自身は、数値が高いから受診するのは、成績が悪いから塾に行きなさいというのと同じで、違和感を覚えます。むしろ、その方がどんな人生を歩みたいのかが大切です。高齢者でつつがなく生活しておられる方に対しては、無理に数値を下げる必要はありません。また、同じ数値でも患者さんによって深刻度が異なります。例えばコレステロール値が高い場合、高血圧など他の病気がないか、家族歴はどうかといったバックグランドが重要です。私がいつも患者さんにお話ししているのは、なぜ数値を下げなければいけないのかを理解して、治療に目的意識を持つということです。
患者さんごとに治療内容は異なるということですね。

しっかりと問診をして、必要な場合のみ検査をして、総合的に判断します。その結果、数値が高くても薬を出さないこともあります。いったん薬を飲み始めると、ずっと続けなくてはいけないと考えておられる方が多いのですが、薬はあくまで「道具」で「目的」ではありません。治療の目的は「脳卒中や心筋梗塞のリスクを下げること」です。生活習慣病の場合、食事などの生活改善に取り組みますが、それで良い結果が得られない場合に、薬という「道具」でサポートします。
元気や勇気を持って帰れるクリニックが目標
神経内科を診療する際のポリシーを教えてください。

神経疾患は2つのタイプに大別できると思います。1つは神経難病と呼ばれ、治療の方法がいまだに確立されていないものです。もう1つは、現在では治療が可能なタイプの疾患で、私が得意とするパーキンソン病と頭痛がそれにあたります。神経内科の医師の中には、難病や新しい病気の研究に注力する傾向がありますが、治療の過程がわかりやすい循環器の病気を専門としてきた私は、やはり神経内科疾患においても「治したい」と思います。私が神経内科の領域で何をすべきかを考えると、必然的に薬やリハビリテーションで改善が見込める病気の治療となり、パーキンソン病と頭痛を専門的に扱うようになりました。
講演会などは行っておられますか?
医薬メーカーに協力してもらって、年に4回程度、セミナーを開催しています。地域のクリニックの先生に参加してもらい、私たちが講師とテーマを選んで、本音で話し合います。また、自治体などの要望を受けて、地域の住民を対象にした講演も行っています。
読者にメッセージをお願いします。
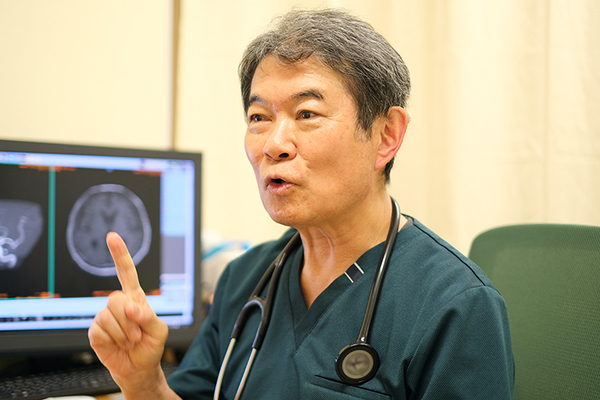
多くの人は医療機関へはできれば行きたくないと思っておられることでしょう。でも、元気になれるところなら、行こうと思いませんか? 私は来院された時はつらそうな表情をしていらした方も、帰られる時には笑顔で、元気や勇気を持って帰っていただけるようなクリニックをめざしています。診療には、適格な問診と必要最小限の検査で的確な診断をするトレーニングを積んできたつもりです。不調や悩みがあれば、どうぞためらわずにご相談ください。






