門田 吉見 院長の独自取材記事
かどた耳鼻咽喉科クリニック
(松山市/山西駅)
最終更新日:2021/10/12

伊予鉄道高浜線・山西駅から車で6分。田んぼが広がり、近くを川が流れるのどかな住宅街にある「かどた耳鼻咽喉科クリニック」。広い駐車場が用意され、自家用車でも通院しやすい環境が整っている。門田吉見院長は、副鼻腔炎、中耳炎、アレルギー性鼻炎など耳鼻咽喉科に関わる症状のみならず、子どもから高齢者まで地域の幅広い世代の患者の多岐にわたる相談に応じている。開院から20年以上たち、近年は、子ども時代に同クリニックに通っていた患者が、結婚して自分の子どもを連れて来院することもあるという。大学病院などで培った知識・技術や医師同士のネットワークを生かし、長年地域医療に貢献してきた門田院長に、耳鼻咽喉科の診療にかける思いなど、じっくり話を聞いた。
(取材日2020年08月20日)
大学病院などでの経験を生かし、幅広い診療に取り組む
耳鼻咽喉科の医師になられた経緯をお聞かせください。

高校卒業後、愛媛大学医学部に進学しました。当時は医学部を卒業するとすぐにいずれかの診療科に配属になるため、5回生、6回生の時にすべての診療科を見て回る実習がありました。愛媛大学医学部附属病院のほか、愛媛県立中央病院や松山赤十字病院を見学する機会もあり、自分に一番合っていると感じた耳鼻咽喉科に進みました。もともと外科系を希望していて、耳鼻咽喉科も外科的領域があって興味深かったことと、何より医局の雰囲気が良かったことが決め手になりましたね。臨床においても研究においても、充実した仕事ができるのではないかと強く感じたんです。
大学卒業後は、県内の複数の基幹病院で経験を積まれたのですね。
大学卒業後は、愛媛大学医学部附属病院などでの臨床研修を経て大学院に進学。その後、鷹の子病院、愛媛大学医学部附属病院、松山赤十字病院などで経験を積み、1999年に当クリニックを開院しました。11年ほどの勤務医生活で耳鼻咽喉科全般の知識・技術を習得し、年齢的にもちょうどいいタイミングだったと思います。勤務医時代は特に喉関係、発声・嚥下を専門としていました。松山赤十字病院では嚥下の検査にも携わっていたので、今でもオファーがあれば月に何度か手伝いに行っています。
クリニックに来られる患者さんの症状で多いのはどのようなものですか?
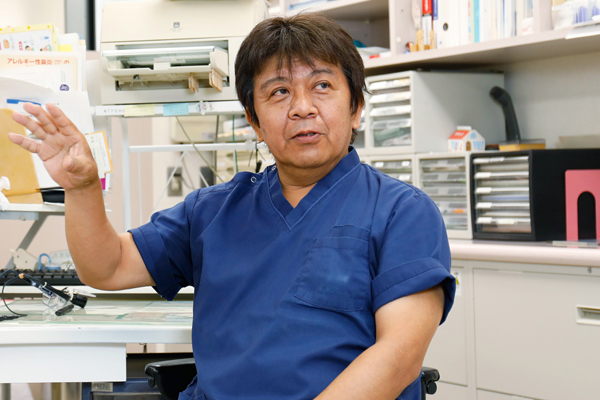
一番多いのは風邪からくる感染症や副鼻腔炎、アレルギー症状です。近年アレルギー性鼻炎は増加傾向ですね。よく知られているのはスギとヒノキですが、花粉は真夏を除いてほぼ1年中、さまざまな植物から飛んでいるんです。ここ数年は飛散量が多い年が続きましたが、今年はスギ花粉の飛散量が極端に減るなど、年によって状況はかなり違いますね。お子さんの症状で多いのは、風邪から中耳炎を起こして、その後鼻の具合がなかなか良くならないといったケース。夏はプールに入る機会が多くなるため、外耳炎も増えます。お子さんの場合、小児科と耳鼻咽喉科を並行して受診するようお勧めすることもありますね。またご高齢の方では、難聴で来院される患者さんが多くいらっしゃいます。聞こえが悪くなったとのご相談を受けて検査を行い、補聴器をつくることになれば、専門の補聴器店を紹介しています。
耳鼻咽喉科全般に対応。患者に寄り添った診療を重視
耳鼻咽喉科の診療範囲はかなり広いのですね。

首から上の症状はすべて耳鼻咽喉科の領域ですね。喉の疾患としては、声枯れを訴える方が多いです。この場合、声帯だけの問題なのか、それとも神経の問題なのかをしっかり見極める必要があります。また声枯れは胃酸の逆流が原因で起こることもあるので、内科に紹介して胃カメラ検査を受けていただくこともありますね。気管食道科の疾患としては、反回神経まひや声帯まひといったものもあります。がんが隠れていないか、神経が走っているところに大動脈瘤などの原因がないか、注意深く診ていきます。耳に関しては、突発性難聴は年齢に関係なくかかる病気で、原因ははっきりとわかっていません。たいていの場合、入院治療をお勧めします。めまいやメニエール病を訴える方も少なくありません。脳腫瘍がないかどうかしっかり確認することが重要です。そのほか、甲状腺などの病気を疑う場合にはエコー検査も行いますし、顔面まひも耳鼻咽喉科の領域です。
先生が診療のモットーとされていることを教えてください。
とにかく耳鼻咽喉科に関することは全般的に、できる限り対応するということです。首から上に現れる症状は全部診ていますので、口腔がんなどを発見することもあります。患者さんから違和感があると言われたところは特に念入りに、あらゆる可能性を考慮して診察して、重大な病気を見逃さないことが重要ですね。喉の症状を訴える患者さんの場合、咽頭がんも疑われますから、まずは目視で診察し、見えにくいときには咽頭ファイバースコープ検査を行います。耳鼻咽喉科のファイバースコープ検査は基本的に鼻から挿入するため、それほど苦痛はありませんのでご安心ください。何よりも、かかりつけの耳鼻咽喉科クリニックとして病気を見逃さないこと、そして適切な治療につなげることが重要であると考えています。
患者さんに接する際、どのようなことを心がけていますか?

できるだけ満足していただけるように、ということは常に意識してます。まずどんなことで来院されたのかお聞きして、診察を行い、どのような検査をするべきかお話しします。そして必要な検査をして、何もなければ安心して帰っていただけますし、何か異常が見つかれば早期に治療を開始します。例えば副鼻腔炎などの場合、手術が必要なレベルなのか、それとも通院での処置と服薬で治療できるのか、その診断をするのが当クリニックの役割です。また、こちらが手術したほうがいいと判断しても、患者さん自身が手術を避けたいと言われることもあるので、無理強いはせず、「薬で頑張ってみましょうか」ということになる場合もあります。患者さんの意向に寄り添うことは大切ですね。また、患者さんが苦痛を感じないように配慮することも重要です。お子さんの場合、初めは怖がって泣くのは仕方がありません。たいていは慣れれば治療を受けられるようになります。
他科や専門医療機関と連携し、適切な医療を提供
地域医療においてどのような役割を担っていきたいとお考えですか?

耳鼻咽喉科の疾患についてはもちろん、風邪などでもまずはご相談いただければと思います。必要だと判断すれば、内科や小児科にご紹介することもありますし、もし手術が必要な状態であれば、適切な専門医療機関にご紹介します。相談窓口のような感覚で来ていただきたいですね。当クリニックに通っていただくことになれば、患者さんとコミュニケーションを取りながら、納得していただける診療を提供します。患者さんが頑張って症状が治まって、「もう治ったから来なくてもいいですよ」と言える状態になるまで全力でサポートしますよ。それが私のやりがいですから。
お休みの日や診療時間外はどのように過ごされていますか?
趣味のゴルフは勤務医時代から20数年続けています。また、耳鼻咽喉科の医師仲間で集まって食事をしながらお酒を楽しむのも、貴重な情報交換の場になっていますね。今年は新型コロナウイルス感染拡大の影響で、もっぱらオンライン飲み会です。みんなで情報を共有し、各自が日々の診療に生かすことで、患者さんにしっかり還元していきたいと考えています。わが家は子どもたちが家を出ていますので、夫婦で晩酌することもありますね。いずれにせよ飲み過ぎは禁物。週に1日は完全休肝日を設けています。
最後に読者にメッセージをお願いします。

私自身は、体が続く限り診療を続けたいと思っています。喉の痛みや風邪の症状などでお困りのときは、耳鼻咽喉科にご相談ください。ちょっとした異変から大きな病気が見つかることもありますので、違和感があれば放置しないでいただきたいですね。内科や小児科などと比べると、耳鼻咽喉科は敷居が高いと感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、決してそんなことはありません。首から頭までのことでしたらなんでもお気軽にご相談ください。






