松田 治己 院長の独自取材記事
松田クリニック
(さいたま市浦和区/北浦和駅)
最終更新日:2025/07/28

JR北浦和駅西口より徒歩約5分。商店街の一角に構えるメディカルビルの3階にある「松田クリニック」。内科診療とともに、漢方専門の外来も実施していることで知られるクリニックである。それぞれの分野を限定して診るのではなく、患者の症状を鑑み西洋医学、東洋医学双方の知見から行う包括的な診療が特色。従来の治療では改善が見られなかった患者が多く来院している。院長を務めるのは松田治己先生。富山大学在学中、自身が患った疾病に対して漢方治療を受けたことから、その奥深さを実感。以来、研鑽を積み漢方専門の医師として診療を続けるプロフェッショナルだ。クリニックの概要や特色、診療でのこだわり、医師をめざしたきっかけなどについて、松田院長に聞いた。
(取材日2015年5月29日)
気軽に訪れられる漢方専門の外来があるクリニック
クリニックはいつ頃の開院ですか?

2000年のことです。開院当初、このさいたま市はなじみの土地ではなく、不安もありました。でも、医局の先輩が院長を務めている「土佐クリニック」が桜区にあり、また、この地域は健康意識の高い方が多く、スムーズに診療体制を整えることができました。開業医として研鑽を積み、日々の患者さんと向き合いながら、今年で25年。あっという間ですね。これからも、健康と地域医療に貢献できるよう、誠心誠意診療にあたっていきたいと考えています。
先生の経歴をお聞かせください。
富山医科薬科大学(現・富山大学医学部)を卒業後、和漢診療室に入局。松戸市立病院、新潟のゆきぐに大和総合病院などで臨床経験を積み、母校に戻って博士号を取得し、教育・研究に携わってきました。助教授として学生を指導する傍ら、臨床の現場にも深く関わり、医療現場の多様なニーズに向き合ってきました。その後、富山県立中央病院にて和漢診療科科長として診療を続け、これまでの経験を生かして当院を開院する運びとなりました。漢方医学との出会いは学生時代。椎間板ヘルニアの痛みに悩んでいた際、和漢診療室の先生に漢方を処方していただいたことです。その体験が、私の進路を大きく変えるきっかけとなり、卒業後に本格的に漢方医学を学ぶ道を選びました。現代医療の中で、漢方が果たせる役割は決して小さくないと確信しています。日々の診療を通じて、その可能性を一人でも多くの患者さんに届けていきたいと考えています。
漢方専門のクリニックなのですね。

そうです。ただ、これまで一般内科、神経内科領域にも研鑽を積んできましたので、東洋医学つまり漢方が築いてきた英知を現代医学に取り入れ、包括的な治療・医療を試みているクリニックでもあります。一般内科領域では、循環器疾患を中心に呼吸器や消化器、内分泌代謝で、心臓カテーテル検査、運動負荷試験などに携わり、虚血性心疾患の治療および管理。そして、神経内科領域では、脳血管障害急性期および慢性期の治療と管理、パーキンソン病などの変性疾患の治療も行っていました。パーキンソン病では、脳内伝達物質の解析を手法として研究を行い博士号を取得しています。
症状改善をめざすだけでなく、体の仕組みを整える漢方
東洋医学および漢方について教えてください。

まず、東洋医学や漢方と聞くと、とても歴史が古いものというイメージがあるかと思います。実際そのとおりで、東洋医学、とりわけ日本漢方の原点は中国の古典医学。集大成化されたのは、漢時代にさかのぼります。それが伝来し、日本の風土や日本人の体に合うように研究されて、日本漢方が誕生。今日に至るわけです。ここで興味深いのが、中国の古典医学を継承しているのが日本の漢方だということなんです。どういうことかと言えば、現代の中国では、近代になり発達した新たな医療体系である中医学が、伝統医学の中心になっています。つまり、中国の古典医学のベースとなった書物を礎としているのは、中国ではなく、実は日本なんです。
漢方治療には、どのような特色がありますか?
漢方医学では、古典医学の代表的な書物などをもとに、患者さんの病態に応じた有用な方剤が示されています。その診断法は「証」と呼ばれ、病状・体質・症状の現れ方から導き出される漢方独特の考え方です。近年は科学的根拠や臨床データも加味しながら、より実践的な処方が行われています。対象疾患は幅広く、高血圧・糖尿病などの生活習慣病や椎間板ヘルニア、アトピーや喘息などのアレルギー性疾患、更年期症状、肩凝り・めまい・不定愁訴、ストレスなど多岐にわたります。漢方単独はもちろん、現代医学の補助として併用されることも一般的です。漢方最大の特徴は、「病気」そのものではなく、「患者さんの病態」に目を向ける点です。西洋医学では原因や患部に直接アプローチする薬が中心ですが、漢方は病気によって変化した心身の状態を整えることによって、症状や疾患全体の改善をめざします。まさに患者さんの全体像に寄り添う医学といえます。
漢方専門の医師として今、発信しておきたいことはありますか?

先ほどのお話と引き続きになりますが、病態や体の変調を改善に導き、身体を健康な状態に整えていくための治療であるということは、積極的に発信しておきたいですね。最近では西洋医学の先生方も使われるようになりましたが、東洋医学には「未病」という言葉があります。「未ダ病ニナラザル」状態のことで、簡単に言えば疾病予備軍、健康以上病気未満といったところです。予防が社会において重要なキーワードになっている現代、この未病への対策が欠かせないのは明らかですが、ここに大きく貢献できるのも漢方であると感じています。
なかなか症状が改善しないときの一つの選択肢として
医師をめざしたきっかけを教えてください。

医師を志すきっかけは中学生の頃、親族が病気を患ったことでした。とはいえ当時は漠然としたもので、航空機関係やものづくりの技術者にも憧れを抱いていたため、医師は数ある夢の一つでした。高校時代に将来を具体的に考えるようになり、医師の道を選びました。今思えば、親族の病気を通して医療の力を実感したことが大きかったのかもしれません。大学ではテニスサークルに所属し、釣りやトレッキング、合宿など充実した日々を過ごしました。そんな中、漢方医学との出会いとなったのが「赭鞭(しゃべん)会」というクラブ活動です。赭鞭とは、薬の神・神農が薬草を見極めるために使った赤い鞭に由来する言葉で、薬用植物や漢方医学を学ぶサークルです。顧問の故・難波先生をはじめ、そこでの出会いや学びがなければ、漢方専門をめざしていなかったかもしれません。現在も赭鞭会は活発に活動しているようで、私にとって原点とも言える大切な場所です。
休日はどのようなリフレッシュをしていますか。
昔はいろいろなスポーツを楽しんでいましたが、最近はゆったりと過ごすことが多いですね。何もしない、これがいちばんのリフレッシュです(笑)。あと、これは仕事につながることですが、漢方や食事療法などの研究をライフワークとしていて、やりがいを感じるとともに楽しんで行っています。同じ症状でも結果は異なり、ある患者さんは著しい効果が望め、一方の患者さんは乏しいこともある。漢方専門の医師が語るのも何ですが、漢方は、いくら研鑽を積んでも足りない、奥深さがありますね。
最後に、読者に向けてメッセージをお願いします。
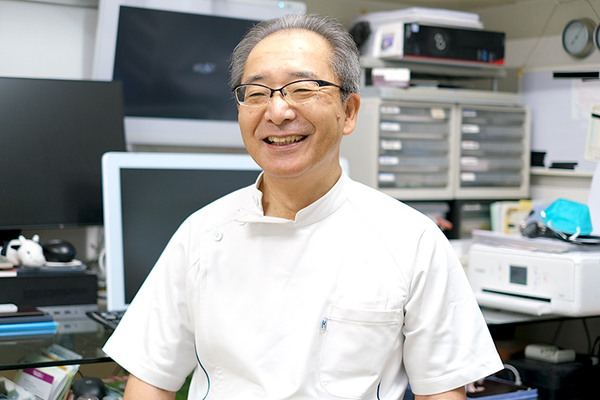
漢方を中心にお話ししてきましたが、その優位性を語るものではありません。医療の中で健康に貢献する一つの選択肢として漢方もあると、考えていただけばよろしいかと思います。また、当院もそうですが、最近は現代医学と東洋医学を合わせ、診療にあたる診療所も増えています。漢方も年々、身近になっていますので、興味のある方は、一度足を運んでみてはいかがでしょうか。そして、「なかなか症状が改善しない」という悩みをお持ちの方へ。現代医学と東洋医学では、お伝えしてきたようにアプローチが異なります。漢方で改善可能な場合もありますので、ぜひお気軽にご相談ください。当院は、これからも治療だけではなく、予防も含め、皆さまの健康、ひいては生涯にわたる豊かな生活に貢献できるよう、診療に尽力していきます。






