治療の終わりがスタート
太田歯科医院の定期検診
太田歯科医院
(交野市/交野市駅)
最終更新日:2025/07/02


- 保険診療
歯が痛い、歯茎に違和感がある、歯の詰め物が取れたなど、何らかの症状や困っていることがあると、私たちは慌てて歯科を受診する。その一方で、痛みなどがない状態であっても、定期検診で歯科に通う習慣を持つ人も少なくない。「歯科はトラブルを治療するだけでなく、問題を未然に防ぐため、あるいはできるだけ早い段階で見つけるために通う場所でもあります」と話すのは「太田歯科医院」の太田貴之院長。同院では、治療が済んだ後も多くの人が定期検診のための通院を継続しているという。太田院長に、治療のための受診から定期検診までの流れや定期検診の大切さ、予防歯科に注力する同院の取り組みなどを解説してもらった。
(取材日2025年6月4日)
目次
検診・治療前の素朴な疑問を聞きました!
- Q患者さんはどのような理由で受診されますか?
-
A
治療のために来院する患者さんもおられますが、検診を受けたい、歯をクリーニングしてほしいといった理由で受診される方も少なくありません。当院の場合、長期間にわたって検診を続けている患者さんが多く、ほかの歯科医院で定期検診を続けてきたけれど、転居によって通うのが難しくなったからとお越しになる方もおられます。強い痛みなどを訴えて急ぎで来院した患者さんに対しては、定期検診を続けていれば「こんなに大変な思いをすることはありませんでしたよ」と、予防歯科の重要性を説明するように心がけています。しかし、忙しい方が多いのか、その後の検診が続かない、予約がキャンセルになるというケースも目立ちますね。
- Q定期検診についてのこちらの取り組みを教えてください。
-
A
3ヵ月おきの検診を基本に、患者さんのお口の状態やお手入れの状況によって、適した頻度をご案内しています。虫歯や歯周病の心配が少ない方などは、間隔が長くなりますが、それでも半年に1度は診させていただきます。検診については、60分程度のゆとりの時間枠を設定しており、毎回決まった歯科衛生士が診療を行う、歯科衛生士担当制を採用しているのも当院の特徴です。お口の中のチェック、歯石の除去や歯の表面の清掃、着色汚れの除去など、検診の際は行うことが本当に多く、短い時間枠では丁寧な対応は難しいからです。また、担当制にすることで、患者さんのお口の状態をよく知った歯科衛生士が診療にあたれるのが利点です。
- Q予約のキャンセルについて何か規定はありますか?
-
A
キャンセルに対してペナルティーを与えるのではなく、前日に電話を差し上げるなど、こちら側が努力してリマインドするようにしています。実のところ、罰則を設けるほうが当院としては楽です。例えば、2回無断キヤンセルすると、予約が利用できなくなるなどすればいいだけですからね。しかし、ご高齢の患者さんの場合は、認知症のために予約を忘れてしまうこともあるので、ご自身の都合でキャンセルされる方と同じように扱うわけにはいきません。一方、ご自身の都合でのキャンセルが多い患者さんには、前日に患者さんの方から確認の電話連絡をしてもらい、電話がない場合はキャンセル扱いにするなど、対応について現在も検討中です。
検診・治療START!ステップで紹介します
- 1予約と受診受付、問診票の記入
-
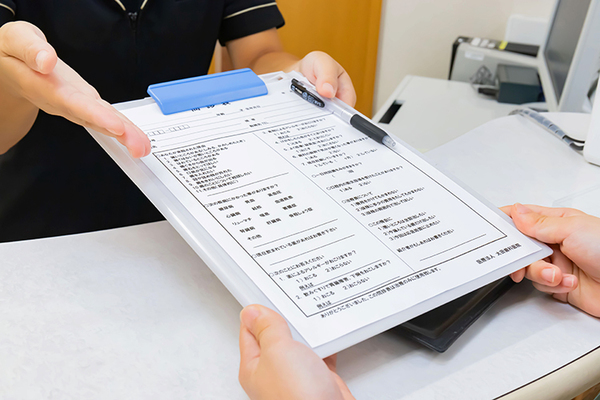
同院では、スムーズに診療を進めるために予約優先制が採用されており、予約は電話のほか、ウェブからも取ることができる。予約をキャンセルしなければならない場合は、電話で速やかに連絡。ウェブ予約の場合は、キャンセルは3日前までとなっている。1回目の受診は、問診票を記入する必要があるため、予約時間の15分前までに受付を済ませるようにしたい。
- 21回目の診療:痛みが強い場合
-

問診票に記載した症状や診療に対する希望などによって、60分の時間枠内の配分や提供される診療内容が異なる。痛みを訴えている患者の場合は、まずは痛みを抑えるための処置を行った上で、今後はどのような治療が必要となるのか、院長から説明を受ける。同院では、口の中の様子や治療法についての説明画像などを、診療台に設置された大型モニターで確認しながら説明を受けることができる。
- 31回目の診療:検診希望の場合
-

痛みはないものの気になるところがある場合や、検診を希望して受診した場合は、60分の時間枠のうち院長が30分程度、歯科衛生士が30分程度を受け持つ。まず院長が口の中の状態を確認して、患者の訴えのほかに問題がないかチェック。小さな虫歯の場合は、この時間枠内で対応できるケースもある。残りの時間は、担当の歯科衛生士が歯のクリーニングやブラッシング指導などを提供する。
- 4精密検査とカウンセリングの後、本格的な治療の開始
-

本格的な治療が必要な場合は、基本的に2回目の受診以降の対応となる。同院では歯科用CT、口腔内スキャナーといった先端の機器を備え、必要に応じてそうした設備を使って詳しい検査が行われ、患者ごとに治療計画が立案される。その後、治療計画についての詳しい説明やカウンセリングが実施され、計画に同意した場合は、本格的な治療がスタートする。
- 5定期検診を継続
-

治療の完了後、再び悪くならないよう定期検診のプランが提案される。検診の頻度は、3ヵ月ごとを基本に、患者の口の中の状態や手入れの状態によって調整。状態が改善されれば、受診の間隔が広くなることもある。検診時には、院長が口の中の状況をチェックし、担当の歯科衛生士がクリーニングや歯磨き指導などを行う。患者に合わせたきめ細かなケアやアドバイスが提供できるのが歯科衛生士担当制のメリットだ。
※歯科分野の記事に関しては、歯科技工士法に基づき記事の作成・情報提供をしております。
マウスピース型装置を用いた矯正については、効果・効能に関して個人差があるため、必ず歯科医師の十分な説明を受け同意のもと行うようにお願いいたします。







