田中 彰 院長の独自取材記事
田中彰レディスクリニック
(横浜市都筑区/センター北駅)
最終更新日:2024/06/14
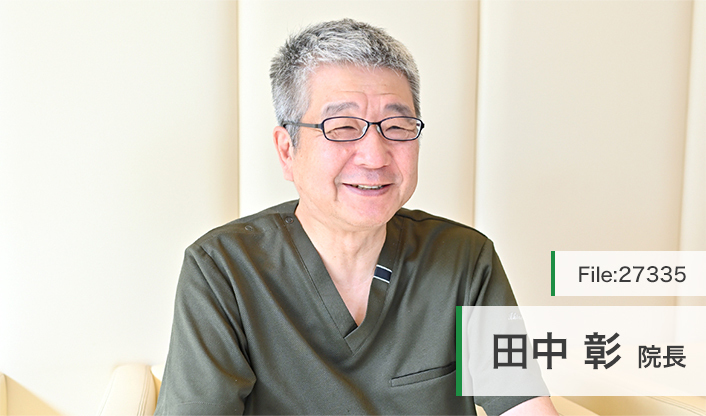
「おめでとう」と患者を祝福できる診療科であることに惹かれて、産婦人科を選択したという「田中彰レディスクリニック」の田中彰院長。大学病院や基幹病院で多くの産婦人科診療に携わり、豊富な診療経験と専門性を持つベテランドクターだ。田中院長は自身の診療方針について、「基本的に慎重で怖がりなので、二重三重に安全策を講じ、患者さんが納得するまで十分に説明を行います」と話す。常に患者の立場を考えた診療姿勢も印象的で、クリニックの端々にも、デリケートな悩みを抱える患者が受診しやすい心配りが感じられる。「困った時は遠慮せず相談してほしい」と言う田中院長に、産婦人科診療への思いやクリニックの特徴を聞いた。
(取材日2024年5月14日)
大学病院などでの豊富な診療経験と専門性を生かして
まず、産婦人科の医師を志したきっかけを教えてください。

医学部時代、各診療科の講義や実習を経験する中で、「おめでとう」と患者さんを送り出せるのは、産科しかないのではないかと思ったからです。おめでたいから、明るいなと。もっとも実際に産婦人科に入局してみると、お母さんと赤ちゃんの2人を同時に診る必要があり、深刻な症例も多く、甘いものではないということがすぐにわかったのですが。また当時は、このように人口が減少したり、お産が減ったりするとは思っていませんでした。統計上分娩数が減ってくるのは感じてはいましたが、当時は休む間もないぐらい分娩を手がけていましたし、ここまで少子化が進むとは思っていませんでしたね。
開業されるまでの経緯をお聞かせください。
日本医科大学の産婦人科に所属して、千葉北総病院など関連病院に勤務し、横浜赤十字病院では産婦人科部長を務め、横浜市立みなと赤十字病院への移行も経験しました。分娩や悪性腫瘍の手術など、産科婦人科のさまざまな診療に携わる中で、婦人科疾患や不妊症などについて家族や友人にも相談できず、一人で悩まれている方がとても多く、じっくりと対話を重ねながら患者さん自身が求める答えを一緒に探していきたいと考えるようになったのです。私の専門性や経験を生かした外来診療を提供したいと考えて、当クリニックの開業に至りました。この場所を選んだのは、今まで関わってきた大学病院や基幹病院との連携も考えてのことですね。
開業の際、どのようなところにこだわりましたか?

患者さんがなんでも相談しやすいようにプライバシーに配慮して、安心、安全、くつろぎ、ゆとりのある診療を提供したいと考えました。ですから、院内は患者さん同士や患者さんとスタッフの動線が重ならない構造ですし、カウンセリングルームは完全個室です。診療面では、ある程度厚みのある診療、専門的な診療を提供できる設備を整えています。中等度の細胞異形まで診ることができるので、大学病院から逆紹介されることもあります。また不妊症や不育症にも対応し、産婦人科全般で患者さんが困った時に相談に乗れるようにと考えていて、それは実践できている気がしますね。
安全を重視した診療と患者との十分な対話を心がける
診療の際に、大切にされていることを教えてください。

望まれて妊娠した方には「おめでとう」と声がけをしています。妊娠も出産もおめでたいことなので、携帯で撮影してもらったり、USBメモリーなどを持ってきてもらえれば超音波の画像データもお渡ししています。おめでたい結婚式や七五三で写真撮影を断らないのと同じことです。一方で、分娩をはじめ診療に大きな責任も発生するので、そのリスクを背負っていることは常に意識しています。「まだですか?」と言われたりはしますが大きなトラブルもなく診療に携わることができています。ある意味とても慎重で怖がりなんですよ。ですから検査や診察は入念に行いますし、治療を行う前にしっかり説明して、患者さんが「聞いていない」と不安に思うことがないように努めてきました。
患者さんとの対話を大切にされているのですね。
はい。子宮がん検診の結果一つをとっても、当院は対面での説明が基本です。検査結果を郵送したりPDFをスマートフォンに送ったりする施設もあるようですが、私は見落としや抜けがないように、また、必要な人はきちんと精密検査を受けられるようにと考えて詳しく説明しています。婦人科の検査を受けたけれど、「結果の見方がよくわからない」「異常がないのか不安」と困った経験のある人は多いのではないでしょうか。例えば子宮頸がんの検査では、子宮頸部の状態をベセスダ方式という方法でNILM(異常なし)、ASC‐US(正常〜軽度異形成の疑い)などと分類するのですが、異常のグレードがいろいろあってわかりにくいのですね。そのため直接、患者さんへの丁寧な説明は欠かせないと思っています。
わかりやすく説明してもらえると安心できます。

そうなんですよ。患者さんから相談された時に、「判断するのはあなた自身です」と突き放すのではなく、きちんと副作用などリスクについても踏まえた上で、取り得るほぼすべての方法をお話しし、その患者さんにとって一番合っている方向を決めていっています。そのため、患者さんが不安に思ったり気持ちがぐらついたりしないようにと心がけています。また、子宮頸がんのワクチンについては、副作用についてよくお話しした上で、検討していただいています。ただし、接種したほうが良いというスタンスで対応しています。
月経不順から不妊症まで困った時に頼りになる存在に
かかりつけの患者さんの急変などの際は、夜間も電話対応されているそうですね。

開業当初から、夜も24時間体制で対応しています。「何かあったら自分が責任を持たないといけない」と覚悟しながら診療をしています。しかしながら、急変やトラブルは起こりにくくて、意外と緊急の電話がかかってくることは多くはないものなんですよ。というのも、二重、三重に安全策を講じて慎重に診ている上に、「こういう場合はこうしてください」「こうなったら、夜でも電話してください」と詳しく説明して理解してもらっているので、患者さんの安心につながっているのだと思います。自分が担当する患者さんに責任を持つ方針は、勤務医時代から今日に至るまで変わりません。当クリニックでも同様の診療方針で患者さんに向き合い続けて、今日に至ります。
先生の立場から、現在気になっていることなどがあれば教えてください。
生理不順で低容量ピルを服用されている方がとても多いようです。ピルは正しく使えば有用ですが、40代以降の方は血栓症のリスクが高くなりますし、逆に10代後半の場合は、妊娠のプロセスまでを説明して将来のことを考えた上でピルなどの治療を選択してもらうようにしています。将来の妊娠を考えると今一度ちゃんと排卵ありの月経がくる術を確認してからピルなどを開始します。また、開業医は総合診療科的な側面もあるので、産婦人科を軸にして他の診療科についてもある程度のアドバイスを行い、必要な治療につなげていくことが必要だと思っています。例えば「めまい」は更年期障害だろうと考える方が多いのですが、原因が脳神経疾患ならば命にも関わるので、まずは脳神経外科、次は頻度が高い耳鼻咽喉科へとおつなぎします。患者さんが必要な医療につながるように道筋をつけるのが開業医の役割だと考えています。
最後に、読者へのメッセージをお願いします。

女性の場合、体の不調や悩みなどは産婦人科を受診していただくと良いと思います。PMS(月経前症候群)なども、産婦人科を受診してコントロールを図ることで改善が期待できることが多いので、ぜひご相談ください。また、インターネットの情報には振り回されないように注意しましょう。インターネットには、医学的見地に基づいた情報もありますが、まったく正しくない情報もあります。何かを検索すると、それに関連した情報が次々と流れてくることにも注意が必要ですね。子宮頸がん・子宮体がんの検査ひとつとっても、インターネット上ですごく痛い検査だとか書かれていることがありますが、当院ではできる限りそうならないように子宮の形態に配慮して、検査をスムーズに行うように心がけております。何事も、わからない場合は医師に相談していただければと思います。






