今上 修一 副院長の独自取材記事
イマウエ歯科クリニック
(小豆郡土庄町)
最終更新日:2025/07/22

「大切なのは、機能する口腔をつくることです」。朗らかにそう語るのは、約20年の時を過ごした富山大学附属病院を離れて、故郷の小豆島でリスタートを切った今上修一副院長だ。専門は、歯科口腔外科。口腔がんの切除や再建手術でも豊富な経験を持ち、現在は父親が院長を務める「イマウエ歯科クリニック」の副院長として、一般的な歯科疾患から口腔粘膜疾患まで幅広く治療を行っている。今後は「お口の中の困り事」を起点に、全身の健康状態まで見据えた医療を実現すべく、他科・多分野との連携体制を構想。100年の歴史を持つ歯科診療所を親子2代で守りながら、離島という環境下で提供される医療に変化を巻き起こそうとしている。すべては、小豆島で暮らす人々のため。今後の活躍と、地域医療への貢献が期待される今上副院長に話を聞いた。
(取材日2025年6月4日)
口腔環境の「困り事」を受け止めたい
歯科医師を志した経緯をお聞かせください。

父も母も歯科医師という家庭に育ちました。自宅の隣が診療所だったので、子どもの頃は気軽に診療所へ足を運んでいましたし、「将来の夢は?」という質問に対しても、決まって「歯医者さん」と答えていました。進学先は、北海道大学の歯学部です。雪国の大学を選んだ理由の一つは、スキー好きの父の影響ですね(笑)。卒業後は札幌医科大学附属病院の歯科口腔外科で1年半、研修を受けました。「口腔外科は最初に学ぶべき領域」という父からの助言もあり、口腔外科を選ぶことに迷いは生じませんでしたが、母校に設置されていたのは、あくまでも歯学部の中の口腔外科です。口腔外科だけではなく、一般歯科治療も学べるようにと、歯学部附属病院ではない単科の口腔外科への入局を考え、札幌医科大学医学部に属する歯科口腔外科を選びました。
お父さまと同じ、口腔外科を専門に選ばれたのですね。
小豆島の総合病院には、口腔外科が存在しません。この島の人々がお口の中のことで困らないようにするためには、口腔外科に行く必要があると考えていました。父も私と同じ思いで、口腔外科を専門に選んだと聞いています。札幌時代には口腔がんと口唇裂口蓋裂を専門とする恩師に出会い、その恩師に誘われて、2005年に富山医科薬科大学附属病院(現・富山大学附属病院)へ赴任。富山では口腔がんの治療を専門として、特に切除後の再建手術に力を入れていました。再建にあたって心がけていたのは、可能な限り口腔の機能を取り戻すということです。治療の過程で顎の骨が失われたとしても、義歯やインプラントを取り入れながら、食事や会話ができるようにと力を尽くしていました。19年半を過ごした富山での経験の数々は、今の私の大きな糧となっています。
大学病院では、他科との連携も不可欠だったとか。

口腔がんの治療は、手術だけで終わるものではありません。術前から始まる周術期管理、また薬剤を用いた化学療法も必要とします。当然、歯科の領域に収まらない問題が数多くありますから、内科や麻酔科、集中治療の先生と連携して治療にあたっていました。がん治療後の再建手術においても、整形外科の先生には本当にお世話になりました。私は現在でも、月に1週間ほどは富山大学附属病院に勤務しサポートを続けていますが、口腔外科を預かる後輩たちには、手術計画の立案だけでなく、関係各科やかかりつけ医と連携した、周術期や術後のフォローアップの指導も行っています。この連携体制をどう構築するかはとても重要な問題で、時には連携医を含めたウェブカンファレンスに参加することもあります。重篤な口腔疾患を抱えた患者さんたちに寄り添うためには、歯科医師も医師と同じように患者さんの全身状態と向き合い、術後の日常生活まで気を配ることが必要です。
近しい距離で、機能する口腔をつくる
小豆島に戻られた経緯は?

70歳になった父に病気が見つかり、一緒に手術の説明を聞きに行ったことがきっかけです。まだまだ父から学びたい分野がありましたので、2018年頃から1年半ほどの期間は、こちらへ戻って小児矯正や義歯作製などを学んでいました。そこから再び富山へ移り、お世話になった恩師の退官に立ち会いつつ、2025年3月に退職。同年4月から、この新築移転した場所で再スタートを切っています。新しい建物の中で私がこだわった場所は、個室の面談室です。歯科診療台ではなかなか患者さんとお話ができませんので、面談室でじっくりお話を聞きながら診察し、診断をつけていくという環境を整えました。
現在の診療体制について教えてください。
成人矯正は父の担当ですが、それ以外の一般歯科治療などについては、役割分担をしていません。外科処置は症例によりけりで、口腔粘膜疾患や、難治性の顎関節症などは私の対応が多いでしょうか。歯科医師以外の人員は、歯科衛生士が6人、受付が1人という構成です。スタッフはベテランばかりで、私以上にこの診療所をよく知っていますね。主訴のヒアリングはスタッフが中心で、症状の原因を検討する際にも、歯科医師とほぼ対等な立場で参加しています。このスタイルは、私が島へ戻る前から確立されていました。父の教育レベルの高さには驚くばかりですが、大学病院時代の患者さんとは距離の近い診療を続けてきたので、今は少し患者さんが遠く感じることもあります。もちろん、今の体制も素晴らしいところが多くありますので、それぞれの良いところを少しずつ融合していきたいと思っています。
先生の診療のモットーはございますか?

歯を守ることも大切ですが、それ以上に、「機能する口腔」をつくることが重要だと思います。状態の悪い歯を無理に残そうとすると、逆に噛みづらくなったり痛みが出たりと、患者さんが我慢を強いられる場面が出てくるでしょう。私は患者さんの全身状態を踏まえつつ、患者さんのライフスタイルや通院手段、ご家族のサポート体制なども考慮した上で、口腔機能を維持する治療方針を探っていきたいです。そして、最終的には誰もがお口の中のことで困らなくて済むようにしたい。それは決して簡単なことではありませんが、お口の困り事と悩み事すべてをしっかりと受け止めながら、ふるさとに暮らす人々の生活を守っていきたいです。
多職種連携が生きる地域医療をめざして
将来への展望をお聞かせください。

今後は大学病院で身につけた幅広い知識をこの島に還元するとともに、島の中で求められること、取り組むべき課題に焦点を絞っていきたいと思います。具体例を挙げるとすれば、まずは島の基幹病院と協力体制を築きたいです。口腔の疾患は幅広いですが、歯科医院でできる検査は限られています。血液検査やMRI、病理検査、細菌検査などを基幹病院に依頼することができれば、症状の原因を見極め、正確な診断につなげることができます。治療が難しい疾患については、島外の専門施設にお願いしなければならないケースもあると思います。その意味でも島内外でネットワークを広げ、医科と歯科とで並行して診療を継続する、包括的な地域医療を展開していくことが目標です。
「連携」は先生の大きなキーワードですね。
例えば小児矯正の分野に目を向けると、歯並びだけが問題と見せかけて、実は口腔機能の発達に問題を抱えているケースが存在します。今は歯科衛生士がトレーニングを工夫してくれていますが、歯科の視点だけでは、おそらく限界があるはずです。大学病院では、言語聴覚士(ST)とともに口腔がんや口蓋裂患者さんのリハビリテーションにも携わっていましたので、将来的には言語聴覚士とも連携して、個々の発達に即した口腔機能ハビリテーションを取り入れていきたいです。
読者へのメッセージをお願いします。
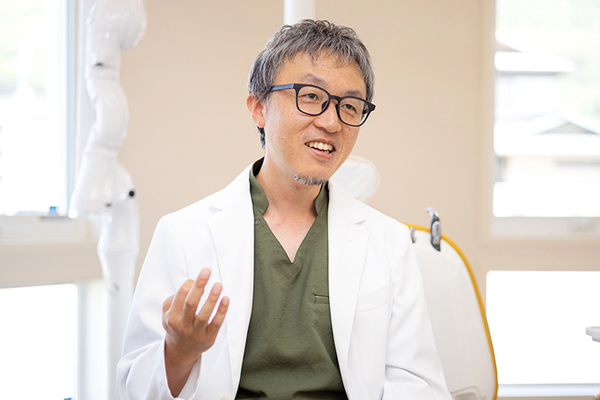
現状は昔から通ってくださっている方々のメンテナンスと、その中で発見された症状や疾患の治療が主な診療内容です。しかし口腔外科の専門性を生かすという意味では、もう少し新しい患者さんの診療枠を検討したいと思っています。診療フロアが動いている横の面談室で新規患者さんのご相談に乗り、主訴の解決をお手伝いできたら良いですね。今の私は、地域に根差した医療の姿を見つめ直している最中です。父やスタッフが整えた従来の診療スタイルを生かしつつ、周辺の医療機関との連携体制を構築して、さらにこの島の人々に寄り添った医療を実現したいと思います。小豆島の皆さんが、お口のトラブルで困り悩むことなく、安心して暮らせる環境づくりをめざして、一歩ずつ頑張っていくつもりです。
自由診療費用の目安
自由診療とは小児矯正(一次矯正、機能訓練など)/8万~25万円、成人ブラケット矯正(二次矯正)/60万円程度、インプラント治療/40万円程度






