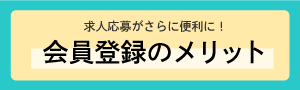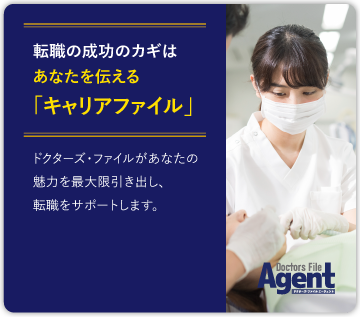山下歯科 (鹿児島市/高見橋駅)
山下 裕輔 院長の独自取材記事
虫歯や歯周病の治療であれば歯科医院に行く人でも、「飲み込み」の不具合は別の診療科を選ぶ人が多いだろう。しかし実際には、口の機能と喉の機能は密接な関係があるという。鹿児島市中央町の「山下歯科」は、虫歯や歯周病の治療はもちろん、咀嚼や嚥下機能の治療にまで対応する歯科医院だ。老年歯科領域を専門的に学んできた山下裕輔院長は、「患者が一生涯自分の口でおいしく食べること」を目標に、口腔機能低下症や摂食嚥下障害の診断や予防のための訓練に取り組んでいる。同時に、診療の半分を訪問歯科診療に充て、同院に通えない患者の口腔ケアにも力を注いでいる。そんな山下院長に、クリニックのめざす姿や診療への想いを聞いた。
患者が生涯自分の口で食べるための口腔健康管理を提案
現在はどのような患者さんが来院していますか?
患者さんのほとんどは、近隣のご高齢の方々です。一方、症状として多いのは歯周病の患者さんですね。というのも、当院は先代の院長である父が日本歯周病学会歯周病専門医として、歯周病治療に力を入れてきた背景があるのです。患者さんの中には、遠方から新幹線を利用してお越しになる方や、40年近く通ってくださる方もいらっしゃって本当にありがたい限りです。1975年の父が開業した当院を、2024年6月に私が継承して院長となりました。現在、常勤の歯科医師は私と父、非常勤歯科医師が1人、そのほかにスタッフが3人。一般歯科、予防歯科、訪問歯科に対応し、現在は外来診療と訪問歯科診療を半々くらいで対応させていただいています。
先生のこれまでのご経歴を伺います。
小さい頃から歯科医師である父の背中を見て育ってきました。診療中にここに遊びに来ることもあり、一人ひとりの患者さんに丁寧な対応をしている父の姿を見て、率直に「すごいな」と思っていました。ですので、歯科医師をめざしたのも自然な流れでしたね。大阪歯科大学を卒業後、鹿児島大学病院の義歯・インプラント科の研修医となり、そのまま医局に入りました。外来診療と並行して、大学院で老年歯科と摂食嚥下について専門的に学びました。簡単にいうと、高齢になると咀嚼や飲み込みなどの口腔機能が低下してくるので、それを早期に自覚して予防していく、というような領域です。
院長を継承された時に決意されたことはありますか?
目標としては、患者さんが一生涯自分の歯でおいしく食べることができるように、私たちができ得る「予防管理」を提案していきたいと考えています。そのため、父親が提供してきた歯周のメンテナンスは、引き続きしっかりと推進していく構えです。併せて私の専門性を生かし、ご高齢の方々の口腔機能の維持、口腔機能低下症の治療にも力を入れたい、と考えています。また、患者さんを長きにわたってサポートしていくためには、診療のかたちを変える必要性も出てくるかもしれません。かかりつけ歯科医院として患者さんのお口の状況をしっかり管理し、通うことができなくなった患者さんには、訪問歯科診療を通じて、できる限りお口のケアを継続させていただきたいと思っています。
口腔機能低下症や摂食嚥下障害の治療を推進
先生が注力している口腔機能低下症とはどのような症状ですか?
口腔機能低下症は2018年に保険が適用された新しい病名で、主に加齢により口腔内の咀嚼、嚥下、構音、唾液、感覚などの機能が低下していく症状です。以前と比べて「食べ物が噛みづらい」「食べ物が口に残ってしまう」「食事でむせやすくなった」「薬が飲みにくい」「口の中が乾く」「滑舌が悪くなってきた」といった症状が代表例です。お伝えしたように、私は大学院時代、これらの症状についても専門的に学んできました。口腔機能の維持は、生涯にわたり食事を楽しむことにつながり、全身の健康にとっても重要であるのに、外来診療で本格的に取り組んでいる歯科医院はまだ少ないのが現状です。超高齢社会の今、歯科において一層積極的に取り組むべきではないかと考え、継承前からその旨を父に伝え、準備をしてきたのです。
口腔機能低下症は、どのように検査や治療を行うのでしょう。
口腔機能低下症は、舌の汚れ、乾燥、噛む力、舌・唇の動き、舌の力、咀嚼力、飲み込む力という7つの項目をチェックして診断します。特に多いのは舌や唇の動きの低下で、新型コロナウイルス感染症の影響で人と会話する機会が著しく減ったのも大きな要因と考えられています。「パ・タ・カ」という言葉をそれぞれ5秒間に何回言えるかをカウントして検査し、低下が認められる場合は、人と会話する機会を増やしていただき、舌を上げる・伸ばすなどの運動を指導します。咬合力に関しては、残存歯数の確認や硬いものを噛んでもらうなどして検査し、必要に応じて入れ歯など義歯の調整を実施。乾燥が認められる場合は、唾液腺のマッサージなどを提案します。さらに、お口や舌の動きなどを定期的に動画に撮って一緒に確認もします。とはいえ、いきなり多くの訓練を取り入れることはせず、患者さん自身が毎日続けられることからご提案するよう努めています。
摂食嚥下障害について教えてください。
口腔機能低下症の進行によって発症する代表的なものが摂食嚥下障害です。その前兆は「食事をするとむせる、咳込む」「飲み込むのに時間がかかる」「口に食物が残っている」などさまざまです。高齢による筋力の衰えが原因となることが多いですが、生まれつきの病気や脳卒中などの脳血管疾患により起こる場合もあります。放置すると、誤嚥性肺炎や窒息、低栄養、脱水などを引き起こす可能性があります。診断では、まず日常生活に対する質問や水飲みテストなどを実施。機能が落ちているようでしたら、患者さんやご家族に嚥下に問題があることを共有します。歯の損失や義歯の不具合があれば、当然その治療も行います。それと併せて寝っ転がって頭を上げる「頭部挙上訓練」や、喉の筋肉を刺激する「おでこ押し体操」など、さまざまな飲み込みの機能訓練をご提案していきます。
症状や障害の有無を問わず地域の口腔ケアに取り組む
訪問歯科診療にはどのように取り組まれていますか?
近隣の高齢者や障害のある方、先天的な病気がある方、医療的ケア児のご自宅に伺い、診療をしています。高齢者は持病のある方がほとんどですので、ご家族に体調の変化などを伺うなど全身状態に配慮しながら治療を進めます。一方、歯科衛生士は担当のケアマネジャーや持病のかかりつけの医師と連絡を密に取り合っています。居宅でも、虫歯治療や歯石の除去、抜歯、入れ歯治療など、院内診療とほぼ同レベルの治療を行っています。患者さんがお口の中を見せる時に緊張がほぐれるよう世間話などもしますし、逆に治療に入れば患者さんの負担がないように迅速な処置に努めています。地域にはまだケアが行き届かない患者さんもいらっしゃるかと思いますが、こちらとしては、症状や障害の有無を問わず、できる限りの口腔のケアをして差し上げたいと願っています。
予防ケア、歯周メンテナンスについても教えてください。
まず患者さんに検査のご要望を確認した後に、歯肉の炎症、出血の有無、歯周ポケットの深さや歯の動揺度などの一通りのチェックを行います。お口の状況に合わせて歯のクリーニングや歯石除去、ブラッシング指導を行い、その後は1~3ヵ月ごとのメンテナンスに移行します。そもそも歯の疾患は、内科などの疾患と違って不可逆的、つまり元の状態に戻すことができません。悪くなってから治療を始めても、残念ながら削ることや埋めること、あるいは歯が抜け落ちたら義歯、というような選択をせざるを得ないのです。一方で、ご自身の歯磨きは重要ですが、完璧に磨くのは難しい上、歯石などは歯ブラシではもう取れません。ですので、普段から歯科医院でのメンテナンスも取り入れながら、しっかり予防に取り組んでいただければ、と考えています。
今後の目標や地域の人へのメッセージをお願いします。
お伝えしたいのは、お口の中と喉の奥はすべてつながっているということです。「飲み込み」の不具合は耳鼻咽喉科や内科と思われている方も多い中で、当院が、摂食嚥下障害をはじめとした口腔機能低下症に対して専門的な検査や治療を行っていることを、まず地域の方に知っていただけたらと思います。そして、いつまでもお口で食事ができる環境を整えるためにも、症状がある方はできるだけ早く対策をしていただきたいと切に願っています。歯のことはもちろん、お口の機能で気になることがあれば、ぜひご相談ください。