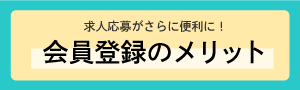医療法人社団 蒲生東診療所 (越谷市/蒲生駅)
井関 正和 院長の独自取材記事
東武伊勢崎線蒲生駅・新越谷駅、JR武蔵野線南越谷駅から徒歩約15分。高齢者からファミリー層まで、幅広い年代の人々が暮らす閑静な住宅街の中に「医療法人社団 蒲生東診療所」はある。優しい笑顔が印象的な井関正和先生は、2007年に先代の院長であった父から同院を継承した。長く地域住民の健康を支え続ける同院は、井関院長の専門である消化器内科に力を入れながら、周辺の医療機関との連携体制を生かした幅広い診療に対応。何でも相談できる、医療機関の最初の窓口としての役割を果たすことに努めている。丁寧に地域医療に対する思いを語る井関院長の姿からは、地域の人々への思いやりや地域医療に貢献したいという気持ちが伝わってきた。今回は、そんな井関院長に、地域に対する思いやクリニックの特徴について、詳しく話を聞いた。
地域のクリニックとして「最初の窓口」の役割を果たす
先生は、先代から2007年にこのクリニックを継承されたそうですね。
当院は約40年前に父が開業しました。当時、この辺りにはクリニックが少なく、交通の便も発達していなかったため、お年寄りや足の悪い方のためにも、近くにクリニックがあったほうがいいと、この地域を選んだと聞いています。私はここで、白衣姿の父を見ながら育ちました。大きな病院の勤務医や別の地域で開業するという道もありましたが、私を育ててくれた蒲生の地域の皆さんに恩返しがしたい、父が築いたクリニックを守っていきたいと思い、大学卒業後、三郷市のみさと健和病院での勤務医経験を経て、2代目として2007年からここで診察しています。私のことを子どもの頃から知っている患者さんや、親子2代、3代で通っていただいている患者さんもいらっしゃるなど、地域の方との付き合いは長いです。
こちらのクリニックは、地域でどのような役割を担っていますか。
地域のクリニックの役割は、医療機関の最初の窓口となることだと考えています。この地域も、お年寄りからお子さまやその親であるファミリー層も含めて、幅広い年代の方が住むようになっている印象です。その分、病気や困り事の内容も多岐にわたりますが、病院を何ヵ所も回らなくても済むよう、なるべく幅広い患者さんを受け入れることを大切にしています。当院は内科や小児科が中心ですが、専門の先生に診てもらったほうがいいと判断した際は、連携している専門の先生や大きな病院に紹介することも可能です。病気は早期発見が大切ですので、気軽にご相談に来ていただければと思います。
診療において、大切にされていることをお聞かせください。
診療で心がけているのは、患者さんの言葉をまず聞くことです。人によって痛みや症状の表現が違うこともあるので、つらいところや、気になっていることを最初に患者さんにお話ししていただきます。その上で、こちらからより詳しいお話を伺う。こちらから誘導するのではなく、まずは全部思いを吐き出してもらうことで「ちゃんと伝わっているのかな」という、患者さんの不安を取り除きたいと考えています。病院嫌いの方でも気軽に来ていただけるようなクリニックであるためには、患者さんと信頼関係を築くことが大切です。そのためにも、患者さんの話をよく聞くことと、心のこもった治療をモットーとしています。
負担の少ない検査、診療、服薬をめざした医療体制
先生のご専門についてお聞かせください。
私の専門は消化器内科ですので、内視鏡検査や胃腸の超音波検査には力を入れています。特にエックス線や胃カメラに関しては、がんをより見つかりやすくするために新鋭の設備を備え、週1回胃カメラを使った定期検診も行っています。内視鏡が怖いという患者さんもいらっしゃいますので、なるべく麻酔の段階から患者さんへこまめに声をかけたり、不安の強い方には眠っている間に検査を終えられるよう麻酔を使用したり、負担の少ない形をめざしています。
がんや病気においては、やはり定期的な検査が重要なのでしょうか。
がんをはじめとする病気は、症状が出る前に発見し、早期に治療ができれば、軽症の状態でとどめることがめざせます。病気を早期発見するためにも、症状が出てから検査をするのではなく、定期検診を受けることを皆さんにお勧めしています。内視鏡検査についても、一度やってみて「そんなに怖くなかった」と思っていただければ、その次の年の検査にもつながると思います。そのためにも、なるべく不安がないように検査を行うことが重要だと考えています。
東洋医学や漢方にも力を入れていると伺いました。
はい。例えば、ご高齢の患者さんに対して、漢方薬を処方したり、薬を減らしたりするための相談に乗ることも可能です。患者さんの中には、多量の薬を服用することが負担になっている方も多いと思います。必要な薬は飲まないといけませんが、なるべく減らす方向で相談に乗ることも意識しています。また、中には長く漢方薬を服用することに抵抗がある方もいらっしゃるので、どんな考え方の患者さんも安心してお薬と付き合っていけるよう、じっくりと相談していきます。
外部の栄養士や医師との連携についても詳しくお聞かせください。
近隣にある同級生の耳鼻咽喉科や、大学病院、市立病院などとの横のつながりを重視し、お手紙だけではなく、電話などを使って素早く連絡し合える連携体制を整えています。大きな病院で働く医師と地域のクリニックで働く医師が情報交換できることは、お互いに良い刺激になっていると思いますね。また、例えば患者さんに日々の食事内容について書いてきてもらったものを、知り合いの栄養士にチェックしてもらい、その結果を患者さんにアドバイスすることも可能です。密に連携できる体制を幅広く確保しておくことは、患者さんの安心にもつながると考えています。
受診への抵抗を減らし、気軽に相談できるクリニックへ
スタッフとのチームワークで気をつけていることはありますか。
アットホームなクリニックですので、仕事の分担をするというよりは、一体感を持って仕事をすることを重視しています。例えば、看護師だけでなく、事務員も泣いているお子さんに話しかけたり、お年寄りの方が来たら誘導したりと、役職や役割に関わらず、みんなが一人ひとりに寄り添う。スタッフのこうした姿勢によって、当院のチームワークは成り立っていると思います。定期的にミーティングをしたり、スローガンを共有したりすることもありますが、みんながこのチームワークを共通意識として認識できていると感じますね。
先生ご自身は、健康維持のために意識されていることはありますか。
昔から自分の健康維持のために、フットサルとサッカーで体を動かすことを続けています。フットサルは週1回、サッカーは月1回定期的にやっていますね。患者さんのためには自分自身も健康でいなければならないので、意識的に体を動かすようにしています。食事についても、患者さんに指示をすることがありますが、自分もその大変さを実感しないとつらさがわかりません。そのため、規則正しい食生活を意識したり、夜中に食べないようにしたりと、なるべく自分も患者さんに指示できるような規則正しい生活習慣を保ちたいと思っています。
今後の展望についてお聞かせください。
今は患者さん一人ひとりになるべく時間を取るようにしていますが、そうすると待ち時間も長くなってしまいます。混む時間、混まない時間をこちらから患者さんに周知していくなど、もう少し工夫していきたいですね。また、待ち時間をできる限り少なくすることはもちろんですが、お待ちいただいている時間も苦痛にならないように、アットホームな雰囲気は維持していきたいです。これからも一人でも多くの地域の方々に信頼していただけるよう、努めてまいります。
最後に読者へメッセージをお願いいたします。
早めにご来院いただければ、それが早期発見につながるかもしれません。とはいえ、クリニックにかかることに対し、抵抗がある方もいるでしょう。当院は、なるべくそうした不安を取り除けるようなクリニックをめざしています。内科、小児科の診療のほか、漢方治療や更年期障害でお悩みの方へのプラセンタ療法など、幅広い健康相談も受けつけています。丁寧に問診をして、幅広い選択肢の中から患者さん一人ひとりに合う治療法をご提案しますので、心配事や「変だな」と思うことがあれば、お気軽にご相談ください。