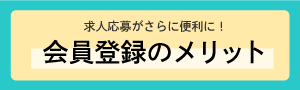しばファミリークリニック (宇都宮市/東武宇都宮駅)
柴野 智毅 院長の独自取材記事
宇都宮駅から車で約12分、栃木県立美術館のほど近くに「しばファミリークリニック」は位置する。長年地域で親しまれてきた内科クリニックを継承する形で開業した柴野智毅院長は「困ったときはここへ来れば大丈夫」と信頼されるような「昔ながらの町医者」をめざして、外来診療と訪問診療の両方を実施。大学病院での経験から「診療分野の隙間で取りこぼされてしまう人が出ないよう、どんな症状でもまずは診て、どうすれば良いのか示すことを大切にしています」という柴野院長に、外来診療と訪問診療でそれぞれ大事にしていることや、今後力を入れていきたいことなどについて語ってもらった。
困った時に気軽に頼れる「町医者」をめざして
以前は自治医科大学に勤務されていたと伺いました。
はい、そうです。下野市にある自治医科大学の本院で、肺がんをはじめとする呼吸器疾患の治療・研究・教育を行っていました。医局を辞めて、前院長先生からこちらを引き継いだのが、2022年1月になります。クリニックを開くと決めたきっかけはいくつかあるのですが、その一つが、医局で感じていたモヤモヤです。私の専門は呼吸器外科ですが、経験を積むにしたがい、後輩の手術指導や研究が仕事の中心になってきました。その患者さんが起きている時に会うこともないし、患者さんと接する時間はどんどん少なくなり、そんな日々は自分のやりたいこととは少し違う、という漠然とした不満がありました。その点、クリニックは直に患者さんに接する場であることが、開業を決める理由の一つになりました。
開業以来、クリニックとして大切にしていることがあるそうですね。
大学病院にいた時から感じていたのは、今は医療が専門別に細分化されて「うちの科の担当ではない」と断るケースが多いことです。その結果「じゃあ、私はどうしたら良いの?」と困っている方、どこに行ったら良いのかわからない方が増えているように思いました。そんな状況を嫌だなと思っていたので、うちはそれこそ20年、30年前の「町医者」のように、どんな症状でもまずは診るし、何か困ったら気軽に相談に来られるクリニックにしたいと、開業当初から考えていました。それは今も変わりません。僕の専門は呼吸器なので、初診時は咳などで来られる方が多いように思いますが、生活習慣病から精神的な不調など、本当にいろいろな症状の方がいらっしゃいます。患者さんの年代もさまざまで、新生児から訪問診療希望の高齢者まで幅広くいらっしゃっています。
外来診療と訪問診療の両方を行っているのですね。
ええ。訪問診療は、開業当初の医師一人体制だった時から少しずつ始めました。常勤の医師や看護師などの仲間を増やしながら、多くの患者さんに対応できるよう徐々に体制を整えていきました。僕はもともと肺がんの治療が専門だったので、大学病院では、手術の後なかなか家に帰れなくて、そのまま病院で亡くなる方を多く見てきました。帰れない理由はさまざまですが、例えば胸に管が入っていて管理が必要だけれど、管が入っていたら往診の医師も対応できないから、といったものです。この状況を何とかしたいとずっと思ってきたので、開業当初から訪問診療も行い、基本的に難しいケースでも断らないようにしています。もちろん手術後の帰宅だけでなく、通院が難しくなったことで外来診療から訪問診療に移行するということもできます。そうしてスムーズに切り替えができるのは、外来と訪問診療どちらも行っている当院ならではのメリットかなと思います。
誰も取り残すことのないように
訪問診療ならではの難しさはありますか?
検査機器など使える設備が限られることと、患者さんの生活そのものに関わることでしょうか。訪問診療は患者さんの生活の一部ですから、患者さん自身やご家族はどうしたいのかが一番重要になってきます。その分、普通の医療より患者さんに寄りそうことが大事ですし、医療的に見ると正しい選択ではなくても、患者さんやご家族にとって正しいものなら良いのかなと思っています。患者さん本人とご家族の間に摩擦がある場合は、間に立ってうまくまとめ、皆が納得するゴールを設定するのも僕らの仕事ですね。訪問診療ではケアマネジャーさんに介護士さん、看護師さん、それに僕ら医師が総動員でどうやって患者さんを支えてくのが良いのか考えていきます。大変ですが、皆でああだこうだ話し合いながらやっていくのは楽しいですね。
外来診療で大事にしていることや心がけていることを教えてください。
やはり話を聞くことですね。時間がかかることも多いですが、やっぱりそれが一番大事かなと思います。患者さんの訴えを聞いて整理して、医学的な見通しを立てて対処を考えていく。やっていることは本当に昔の町医者と同じですね。「専門分野しか診ません」では取り残されてしまう人が出てくるので、まずは訴えをしっかり聞きます。もちろん僕では診られないものもありますが、その場合は「ここに行ったほうが良いよ」など、次にどうすれば良いのかを伝えるようにしています。もし僕が逆の立場でせっかく時間をつくってクリニックに行ったのに「ここでは診られません」で終わったら「え、じゃあ僕はどうすれば良いんですか?」と困っちゃいますからね。それは違うと思うんです。
お子さんを診ることも多いと聞きました。
小児科を掲げているわけではないのですが、お子さんも結構来ます。風邪や喘息で来る子が多いですが、ワクチン接種や乳児健診もやっているので、そちらも多いですね。子どもはやはり怖がってしまいがちなので、ワクチン接種なんかは「ママの顔見てて良いよ」と言うなど、一瞬意識を逸らした隙にパッと終わらせるようにしています。開業してから身につけた技術ですね(笑)。あと、お子さんは症状や状態をうまく伝えられず、また親御さんは心配のあまり冷静に状態を伝えられないことも多いので、聞き方を工夫したり、親御さんの病歴など周りの状況から判断したりもします。また、採血やエックス線検査は必要最低限にしています。お子さんが泣き叫ぶのを見るのは気持ちの良いものではないですし、エックス線検査はやはり発がんリスクもありますからね。検査を希望される親御さんは多いですが、本当に必要な検査なのかを話し合いながら実施するようにしています。
訪問診療を通じて、患者と家族の生活を支える
先生が医師になろうと思ったきっかけも教えてください。
医師になろうと決めたのは高校受験の時ですかね。ちょうどその頃放送されていた医療系のドラマを見て、面白そうだなと思ったことなどがきっかけです(笑)。
今まで多くの患者さんを診てきたと思いますが、イレギュラーの対応などはどのようにされていますか。
件数としては多くないですが、病院から「今日すぐに訪問診療を受けてくれないか」という依頼があった場合、最期に本人が絶対に家に帰りたいという意思があれば、引き受けることもあります。家で一晩ご家族と最後の時間を過ごせたことで、奇跡的に一時的に意識も戻ることもあります。帰宅を許可してくれる病院、即受け入れ体制を整えてくれるケアマネジャーさんや看護師さんがいることで、患者さんやご家族にとって貴重な1日を提供することができるかもしれません。私としてもできるだけ帰る手助けができるように、医師としてできることを尽くしていきたいと思います。
最後に、今後の展望をお聞かせください。
訪問診療には、より力を入れていきたいと思っています。今は困っている高齢者や医療ケアが必要な方がすごく多いので、そこをどうにかしなくてはいけないとの思いは強いです。ただ、患者さんやスタッフが増えると医療の質の担保が難しくなるので、バランスを見ながら、一歩一歩進めているところです。訪問診療は、医師としてのテクニックも大切ですが、患者さんやご家族とのコミュニケーション能力がとても大切です。信頼できる仲間を集めて多くの患者さんに温かい医療を提供できる体制を作ることが今の私の目標です。