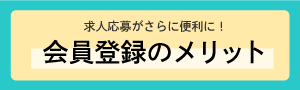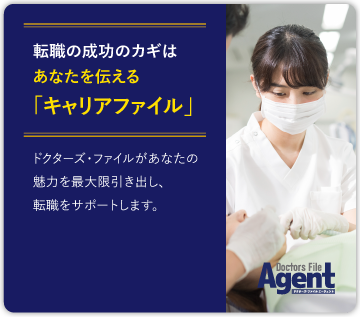おおがい内科医院 (横浜市旭区/鶴ヶ峰駅)
大貝 明日香 院長の独自取材記事
相鉄線の鶴ヶ峰駅から徒歩1分。院長の大貝明日香先生が2025年に開業した「おおがい内科医院」は、一般内科、スポーツに取り組む人を対象にしたメディカルチェックなどの医療的なサポート、人生の最終段階を見据えたACP(アドバンス・ケア・プランニング)の相談の3つを軸にする。大貝院長は「医療を通して、自分らしく生きることを支えたい」と語り、患者一人ひとりと丁寧に向き合う。患者に寄り添うことを忘れず、小さな不安にもしっかり耳を傾ける大貝院長の笑みは穏やかで、丁寧に選ばれた言葉で語りかける話しぶりは優しい。気づけば心を開いていることに気づかされる、そんな雰囲気をまとった大貝院長に、開業に至るまでの歩みやACPへの思い、日々の診療で大切にしていることについて話を聞いた。
医療と患者をつなぐ架け橋になりたいという思いで開業
鶴ヶ峰は先生の地元だそうですね。どんなクリニックをめざして開業されたのでしょうか?
私は15歳の時に父を病気で亡くしていて、地元の皆さんに支えていただきながら育ちました。いつか恩返しがしたいという思いがずっとあり、ゆくゆくは鶴ヶ峰で開業したいと思っていたんです。いずれはと思いながら地元で市民講座を毎月開いているうちに、地域の皆さんから「早く開業してほしい」という声をたくさんいただいたことで背中を押してもらい、2025年に開業しました。当院がめざしているのは、ちょっとした不安も気軽に相談できて、患者さんの生き方を一緒に考えられるようなクリニックです。医療について専門的に学んできた知識があるからこそ、患者さんに医療の選択肢をわかりやすく伝え、納得した上で治療を選べるサポートができると考えています。医療と患者さんをつなぐ架け橋のような存在でありたいと思っています。
先生が医師を志したきっかけも、お父さまの病気にあるそうですね。
当時高校1年生だったのですが、父の病気や治療について説明を受けても全然意味がわからなかったんです。病院の方々は良くしてくださっているとわかるのに、父の命に関わる選択の意味や重さが自分の中にきちんと落ちてこなかった。そのくらい医療用語は難しく、患者が理解するまでが本当に遠いという実感を持っているんです。だからこそ、「医療のリテラシーを橋渡しできる存在」になりたいと思うようになりました。それまでは伝える仕事に興味があって、ライターや記者にも憧れていました。言葉で伝えることの難しさと面白さの両方を知っているからこそ、医師としてできる関わり方がある……。医師を志した時に抱いた思いは今も変わらず、医師としての軸になっています。
先生がこれまでどんな研鑽を積まれてきたのかを教えていただけますか?
大学では、医学を誰かにわかりやすく伝えるためには人体や病気のルーツから学びたいと思い、ゲノムの研究に取り組みました。最初は内科を志望していたのですが、ある先生に「あなたの患者への接し方や病気への向き合い方は緊急の現場でこそ生きる」と勧められたことで、ゲノム研究とも関連の深い血液内科に進んだんです。血液内科では、白血病や悪性リンパ腫の患者さんを診ます。白血病の患者さんに今すぐ抗がん剤が必要という状況になった時は緊急性が求められますが、だからといって命に関わる選択をよくわからないままにするのは違うと思い、事前に準備していた図や言葉で説明して、患者さんご自身に納得して治療へ臨んでもらえるよう力を尽くしました。血液内科で経験を積むうちに、とある患者さんの言葉から「病気が治った後まで患者さんを支えるには、見た目や生活の質まで考える必要がある」と気づかされたことで、皮膚科で働いていた時期もあります。
最期を決めることは、生き方の指針を決めること
先生が大切にしている診療方針について教えてください。
当院の理念は「共感」「笑顔」「勤勉」の3点ですが、診療で大切にしているのは「共感」です。といっても、どんな人も完全に誰かの立場になりきるのは本当の意味では不可能だと思っています。だからこそ、目の前の患者さんが今どんな気持ちでここに来ているのかを丁寧にくみ取ること、そこに最大限のエネルギーを注ぎたいと考えているんです。例えば風邪だったとしても、その症状が本人にとってどれほど不安かは人それぞれ異なります。私は、今この瞬間に患者さんが感じているつらさにどう向き合うのか、その先にどんな可能性があるのかを、図やたとえ話を使ってなるべくわかりやすく伝えるようにしています。患者さんと一緒に考えて、一緒に医療の選択をしていくために、医師としての説明を「その患者さんに向けた言葉」に落とし込む。そんな診療をしたいと思っています。
ACPにも力を入れていらっしゃるのですね。
ACPとは、将来の医療やケアについてご本人や近しい人、医療やケアチームがくり返し話し合い、医療に関わる意思決定を支援する取り組みです。私自身、「本人にとって一番良い選択は何だったのか」と考えさせられる経験が何度かありました。医師になる前のことですが、闘病中の父のために主治医の勧めを受け入れ緩和的手術を決断しました。しかし、がんの進行により完遂できず、「手術が本当に父の生き方にふさわしい選択だったのか」と今でも心に引っかかる思いがあります。私が考える医師とは、ただ説明するだけでなく、患者さんが納得し同意できる環境を整える存在。だからこそ、開業にあたりACPの外来を設けました。ACPは“死に方”を選ぶものではなく、“どう生きたいか”を見つめ直すための時間。自分の選択がわかれば、日々どんなふうな生き方をしたいのかがわかってくる。そんなポジティブなアクションだと捉えていただけるとうれしいです。
お話を伺っていると、「患者さんに寄り添う」という言葉には収まりきらない先生の思いを感じます。
ありがとうございます。私が思う寄り添い方とは、そばにいる、親身になるというだけではなく、「同じ方向を向く」という意味合いが強いのかもしれません。私は、一人ひとりの患者さんの歩幅に合わせて、一緒に考えながら進んでいける存在でいたいと思っています。一方的に「これが正解です」と提示するのではなく、生活や価値観の背景を踏まえて複数の選択肢を出し、患者さん自身が選べるようにする。それが、私なりの寄り添い方です。ACPも同じで、誰かの人生の一部を一緒に考えることには責任もありますが、深いやりがいがあります。医師として、人として、その信頼に誠実でありたいと思いながら向き合えるよう心がけています。
小さな不安から気軽に聞ける、家族のようなクリニック
診療をとても大切にされているのですね。
私は、患者さんと話すことにしっかり時間をかけたいと思っています。例えば初診では、症状の話だけでなく、住んでいる家が木造か鉄筋かといった生活の背景までお聞きすることもあります。一見関係なさそうに思えることも、病気の経過や体調に影響することがあるんです。カルテに記録する際は、患者さん自身の言葉で話された情報をしっかり残すようにしています。私は、医療者として患者さんに向き合うというよりも、医療に少し詳しい家族として隣にいるような診療をしたい。その人の人生の一部に関わらせていただく時間だからこそ、急がず、真っすぐに話を聞くことを大切にしています。
先ほどお話に挙がった市民講座ですが、定期的に開催されているそうですね。
現在も、月1回のペースで市民講座を開いています。講座では毎回テーマを決めて、できるだけかみ砕いた言葉でお話ししています。外来よりも少し自由に、質問しやすい雰囲気を大切にしています。私自身にとっても患者さんにどう話せば伝わるのか練習できる機会になっていて、自分の言葉を見直すきっかけにもなっているんです。最近は、企業や学校からお声がけいただくことも増えてきました。地域の方の「わからない」を少しでも減らすために、これからも続けていきたいです。
最後に、読者へのメッセージをお願いします。
小さな不調を感じたときに「こんなことで病院に行ってもいいのかな」と迷うことって、きっと誰でもあると思うんです。でも、そう思ったときにこそ私に話してもらえたらと思っています。「こんなこと」の中に何か大きな病気の入り口が隠れているかもしれないし、何もなければ「何もなかった」と安心して帰ってもらえるだけで構いません。医療は自分らしく生きるためにあるものだと思っていますので、どうぞ気負わずに、身近な人に話すような感覚で来てもらえたらと思います。