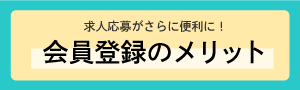みちくさ眼科中村橋 (練馬区/中村橋駅)
岩佐 真弓 院長の独自取材記事
中村橋駅より徒歩約1分のメディカルモールの2階に2024年5月に開院したのが、「みちくさ眼科中村橋」だ。木目を生かした居心地の良さを感じさせる待合室が印象的な同院。岩佐真弓院長は、眼科の医師の中でもそう多くない神経眼科が専門。白内障や緑内障、結膜炎、視力の問題など眼科一般を幅広く診療する中で、眼瞼けいれんや複視、斜視、甲状腺眼症など神経が関係する目の病気に対し、専門性の高い診療を提供している。「患者さんに笑顔で帰ってもらうことを大切にしています」とすてきな笑顔で話す岩佐院長に、同院のことや診療の取り組み方などについて、詳しく話を聞いた。
神経眼科を専門に目の病気や症状を幅広く診療
なぜ開業するにあたってこの場所を選んだのですか?
私は神経眼科が専門ですので、MRIがすぐに撮れたほうが助かるんです。そこで、隣の富士見台駅との間に画像診断のクリニックがあり、依頼をしたらすぐに検査をしてくれて、患者さんが戻って来られるここを開業の場所に選びました。院内は、医療機関ではないような雰囲気を心がけています。例えば、診察室にはレーザー治療器がありますが、患者さんは見慣れてなくて圧迫感があるかもしれませんので、その上のほうに目が行くように絵を飾っています。また、待合室に季節の飾り物を置いて、患者さんが安心できる空間を心がけております。クリニック名の「みちくさ」には、道草をするように、気軽に受診してほしいという思いが込められていますが、実は、もう一つ意味があるんです。当院の待合室に説明したシートが置いてありますので、来院した際に読んでいただけたらうれしいです。
神経眼科について、詳しく教えてもらえますか?
「神経眼科って何?」という人もおそらく多いと思います。ざっくりいうと眼球だけではなく、その周りの組織や脳とのつながりなども診ていく分野です。多い病気としては、眼瞼けいれんや物が二重に見えてしまう複視、斜視。バセドウ病の方に多い甲状腺眼症も目に特徴的な症状が現れますが、そういったものを専門にしています。ただ、神経眼科の診療しかしていないのかというと、そんなことはまったくありません。白内障や緑内障、結膜炎、視力の問題、糖尿病網膜症、黄斑変性、眼鏡やコンタクトレンズの処方などまで、一般的な眼科で取り扱う病気や症状を幅広く診療しています。
どのようなときに、神経眼科の専門的な診療を受けたほうが良いのでしょうか?
例えば、眼瞼けいれんは瞬きがコントロールできなくなってしまう病気で、目が開けられなくなっていれば一目瞭然ですが、軽症例は見分けづらく、ドライアイの治療だけされている場合も少なくないんです。よくある症状としては、室内でも光がまぶしい、目が乾く、目を開けているのがつらい、開けるのがつらいから気づくと閉じているといったものが挙げられます。私は、その診断や治療の第一選択であるボツリヌス毒素製剤の注射も多く経験してきましたので、より適切に治療できるよう努めています。また、バセドウ病で目の調子が悪いときに、甲状腺の影響を受けているかどうかの判断も可能です。他に、斜視や複視なども、例えばプリズム眼鏡を使うのか、それとも手術をしたほうが良いのかなどのご相談にも乗っています。斜視へのボツリヌス毒素製剤の注射も、当院で対応可能です。これらの病気でお悩みの方にも、ぜひ受診してほしいですね。
ドライアイや小児の近視進行抑制治療にも対応する
開業から1年たち、最近多いご相談はありますか?
時期的なものもあると思いますが、学校健診で指摘されたお子さんの視力についてご相談にいらっしゃる方が多いです。他には、春頃はやはりアレルギー症状に悩まれている方がいらっしゃいますし、時期にかかわらずドライアイのご相談も開業当初から多いですね。また、小児の近視の進行を点眼薬で抑制する治療の問い合わせも増えています。近視進行抑制の低濃度アトロピン点眼薬はもともとあったものなのですが、2025年4月に承認が下りたこともあって問い合わせが増えました。近視は眼軸といって眼球の奥行きが長くなることで進み、体が成長する時期に眼軸も伸びるといわれ、この時期でないと近視進行抑制治療は効果が望めないといわれています。そのため、近視の進行を抑える治療は10代後半まで可能といわれているので、中学生以上でも相談にのっています。こちらは自費の診療となり、検査なども含めて保険診療外となります。
ドライアイの治療では涙点プラグ治療も行っているそうですね。
開業前に勤務していた病院でも対応することが多かった治療で、当院でもご相談が増えています。涙の流出口にプラグという栓を差し込むことで、お風呂に栓をするのと同じように涙がたまり、ドライアイの改善が見込めます。プラグには2種類あり、一つはシリコンで栓をするもの。こちらは1回入れると年単位で使える方もいますが、まれにすぐに外れてしまったり、擦れて痛みがあり外さなくてはならなかったりする方がいます。もう一つはコラーゲンで栓をするものです。こちらは痛みや異物感が少なく、物を入れるのが怖いという方にもお勧めです。ただ、2ヵ月ほどで流れてしまうので、継続する場合は定期的にコラーゲンの充填が必要です。どちらもメリットデメリットがありますので、説明をして選んでいただいています。
検査機器もいろいろ置かれていますが、眼科の検査にはどのようなものがありますか?
一般的な検査として視力検査と眼圧検査、緑内障や糖尿病網膜症、加齢黄斑変性などの診断に有用な眼底検査、眼球を動かさずに周囲の見える範囲を測る視野検査などがあります。中でも、皆さんよく知っている視力検査は、眼科に従事する者とそうでない方では一番認識に差がある検査かもしれません。患者さんからすると数値がわかるだけの体力測定に近いイメージのようですが、私たちからすると数値以外にたくさんのことが知れる情報量の多い検査なのです。その情報から今後起こり得る病気のリスクがわかることもあります。無駄な検査だと思わずに、受けていただけるとうれしいです。また、当院には20分ほどで結果が出るアレルギー検査機器もあります。自分が何のアレルギーなのか知りたいという患者さんの声が多かったため、導入しました。指先からの採血なので、お子さんでも受けていただきやすい検査です。
子どもから大人まで笑顔で帰ってもらえるクリニックに
診療の際に心がけていることを教えてください。
まず、一人ひとりの患者さんに笑顔で帰ってほしいというのがあります。ですから、目の前にいる患者さんが、安心しているのか不安を感じているのかなど、良い空気も悪い空気も積極的に受け取るように心がけています。また、幅広い年齢の患者さんがいらっしゃるので、それぞれに合わせた対応をしようと思っています。例えば、お子さんの患者さんの場合は、診察室に入ると怖くて泣いてしまう子もいます。ただ、眼科は泣いてしまうと診察が難しいので、なるべくお子さんがニコニコしているうちに診察を行うようにします。
お忙しい日々とは思いますが、先生はどのようにリフレッシュをしていますか?
犬を飼っているので、一緒に散歩するのが趣味なのですが、そのつながりでできた友人の店が近くにあるんです。そこでみんなとのんびりしゃべったり、お茶をしたりするのがリフレッシュになっています。最近では、15年ぶりにバイオリンを再開しました。自分の音と向き合っている時間は他のことが考えられないので気分転換にとても良いのと、全身を使うので運動したような気持ちよさがあります。一生の趣味があるのは幸せなことですね。
最後に今後の展望と読者へのメッセージをお願いします。
目に関わる病気は進行すると治療が難しい病気が多く、視力が落ち始めるとどうにもならない場合がほとんどです。特に緑内障や糖尿病網膜症などは、症状がないうちに早期発見することが大事になってきます。コンタクトを作りに来た方やものもらいなどの治療に来た方など、別の主訴でいらした方たちの中からでも、そういった病気を見逃さずに早期治療につなげていくことは、地域のクリニックとしての使命だと考えています。また、身近で神経眼科の診察が受けられるところは少ないと思いますので、バセドウ病や視神経の病気をしたことがある人、視神経に影響のある薬を飲んでいる人の検診などの細かいニーズにも応えたいと思っています。よくある目の病気や悩みも、本当にスーパーの袋を持ったままでも気軽に受診してください。