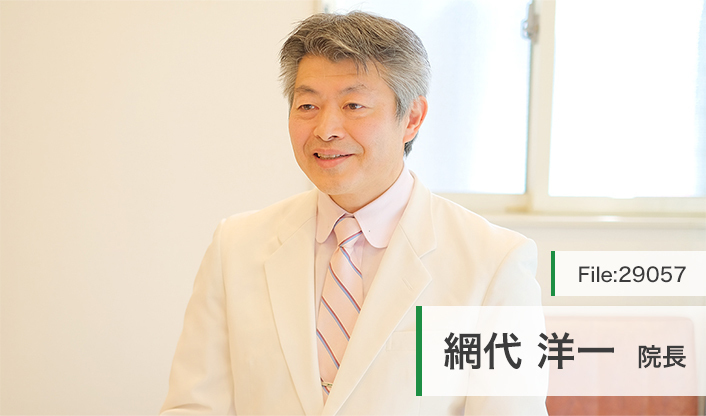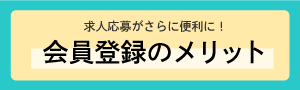にいじゅく組合診療所 (葛飾区/亀有駅)
網代 洋一 院長の独自取材記事
東京・葛飾にある「にいじゅく組合診療所」は、戦後の混乱期に互助目的で創設された生活協同組合が前身だ。ダークグレーの外観は住宅や学校が建ち並ぶエリアに溶け込み、今も建物の外壁に残る「新宿組合診療所」の銀文字が、昭和から平成、そして令和と、地域とともに歩んできた歴史を感じさせる。内科全般およびプライマリケアを担う一方、網代洋一院長が長年研鑽を積んできた循環器内科領域や睡眠時無呼吸症候群(SAS)においては、特に専門的な治療に対応することが可能だ。より充実した地域医療の実現に向け、予防医療と早期発見に力を入れることはもちろんオンライン診療も取り入れ、通いやすい体制づくりを実施。そんな網代院長に、診療所の特徴や今後の目標について語ってもらった。
地域住民の健康を支えつつ、専門的な医療も提供
「にいじゅく組合診療所」は、開設から80年近い歴史があるそうですね。
当診療所は終戦後間もない頃に私の祖母が創設した「新宿消費生活協同組合」が前身です。1947年に利根川流域を襲ったカスリーン台風でここら一帯が水浸しになり、医療機関もほとんどつぶれてしまって住民の生活が危機にさらされたため、その翌年に新宿生協の医療部門として診療を始めたそうです。やがて生協本体の活動は縮小し、現在は当診療所のみが存続しています。父が支えてきた地域のプライマリケアを担う診療所として、向かいにある母が院長を務める「あじろ小児科」とも協力しながら、すべての年齢の患者さんに対し、総合的な医療サービスの提供をめざしています。また、数年前には施設全体をリニューアルしました。ご高齢の患者さんが多いことから、もとは2階にあったレントゲン室を1階に移して利用しやすくしたほか、訪れた患者さんの気分が少しでも和らぐように、より明るく温かみの内装に一新しました。
こちらの診療所でどのような医療の実現をめざしていますか。
一番大事にしているのは、地域医療の一端を担い、皆さんの健康を支えることですね。体と心の健康が、社会的にも良い状態であるウェルビーイングの実現に向けて貢献していきたいと考えています。私は長く循環器を専門として、不整脈や心不全、睡眠時無呼吸症候群(SAS)などの治療に携わってきました。専門的な経験を、地域の皆さんをはじめ、当診療所のことを頼って来てくれるすべての人たちに提供したいです。また、予防接種をはじめとする予防医療や生活習慣の改善、心臓病やがんの早期発見に向けた検査の実施などにも力を入れていきたいと思います。
地域医療に尽力されているんですね。
地域医療における当診療所の役割は、プライマリケアの一言に集約できます。かかりつけ医、ホームドクターが担う医療というとイメージしやすいでしょうか。私としてはどんな患者さんも診るという心構えでいます。どんなことでも気軽に相談できる医療の入り口となり、専門病院・大規模病院との隙間を埋める医療がプライマリケアだと捉えています。患者さんには、どの診療科を受診したらいいのかわからない場合も含め、まずは医療の入り口として安心して活用していただきたいと思います。
循環器疾患や睡眠時無呼吸症候群の治療に力を入れる
睡眠時無呼吸症候群の注意点について教えてください。
睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中に呼吸がたびたび止まる病気です。注意点は、とにかく気づきづらいこと。「居眠りしてたるんでる!」と怒られてたけど、実は睡眠時無呼吸症候群であったことも。「居眠り運転」も要注意。家族からの指摘で初めて来院される方がとても多いですね。睡眠時無呼吸症候群は、小柄な日本人は痩せてても発症しやすく、肥満や加齢による喉を支える筋肉の衰えがあるとさらに悪化します。治療としては、機械で鼻から気道へ圧をかけるCPAP治療(持続気道陽圧療法)で治療していく方法と、連携する歯科医院で作製したマウスピースを作製して睡眠中の上顎と下顎の位置を調整する方法が2本柱です。重症の睡眠時無呼吸症候群は、気づかれないまま動脈硬化を進行させるので、放置せずにきちんと治療することは将来の脳梗塞や心筋梗塞などの動脈硬化性疾患を予防する上でも極めて重要です。
この医院で睡眠時無呼吸症候群の治療を受けるメリットを教えてください。
睡眠時無呼吸症候群のCPAP治療は、導入期は月に1回、安定期は2ヵ月に1回の診療としています。当院はオンライン診療でのCPAP管理も対応しますので、特にCPAP治療のみでお薬処方のない方は通院の負担を軽くできます。生活習慣病の治療や当院管理栄養士による栄養指導など、睡眠時無呼吸症候群と合わせた幅広い健康相談・健康管理にも対応できます。
病気の早期発見にも注力されているのですね。
当院では、心臓病やがんの早期発見に力を入れております。ちょっとした症状や検査の異常も見逃さないように日々取り組んでおります。大学病院などでも使用されている高性能の超音波検査機器を導入しており、心臓病やがんを含む病気の発見につながっています。最近では、ストレインという心臓の動きをより詳細に解析することで、注目されている心アミロイドーシスの早期発見に注力しています。
不整脈の発見についても教えてください。
不整脈は不整脈が起きていない時には診断がつきません。検査では不整脈が起きている時に心電図への記録が大切なため、心電図を連続記録できるホルター心電図検査を行います。標準的には24時間のホルター心電図検査が多いですが、当院では最長2週間の長時間ホルター心電図検査や、症状が起きた時に記録できるイベント心電計を実施できる環境を整え、不整脈発見に努めています。特に意識している不整脈に脳梗塞の原因となる心房細動があります。心房細動は症状がないことも多く、脳梗塞発症まで気づかれないことも多い、怖い不整脈です。それだけに「脳梗塞になる前になんとか発見したい」という思いから疑わしい方には積極的に長時間ホルター心電図検査を勧めています。また心房細動をカテーテルアブレーションで治療しても、睡眠時無呼吸症候群を合併しているとせっかく治療した心房細動が再発してきてしまうことも多いので、早期発見にも心をくだいてます。
診療所というチームで患者の健康をサポート
大学病院や総合病院で経験を積まれた先生が、診療所に移ってこられた経緯をお聞かせください。
実は、父や母から、この診療所を継いでほしいとは言われたことはなかったんです。私はもともと研究と地域医療というまったく方向の異なる道に興味がありました。勤務医時代、病気に苦しむ患者さんと接する中で、もし病気になる前に医療介入できていたら、この患者さんは元気な人生を送っていたのだろうと、悔しく思うことがしばしばありました。その思いが積もっていき、だんだんと、予防医療や病気の早期発見を地域医療で実現していきたいという気持ちが強くなっていきました。それが理由の一つです。
治療を進める際に気をつけていることはありますか?
医学的に最良と思われる治療も、患者さん本人の考えや経済状況、ご家族の意向などにより希望されないこともあります。なので、個々の治療方針を決定する際は、それらの事情を伺い配慮するよう心がけています。いわゆるシェアードディシジョンメイキング(共同意思決定)ですね。医療を押しつけるのではなく、患者さんがご自身の病気やそれによる今後の可能性を適切に理解できるよう、医療の専門家として説明やアドバイスし、意思決定のお手伝いをするつもりで接しています。
読者へのメッセージをお願いします。
患者さんと接する時に肝に銘じているのは、初めの主訴がすべてではないということです。看護師やスタッフに打ち明けている情報がもとになり、意外な病気が見つかることも数多くあります。その経験がわれわれの血となり肉となります。まさに「患者さまからの学び」を日々実感しています。だからこそ、今後も当診療所はスタッフとの連携を大切にし、チームで皆さまの健康をサポートし、寄り添っていきたいと考えております。何か健康に不安を感じた時、健康に関して相談したい時は、どうぞ気軽にご相談ください。スタッフ一同お待ちしています。