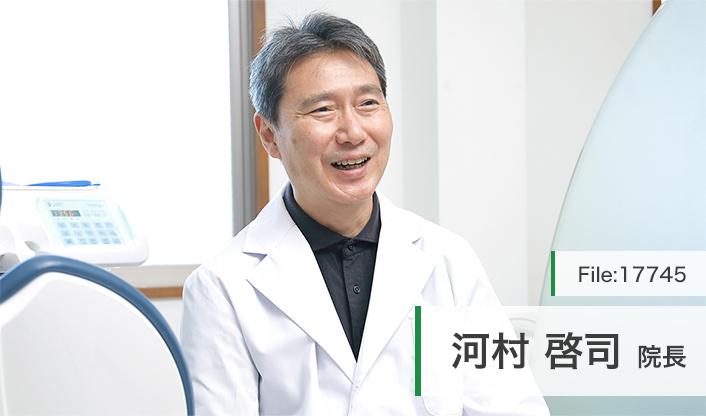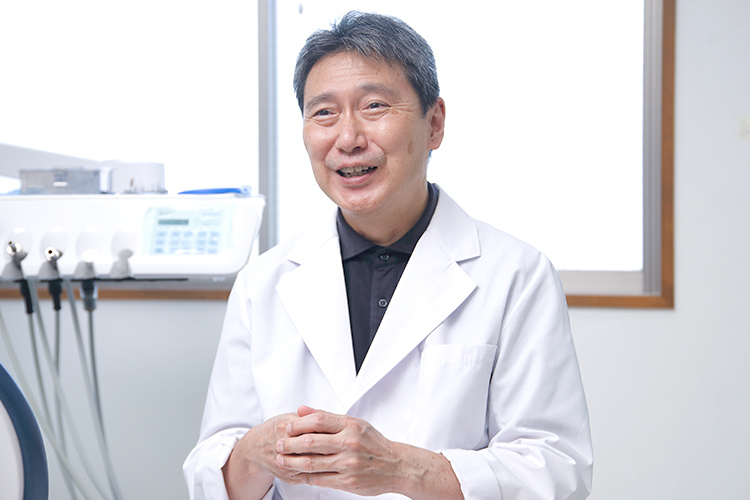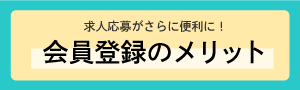河村歯科医院 (八尾市/八尾駅)
河村 啓司 院長の独自取材記事
八尾駅から徒歩7分、近鉄八尾駅から徒歩15分に位置する「河村歯科医院」。一般歯科をはじめ、歯科口腔外科や小児歯科、審美歯科など幅広く対応する一方、特に予防歯科に力を入れている。「歯の痛みや不調を放置すると、食事から十分な栄養が取れず、仕事や学業、スポーツのパフォーマンスにも影響します」と河村啓司院長は話す。予防の習慣が広がれば、誰もが本来の力を発揮でき、社会全体の活力向上にもつながるという。今回は、河村院長に予防歯科へのこだわりや患者への思い、歯科衛生士への期待、今後の展望などについて詳しく聞いた。
歯の治療で日々の活動パフォーマンスを守る
地域の顔としてすっかり信頼される存在ですね。
おかげさまで、八尾で開業して早いもので19年になります。患者さんもフレンドリーで温かい方ばかり。この地で開業できたことを心から幸せに思っています。当院では、一般歯科をはじめ歯科口腔外科や小児歯科、審美歯科など幅広く対応しています。また、口臭ケアの提供や、スポーツに励む子どもたちのためにマウスガードを製作するなど、スポーツ歯科にも取り組んでいます。中でも私が最も大切にしているのは予防歯科です。虫歯を治療しても、失った部分が人工物に置き換わるだけで、本来の歯の量は減ってしまいます。皮膚の傷と違って歯は一度失うと二度と元に戻らず、治療を重ねるほど自分の歯は少なくなっていきます。だからこそ、健康な歯を守ることが何より重要なのです。
やはり、予防が大切なんですね。
口腔ケアは生活や仕事、スポーツなどのパフォーマンスを維持する上で欠かせません。歯が痛むと食事が不自由になり、栄養が十分に取れず、気分が落ち込んだり不眠になったりすることもあります。実際に、重要なプレゼンの直前に歯の痛みで力を発揮できなかった会社員や、口腔内の不調で本来のプレーができなかったアスリートも診てきました。私は縁の下の力持ちとして、患者さんが健康な歯や口腔内を維持できるようサポートし、社会や家庭に良い循環を生み出したいと考えています。なかなか歯科医院に行けず、歯の痛みや不調を抱えている人は少なくありません。そうした問題を早期に解決できれば、子どもから社会人、高齢者まで多くの人が本来の力を発揮できるようになります。結果として、日本社会全体の活力向上にもつながると考えています。
予防歯科にはスタッフの協力も欠かせないのでは?
歯科衛生士は単なるアシスタントではなく、口腔ケアのプロフェッショナルです。歯の汚れを落とすだけでなく、日々のブラッシングを正しく行えるよう指導し、患者さんが自宅でもケアを継続できるよう導いてくれます。歯科医院での3ヵ月に1回、年に4回のメンテナンスよりも、残りの361日のセルフケアのほうが大切だからです。私は、歯科医院は歯科医師と歯科衛生士が役割を分担して支える「チーム」であると考えています。歯科医師が壊れた歯を治すなら、歯科衛生士は健康な歯を維持する役割を担う。患者さんの多くは「歯科医師に診てもらわなければ」と考えがちですが、実際には予防やメンテナンスのプロである歯科衛生士こそが、日常的なケアを支える存在です。餅は餅屋、という言葉のとおりです。実際、当院の歯科衛生士たちは自ら考えて動き、患者さん一人ひとりに合わせたケアを実践してくれています。
乳幼児期からの離乳食相談や口腔機能育成も
頼もしい歯科衛生士さんたちですね。
現状では歯科衛生士が独立して診療所を持つことはできませんが、将来的には歯科衛生士が個人で診療所を構え、地域の人々が気軽に通えるような仕組みがあってもいいのではないかと思います。それほど歯科衛生士の役割は重要です。私は歯科衛生士たちが最大限の力を発揮できるよう、環境や器具を整えていますし、学びたいという気持ちを育てサポートしていこうと思っています。当院では、歯科衛生士が中心となって、乳幼児期からの離乳食相談や口腔機能育成にも取り組んでいます。国全体としても、歯科衛生士をもっと育成し、その立場を高める必要があります。歯科衛生士が活躍の場を広げれば、予防の文化が根づき、医療費の削減にもつながるはずです。
離乳食相談や口腔機能育成とはどのような内容でしょうか?
これは、歯が生える前から赤ちゃんの口周りの筋肉を育て、適切な離乳食の進め方や姿勢、スプーンの使い方、歯磨き習慣など、生涯の口腔機能に関わる生活習慣を身につけさせるための取り組みです。歯並びや矯正の有無を直接変えるものではありませんが、噛み方や飲み込み方、食べ方の基礎をつくり、「生涯にわたり自分の口から食べる力」を守る大切な一歩となります。子どもは、勉強が得意でもスポーツに才能があっても、歯や口の機能が弱く十分に栄養を取れなければ力を出しきれません。逆に、しっかり食べられる子どもは体が元気に育ち、挑戦へのエネルギーを得られるのではないでしょうか。
粘膜疾患も得意分野の一つと伺いました。
粘膜疾患は、舌や歯肉、頬、口蓋などの粘膜に生じるさまざまな病気の総称です。赤く変色したり白い斑点など、症状は多岐にわたります。大学病院では口腔がんを扱う歯科医師は多くいますが、地域の歯科医院でその手前の段階から専門的に診る歯科医師は少ないのが現状です。当院ではこの領域を丁寧に診療し、必要に応じて専門医療機関と連携し、病理検査まで行える体制を整えています。患者さんが最も不安に感じるのは「口腔がんではないか」という点です。例えば、口内炎は初期から痛みがありますが、初期の口腔がんは自覚症状がないまま進むことも少なくありません。そのため私は最悪の可能性も想定し慎重に診断しています。多くの場合は「取り越し苦労で済んで良かった」となりますが、すべての可能性を確認した上で得られる安心感こそ、患者さんにとっても、歯科医師の私にとっても何より大切だと考えています。
患者一人ひとりを理解することから診療が始まる
診療において心がけていることはありますか?
患者さん一人ひとりをできる限り理解することを大切にしています。なぜなら、医療機関に足を運ぶ時点で、医療従事者は少なからずその方の人生に関わることになるからです。患者さん自身のことを知り、同じスタンスで自分も年を重ねていきたいと考えています。その思いが根底にあり、時にはメンタル面で応援するなど、診療中のコミュニケーションにも工夫しています。また、「最低限を維持すること」も大切にしています。虫歯を放置していたり歯周病があったりしても、何も食べられないわけではありません。現時点で食べられているのであればその3年後、5年後も食べられるように、というのが「最低限」という意味です。もちろん、苦痛を取り除き、より快適に食事を楽しめる治療も必要ですが、まずは現在の歯の状態を守ることを重視し、長期的に口腔の健康を支えていきたいです。
どのような歯科医院でありたいですか?
患者さんが近況報告やおしゃべりを楽しみながら、気軽に立ち寄れる歯科医院をめざしています。歯が痛くなってから駆け込むのではなく、未病の段階から日常の一部として来院してもらえると、自然に予防につながると考えています。もちろん、虫歯や歯周病などの状態を迅速に診断し、的確に処置する技術も磨きたいです。しかしそれ以上に、患者さん一人ひとりに何が必要かを考え、寄り添った治療を提供することが大切です。例えばインプラントをご希望の方には、本当に必要かどうかを一緒に考え、不要であれば行わない選択肢も提案しています。今はオーダーメイド治療やAIの導入など診療も多様化しています。同院では短時間で歯周病菌の検査ができる装置も導入しており、少しでも患者さんのためになれたら、と思っています。培った自分の技術や経験は大切にしつつ、新しい方法も柔軟に取り入れ、患者さんに安心を届けられる歯科医院でありたいと考えています。
読者へのメッセージをお願いします。
超高齢社会が進む中で、元気なお年寄りが増え、家族や友人と一緒に楽しく好きな物をおいしく食べられる未来を描きたいと考えています。そのために歯科医師として何ができるかを常に考えています。当院もやっと地域に根づいてきた実感があります。啓発活動や歯科衛生士の取り組みにより新しい世代の患者さんも増えてきました。これからも患者さんやスタッフ一人ひとりと向き合い、満足度の高い治療を提供しつつ、笑顔が笑顔を呼ぶ、そんな町づくりに貢献していきたいと思っています。