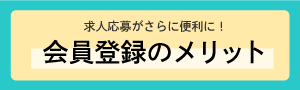土井ファミリー歯科医院 (広島市安佐南区/上安駅)
土井 伸浩 院長の独自取材記事
アストラムライン上安駅から徒歩で約3分の距離にある「土井ファミリー歯科医院」。2001年の開業から現在まで、小さな子どもから高齢者に至る幅広い年齢層の患者が通う歯科医院だ。2019年からは通院が難しい患者への訪問歯科診療も行っている。土井伸浩院長は昭和大学歯学部を卒業後、広島大学歯学部に入局。岡山県岡山市内の歯科医院勤務を経て開業した。日本歯周病学会歯周病専門医の資格を持ち「予防に勝る治療はない」という診療方針を掲げ、予防歯科を主軸にしながら、虫歯・歯周病の治療はもちろん、入れ歯治療、インプラント治療、歯列矯正、審美歯科など多様なニーズに応じた診療を展開している。笑顔を絶やさず何でも気さくに話してくれる土井院長に、歯科医師をめざした経緯から診療の内容、今後の展望など、いろいろと話を聞いた。
小児から高齢者まで幅広い悩みをカバー
まず、歯科医師をめざした経緯を教えてください。
明確な理由は特にないんです。性格的にオフィスワークは無理だろうと思い、高校を卒業したら手に職をつけたいと思っていました。それでまず造園業に興味を持ち、実際に少し仕事をしたこともありましたが、やっぱり大学に行こうと考えたとき、たまたま縁のあった人から「手に職をつけるなら歯医者も面白いよ」と勧められたのが、この道に進んだきっかけです。でもいざこの世界に入ってみたら、思ったよりも自分に向いているように感じました。それ以前から自分が共感していた「自利と利他の心」という、人の役に立つために努力することは自分の喜びにもなるという考え方にも通じるものがあり、それは現在も当院の理念の一つに掲げています。
現在の診療体制を教えてください。
常勤の歯科医師、非常勤の歯科医師、そして歯科衛生士と多くのスタッフが勤務しています。診療台は8台あり、診察は一部を除いて担当制にはしていません。というのも診療のレベルを平均化し、クリニック全体として底上げをしたいと思っているからです。ただし特定の症例について研究したいというような理由がある場合は、同じ先生が1人の患者さんを診るケースもあります。そうすることで引き継ぎの手間などもなく、スタッフとしても仕事がしやすいようです。また全体的なスキルアップのために講師を招いて、主に技術的な面での講習会をしています。そのときは僕自身が実験台になってPMTCなどをしてもらい、スタッフそれぞれの技術的な特徴などを把握した上で、どんな患者さんは誰に頼んだら良いかという参考にしています。
どのような患者さんが多いですか?
多いのは40代から50代くらいの方ですね。そのうちの半数以上は女性の患者さんの印象です。次に多いのが、60代以上のご夫婦など高齢の方、その次が10代以下のお子さんでしょうか。そういった年代の方々を全部合わせると「ファミリー歯科」になるわけです(笑)。いわゆるデンタルIQも高い方が多く、虫歯などの治療よりメンテナンスの患者さんのほうが多いですね。定期検診に来られる方のほぼ皆さんが3ヵ月とか半年先の予約を取って帰られるので、土曜日などは5ヵ月くらい先まで埋まってしまっています。近所の方も多いですが、県外から来られる方も少なくありません。
予防歯科を幹として矯正や訪問歯科診療にも力を入れる
予防歯科に力を入れているとお聞きしました。
僕自身が若い頃あまり口腔ケアをしていなくて、歯が抜けたままのところもあるような状態でした。さすがに歯学部に進んでからはケアをするようになりました。あるとき、授業でインプラントを入れられることになりました。まだインプラントが先端的な技術だった頃で、どんなケアをすれば良いのか不安になって自分で調べたところ、歯周病は良くないということがわかりました。「これは自分が歯周病の専門家になって口の中を守らなければ」と思って勉強し、日本歯周病学会歯周病専門医の資格も取得しました。そういった経緯から、歯周病、予防歯科、インプラントを得意分野としています。と言ってもそれだけでなく、すべての分野をしっかりと診たいという思いがあり、それ以外の診療についてもしっかり学んできています。歯周病とその予防を太い幹として、他の分野を枝葉のように伸ばしていくというのが、理想とする診療スタイルのイメージです。
マウスピース型装置を用いた矯正にも力を入れているそうですね。
ええ。現在のようにマウスピース型装置を用いた矯正が広く普及する前から導入しています。きっかけは、特に10~20代の思春期の患者さんは、目立ちやすいワイヤー矯正がコンプレックスになってしまう場合もあるのではないかと考えたことです。私は歯科に関するあらゆる情報にアンテナを張っているのですが、海外で当時先進の方法としてマウスピース型装置を用いた矯正が広まっていることを知りました。透明の目立ちにくい装置で、エビデンスに基づいて行われる方式でしたので、当院でも取り入れたいと考えたのです。装置の見た目が気になりにくいのはもちろん、ワイヤー矯正に比べると痛みが少ないため、患者さんに喜んでいただけているのではないでしょうか。興味のある方は気軽にお声がけください。
訪問歯科診療もされていますね。
20代の頃から寝たきりの高齢者の口腔ケアにも興味を持っていました。いつかはそういった方を対象とする診療もしたいと考え、介護についても勉強しました。開業した頃に50〜60代だった患者さんの中には、現在当院の階段を上り下りできなくなっている方も少なくありません。エレベーターをつけるのは無理だとわかり、移転するにも近所に空いている場所はなく、どうしようかと思っていましたが、この近くで訪問歯科診療を行っていた先生が辞めるということで私が引き継ぎ、訪問歯科診療を始めることにしました。新型コロナウイルス感染症の流行で一時訪問を中断する施設などもありましたが、口腔ケアと免疫の関係性のデータを取って説明したところ、診療を再開してくれるようになりました。
新たな分野にも積極的に取り組む
歯周病について、皆さんにお伝えしたいことはありますか。
歯周病の専門家としては、歯周病を悪化させないことの重要性について皆さんに知っていただきたいですね。歯周病が悪化する要因は複数考えられるのですが、中でも大きく関連するとされているのが歯ぎしりと食いしばりです。皆さんご存じのように、就寝中や物事に集中している時などに無意識のうちに歯を擦り合わせる癖が歯ぎしりで、歯を強く噛みしめてしまうのが食いしばりです。歯ぎしりや食いしばりにより歯に過度な力がかかることで、細菌が歯周ポケットに入り込みやすくなり、繁殖することで歯周病の進行につながるとされています。
歯ぎしりや食いしばりに悩む方々にはどのように対応されているのでしょうか。
歯ぎしりや食いしばりの大きな要因の一つはストレスであるといわれていますので、心の持ちよう次第で、ストレスをため込まないようにするのが大切だとアドバイス差し上げています。そうはいっても実際問題難しいでしょうから、それ以外の歯科医師としてできる部分でサポートさせていただいています。具体的には、歯ぎしりや食いしばりの原因が歯並びであることも少なくないため、必要に応じて矯正のご提案をさせていただくことも。しかし時間的または費用的な問題から取り組むことが難しい人もいらっしゃいます。そういった場合は、歯ぎしり用のマウスピースや、噛み合わせの高さや位置を調整する咬合調整をご提案することもありますね。
今後の展望を聞かせてください。
高齢の患者さんから、階段の上り下りがつらいという声をいただくことも増えていますので、近くに移転できるところがないか、今後も探していこうと思っています。診療内容としては、これまでどおり予防歯科をメインに据えながら、患者さんのさまざまな口腔内のお悩みに対応できるような包括的な診療の実践をめざしています。私は歯周病とインプラント治療を専門にしていますが、矯正や小児歯科を専門にする先生方もいらっしゃいますのでしっかり連携していきたいですね。自分だけでできることには限りがありますが、副院長をはじめとする先生方の助けを借りながら、どんな症例に対してもレベルの高い診療を提供していけるようにしていきたいと思います。そのための勉強会も主催していて、すでに50回以上開催しています。そういった努力を続けながら、生まれ育った地元に歯科医療で貢献をしていきたいですね。