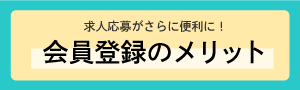はんだクリニック (茨木市/南茨木駅)
半田 忠利 院長の独自取材記事
南茨木駅から徒歩8分。静かな住宅地にある「はんだクリニック」は約25年前に開院したクリニック。医師になった当初から、「なるべく多くの患者さんに貢献したい」と考え、「総合診療を行う医師」をめざした院長の半田忠利院長は、「なるべく多くの疾患に正しく対応できるようにするためには、外科、内科どちらかだけではなく、外科、内科、両方の知識と経験を積むことが必要だと感じました」と語る。現在は、その経験と知識を生かし、地域のかかりつけ医として、一般内科を全般的に幅広く診療を行う。「患者さんが適切な医療を受けられるようにしたい」と話す半田院長に、診療内容や大切にしていることについて話を聞いた。
外科、内科で研鑽を重ね、総合診療を行う医師をめざす
先生が医師をめざしたきっかけは何ですか?
父が医師で開業医をしていたからです。小さい頃から働く父の姿を見て、患者さんを治療し、喜んでいただけるところに魅力を感じました。ある時、町を父と歩いていると患者さんから声をかけられ、「先生のおかげで……」と感謝されたことがありました。そんな様子を見て、父を尊敬しましたし、患者さんの助けになることのできる素晴らしい職業だなと。また自分自身も病気というものに対して興味もあったものですから、自分も医師になって患者さんを救えたら、と考えるようになりました。
ご開業までの経緯を教えてください。
最終的に開業医になりたいと思っており、「なんでも診られるかかりつけ医」をめざして経験を積んできました。外科の視点、経験があることにより、患者さんの異変や、緊急時に最適な判断がつくと考え、まずは外科的な知識と技術を習得することに決めました。京都大学医学部第2外科に入局後、京都大学医学部附属病院、長浜赤十字病院、松江赤十字病院、武田病院の外科に勤務し、非常に多くの手術を担当しました。松江赤十字病院では、麻酔科や救急救命センターでも経験を重ねましたね。その後、内科系の修練のため、京都桂病院総合内科にて糖尿病・内分泌疾患、腎臓疾患、消化器疾患、循環器疾患など、多くの種類の内科の病気の診療を経験し、治療にあたり、エコーや内視鏡についても研鑽を積みました。最終的に京都武田病院では外科医と内科医として勤務し開業。幅広く診られる医師になるため、経験と知識の向上に励んできました。
現在も勉強を続けているそうですね。
開業した25年間、週末はほぼ札幌から福岡まで全国各地の医学セミナーに参加しています。常に新しい技術や薬についての情報が得られますし、何よりこれが一番患者さんのためになると考えています。一般内科系疾患や消化器疾患、循環器疾患、糖尿病、アレルギー疾患、呼吸器疾患、それぞれの領域の勉強会に参加すると、さまざまな分野の先生方と自然と顔見知りになるわけで、すると病診連携、診診連携が取りやすくなります。当院では近くの大学病院や国立循環器病研究センター、その他総合病院とも連携していますが、患者さんの精密検査や手術が必要になった場合にはどの病院のどの先生にと適切に判断し、紹介させていただいています。また逆に病院の先生から患者さんを紹介していただく場合もあります。とにかく患者さんにとって便利なクリニック「あそこに行ったら、ちゃんと紹介してくれる」という点も、患者さんの安心感につながるのではないかと考えます。
治療の目的や内容、薬の作用・副作用を丁寧に説明
患者さんの主訴で多いのは何ですか?
内科と胃腸内科を掲げていますが、実際にはいろんな患者さんを診ていますね。小学生からの診察も可能です。糖尿病、高脂血症、高血圧症といった生活習慣病の方も多いですが、それ以外にも、さまざまな疾患に対応しております。診療では、まず問診を十分に行いながら、視診・触診をしてその後、必要な検査へと移ります。各種エコー検査、レントゲン検査、内視鏡検査、白血球、赤血球、CRPが数分で出る血球計算装置、肺の働きや呼吸の病気がないかを調べるスパイロメトリーも備えています。診断結果から必要と判断した場合は、病院や専門のクリニックを紹介しますが、その際も「こういう理由があるので、すぐに受診してください」とか、「急がなくてもいいから来週中には行ってください」というように、患者さんが納得して適切な医療を受けられるようわかりやすく説明しています。
診療の際に大切にしていることは?
繰り返しになりますが、患者さんにとにかく丁寧に説明することですね。今の病気について、なぜ治療をしないといけないかということをまずご理解いただいた上で、薬については、薬を飲む目的、服用の方法やタイミング、考えられる副作用についても、「もしこんな症状が出たらご相談ください」と具体的にお話しします。治療期間の目安やどこが治療のゴールなのかということまで、とにかく丁寧に細かく説明します。もし初診の患者さんが相談に来られたとき、それが明らかに専門外の症状だと判断をしたら、「〇〇クリニックに行かれたほうがいいですよ」と理由も併せてお伝えし、必要であれば地図もお渡ししていますね。当院で診療する場合も、他院に紹介する場合でも、皆さんに満足いただけるような診療をめざしています。
なぜ丁寧な説明にこだわるのでしょう。
例えば、なぜ血圧、高脂血症の薬を飲まなきゃいけないのかというと、こうした生活習慣病というのは、5年後、10年後に脳卒中や心臓病、慢性腎臓病、認知症などを発症するリスクが高くなる病気だからです。今、薬を飲んで生活習慣病を治療することは、将来起こるかもしれない重篤な疾患の予防につながるのです。ただ、薬には必ずベネフィットとリスクがありますから、僕自身はあまりたくさん多くの薬を出すことには基本的に反対なんです。「ポリファーマシー」といって多くの薬を飲むことで、体に悪影響が出る場合もあります。そこは患者さんによく説明しながら、その薬を飲むことによって、患者さんのメリットが多い場合には服薬をお勧めします。また、初めて来られた患者さんには、すぐ薬を処方するのではなく、日常生活の見直しを提案することもあります。
患者のために「I do my best」を継続
テーラーメイドの治療にもこだわっていらっしゃいますね。
一人ひとりの生活背景も考慮するのは大事なことです。患者さんの中には一人暮らしの方もいらっしゃれば、仕事で昼夜逆転した生活を送っている方もいます。だからこそ、その方に合わせたテーラーメイドの医療が重要です。例えば、糖尿病でも、太った方と痩せた方では全然タイプが異なり、太った方は食事に気をつけていただいたり、痩せた方についてはしっかりと筋力アップを勧めております。また食事の仕方も大切です。このように人によって指導内容がまったく違います。また高血圧症の方の診療を行う際も、さまざまなタイプがあり、目標の数値も患者さんによって違ってきます。
食事や運動についても指導されているのですか?
寒い時、暑い時に外で歩かなくても食後に座らず皿洗いをしたり、立ってテレビを見たりという方法もあり、必ずウォーキングが必要というわけではありません。とにかくその人に合った長続きできる生活習慣でないと継続できません。生活習慣の見直しによって、減薬が期待できるケースもありますし、そうすると医療費の負担を軽減できることも。そして、患者さんのモチベーションが上がることもあります。あとは、タバコやアルコールの弊害もご説明しながら、食品にしても、私が知っている知識を提供したいと思っています。
趣味や熱中していることはありますか?
ほぼ毎日、オンラインで英会話を楽しんでいます。そして毎日英語で日記も書いています。これからインバウンドの患者さんも増えてくると思うので、英語で対応できるようにしていきたいですね。
今後の展望をお願いします。
引き続き、患者さんに丁寧に説明して、予防できるものを予防する、治療できるものは治療する、私ができないものは、専門の先生にご紹介し、患者さんの健康が長く維持できるようにかかりつけとしての役割を全うしたいと思います。自分の努力を通じて、とにかくなるべく多くの患者さんのお役に立ちたいと考えております。まずはどんな小さなお悩みでも来ていただいて、ご説明し、患者さんに適した治療を提供させていただきます。開業して25年たちますが、患者さんがご自身の人生を「エンジョイ」できるよう、引き続き医師としてお手伝いをしていきたいと思います。