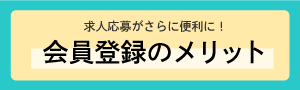中井歯科医院 (加古川市/加古川駅)
中井 聡 院長の独自取材記事
東加古川駅から南西方向2.6km、住宅街の一角にたたずむ「中井歯科医院」は、れんが造りの入り口が目印のクリニック。1986年の開院以来、地域歯科医療の一翼を担ってきた。乳幼児健診に長年携わってきたほか、幼稚園の園医としての経験も持つ中井聡院長は、近年増加している子どもの口腔機能発達の課題に着目し、従来の歯科診療に加え、歯科衛生士との連携を重視したメンテナンスプログラムを展開している。幼少期からの成長発達を見守り、将来的な歯並びの乱れの予防まで視野に入れたアプローチを図るなど、患者それぞれのライフステージに寄り添った診療を実践する中井院長に、診療への想いとスタッフが働きやすい環境づくりについて話を聞いた。
地域に根差し30年以上。長期的視点から見た予防を
まずは先生のご経歴など開業までの経緯をお聞かせください。
私の父は刑務所の看守、母は学校教師をしていました。医療とは異なる分野で働く両親のもとで育ち、周りに歯科医師がいない環境でした。ただ、人と関わる仕事という点では、両親から多くを学んだように思います。大阪歯科大学を卒業後、3年間勤務医として経験を積み、1986年に独立開業しました。開業時から大切にしてきたのは「患者さん中心の医療」というモットーです。歯科医院に自分から行きたいと思う方は少ないでしょう。だからこそ、患者さん一人ひとりの気持ちに寄り添い、求められる医療をきちんと提供できる歯科医院であり続けたいと考えてきました。
開業当初から現在まで、歯科診療に対する考え方に変化はありましたか?
患者さんの中には、開業当時から通ってくださっている方も多く、その方々のお子さんやお孫さんまで家族ぐるみで来ていただいています。こうした長いお付き合いの中で、予防の重要性をより一層実感しています。歯科衛生士による定期的なメンテナンスを通じて、できるだけ長く自分の歯で過ごしていただきたいと考えています。
地域の歯科医院として特に大切にしていることを教えてください。
赤ちゃんからご高齢の方まで、どの世代の方にも安心して通っていただける場所であることです。診療では、歯をできるだけ温存する方針を心がけています。特に「できる限り歯を削らない」という考えのもと、治療計画を立てています。歯を削ることは、つまり健康な歯の一部を失うことに他ならないからです。その点で、予防における歯科衛生士の役割は非常に重要です。定期的なメンテナンスを通じて、患者さんの歯を長く守っていく。そのためには、知識と技術を持った歯科衛生士の存在が欠かせません。当院では、歯科医師と歯科衛生士が、それぞれの専門性を生かしながら患者さんの歯の健康を支えています。
口腔機能の発達支援で、子どもの健やかな成長を見守る
いつ頃から予防へ診療方針を転換されたのでしょうか。
2020年頃から予防を重視した診療への転換を始めました。きっかけとなったのは、歯科医師として働く次男からの一言でした。「これからの時代は予防が大切になる。そのためには歯科衛生士の存在が重要」という助言です。それまでは虫歯や歯周病の治療など、一般的な歯科診療が中心でした。ただ、1歳半健診や3歳児健診の実施に加え、幼稚園の園医としても子どもに長年関わってきた経験があり、幼い頃からの口腔環境づくりの重要性はそれ以前より強く感じていました。最近では虫歯の子どもは減ってきていますが、その一方で口腔機能の発達に課題を抱える子どもたちが増えています。この変化に気づいてからは、信頼できる歯科衛生士との出会いにも恵まれ、チームとして一丸となって予防を重視した診療に取り組んでいます。
幼い頃からの予防を大切にしているとのことですが、具体的に教えてもらえますか?
最近の子どもたちの傾向として、発音がはっきりしない、飲み込みづらそう、姿勢が気になるといった症状を抱えているケースが増えている印象があります。このような問題は、将来的な歯並びにも大きく影響します。そこで当院では、口腔機能の発達と維持に関する専門的な知識を持つ歯科衛生士と協力し、独自の予防プログラムを展開しています。例えば、メンテナンスの中にトレーニングを取り入れ、お子さんの成長に合わせた指導を実施しています。口呼吸や前かがみの姿勢、指しゃぶりなどの習慣は、放っておくと歯並びの乱れにつながる可能性があります。そのため、普段の習慣をしっかりヒアリングしています。スタッフは定期的に外部の講習やセミナーにも参加し、先進の知識や技術の習得に努めています。子どもたち一人ひとりの成長に寄り添いながら、将来を見据えた予防的なケアを心がけています。
予防プログラムを開始されてみて、いかがですか?
予防プログラムを始めてから、特に印象的な変化があります。以前は虫歯の治療のために来院されるケースが中心でしたが、最近では「将来の歯並びが心配」「癖を直したい」といった予防的な相談が増えてきたことを実感します。歯科衛生士も勉強会で得た知識を積極的に取り入れ、お子さんの成長に合わせたアドバイスができるようになりました。こうした一つ一つの変化は、私たちにとって大きな励みになりますね。
スタッフの笑顔が患者を支える
診療時間の見直しを行われたそうですね。
2024年10月から診療時間を見直し、休憩時間を短縮する代わりに、診療終了時間を1時間早めることにしました。きっかけは、子育て中のスタッフを含む、パート勤務の歯科衛生士が多いことです。現在は歯科衛生士7人、受付・アシスタントスタッフ5人がそれぞれのライフスタイルに合わせたシフトで働いています。スタッフが働きやすい環境づくりは、結果として診療の質も高めることになると思うんです。最近、歯科衛生士用の診療チェアを1台増設しました。これにより予防やメンテナンスにより力を入れられる体制が整い、スタッフのモチベーションも上がったように感じます。「仕事と私生活の両立」という言葉をよく耳にしますが、実際形にしていくことの大切さを実感しています。
今後についてはどのようにお考えでしょうか。
歯科診療の中でできることを着実に行い、必要に応じて歯科口腔外科や矯正歯科など各分野の専門家との連携も大切にしてきました。私の座右の銘は、「どこへ向かうかを知らないなら、どの道を行っても同じこと」。これは私の好きな歌の中にある言葉です。先のことは誰にもわかりませんが、今この時を大切に、スタッフが生き生きと働ける環境をつくることが私の役割だと感じています。また、私たちと一緒に働く歯科衛生士も増やしていきたいと考えているところです。先ほども申し上げたように、子育て中の方も働きやすい環境づくりに力を入れていますので、同じ志で診療に向き合えるスタッフと出会えたらうれしいですね。
最後に、読者へメッセージをお願いします。
歯科医院は、どうしても「痛いから行く」「具合が悪くなってから行く」というイメージが強いかもしれません。でも、私たちはそうではない歯科医院でありたい。小さなお子さんからご年配の方まで、気軽に相談できる場所として、これからも地域医療に貢献していきたいと考えています。歯のことで気になることがあればどうぞお気軽にご相談ください。