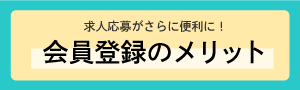三島歯科 (大阪市東住吉区/針中野駅)
三島 賢郎 院長の独自取材記事
大阪を代表する商店街の一つ、活気あふれる駒川商店街が目と鼻の先。近鉄南大阪線・針中野駅から徒歩すぐの、昔ながらの住宅地にある「三島歯科」は、れんが造り風の落ち着いた外観が目印だ。院長の三島賢郎先生が目標とする医療は「口腔内の治療を必要としない」という状態。研修医時代に出会って感銘を受けた、アメリカの歯科医師ダリル・レイモンド・ビーチ氏が提唱する「pd診療」を取り入れ、自らが定義する“正確な診療”をめざして日々奮闘する。患者と二人三脚、理想の歯の実現に向けた予防をはじめとする取り組みについて、三島院長に話を聞いた。
求める“正確な診療”をめざして導入した「pd診療」
診療台がチェアではなくフラットなベッドタイプなので驚きました。
重力の作用の関係で、人の体というのは「横になる(寝ている)、真っすぐに立つまたは真っすぐに座る」という状態が最も安定するといわれています。この水平な診療台では、完全に仰向け姿勢の患者さんの後方に、術者が真っすぐに座ることができます。これはビーチ先生が提唱した「pd(proprioceptive derivation)診療」という、水平のユニットを使用した診療スタイル。安定した無理のない姿勢の組み合わせは患者・術者の双方のストレスが減り、また、私が求める正確な診療が実現できると考え、取り入れました。このユニットのもう一つの大きな特徴は、「うがい」をするところがないこと。いちいち起き上がってうがいをすることで多くの時間が使われます。診療時間を大切にするために、アシスタントが横にいて、口の中をきれいに洗うシステムになっているんです。
どういうきっかけで、pd診療をお知りになったんでしょうか。
大阪大学歯学部を卒業後、研修医として残った小児歯科ではこうしたベッドを使用していたんです。子どもは、大人用のチェアだと背もたれを動かすたびに頭の位置が変わるというのが理由なんですが、ある時、小児歯科の先輩がベッドを使って行うpd診療を紹介してくれたんです。後にセミナーを受講することになり参加したところ、真っすぐ座ったままミラーを使って口の中が良く見え、歯が削れました。口の中の処置はこの状態で行うべきだと思いました。その後の勤務医時代に、時間を見つけては模型などを使って練習。ベッドを用いた歯科医院ではなかったので、チェアを目いっぱい倒して試行錯誤しながらでしたが(笑)。それから開院に際して導入しました。
日本ではあまり一般的ではないようですね。
“座る”というスタイルの発想は、診療に必要な明かりがその昔は太陽光しかなかったことから生まれたといわれるんです。そのため口の中を光源に向け、術者が体を折り曲げてのぞき込むしかなかったんですね。歯科が始まった当初より、こうした椅子タイプが用いられてきた長い歴史がありますから、大学では見学や実習もチェアでの診療ですし、広がるにはどうしても時間がかかるんでしょう。患者さんもまずは座るのが当たり前と思っているので、ベッドを前にして少しばかり戸惑われる場合がありますが、ほんの最初だけです。仰向けのままで会話をするわけではありませんし。ベッドは治療だけ、説明はカウンセリングルームへ移動して行うなど、処置と会話の場所を別々に設けることが仕組みとして決められています。この使い分けは、歯科医院での治療が苦手な人にも安心感につながるようです。
正しい歯磨きと歯科医師の定期的サポートで予防を
診療の中で、特に予防歯科に力を入れておられるんでしょうか。
「処置の必要がない」というのが健康な口腔内の状態ですよね。それが私の目標とするところです。定期検診などの診査で問題が見つからず、日頃のお手入れだけでは落としきれない汚れを掃除する以外は“何もしなくて良い”というのが究極の理想ですね。「チェックしましたが、大丈夫です」と伝えて、完了(笑)。
歯の健康な人が増えると、歯科医院に来る患者さんがいなくなってしまうのでは?
原因があるから結果がある、つまり病気になるわけです。虫歯や歯周病は「細菌」というよりは「歯垢」が原因として深く関わるので、歯垢をしっかり取り除けば、かなり防げる病気ということになります。ただ、皆さんの努力だけではどうしても難しい部分もあるというのが現実。それをサポートし、予防に努めるのが私たち歯科医師の役目でもあると思っています。
毎日しっかり歯磨きをしているつもりの方は多いと思うんですが……。
ペーストをつけた歯ブラシを、口の中で1~2分ゴシゴシ動かすことが歯磨きだと思っている方が多いと思います。それは大きな勘違い。歯科医師の言う歯磨きとは歯垢を取り除くことで、皆さんが習慣的に行っているブラッシングとはまったく別物なんです。しみついた習慣を変えるというのが、もう本当に大変で。歯垢を取り除くためには、歯の一本一本の形状に細かく注意しながら、“狙い撃ち”して磨く必要があります。噛み合わせとか、この歯と歯の間の隙間、というように、どの歯のどの辺に毛先を当てるのかを意識しないと駄目なんです。こんなふうに真剣に磨けば10分ぐらいはかかるでしょうね。誰でも歯磨き指導を受ければ、疲れることなくきちんと磨けるようになりますよ。お口の中を見たときに気になる所があればすぐに指導したいので、患者さんには自宅で使用している歯ブラシをいつも持参してもらっているんです。
10分も磨くとなると、朝昼晩で実行するのは大変ですね。
歯垢を取り除くためのしっかりした歯磨きは、寝る前に行えば十分です。けれどそれを助けるために、簡単に汚れを落とす程度でいいので、毎食後こまめに歯磨きをするのがお勧めですね。それから歯垢などとは別に、口の状態、具体的に言えば唾液の量や質によっても虫歯になりやすい状態があります。口が渇きやすい人は要注意です。定期検診ではそうした口腔内の状況の把握やケアも行えるので、痛みや虫歯がなくてもぜひ検診に来てもらいたいですね。
蓄積した診療記録をベースにした臨機応変なケア
定期検診について教えていただけますか?
まずは問診を行います。歯茎がムズムズするとか、冷たいものがしみるといった気になり始めた症状があれば、この時点で申告してもらいます。次にエックス線写真の撮影。情報量が多く虫歯の検出がしやすいといわれる咬翼法という撮影方法で、半年に1回程度で行います。口腔内の写真も撮り、虫歯、歯周病、噛み合わせの状態をチェックし、診査の結果を記録します。最後にカウンセリングルームに場所を移して、結果報告とセルフケアの指導。もし歯に問題が見つかれば応急処置や以降の治療についての相談をする、というのが一般的な流れです。
きちんと定期検診を希望される方が多いそうですね。
そうですね。歯の健康に対する意識の高い患者さんが多いと感じています。そのため診査や治療の記録を取り続けて経過を観察し、見守ることができるんです。長く通院されていると、皆さん当然ながら年を取られるので、今までできていたことが今までどおりできなくなってきたりします。例えば、視力が弱くなってきたり、リウマチなどで歯ブラシが持ちづらくなってうまく磨けなかったり、唾液が減ってきたり。そういうときに、じゃあ、どうやって歯を磨くのか、歯の健康をどのように維持していくのか、蓄積してきた個々人の資料をもとに一緒に考えることができるんです。急患の電話があった場合にも、それまでの記録を比較すれば何が起こったのかだいたい見当がつくので、スムーズな治療に役立てられるんです。
読者へのメッセージをお願いします。
誰でも虫歯になれば、特に痛みがあれば治療しようと思いますよね。でも「治して終わり」では、口の中の疾病は一向になくなりません。お口の中全体が今どういう状態なのかを知ってもらい、だからこういうことが起こっているんだとわかってほしいです。もちろん歯の磨き方を含めて食生活や習癖、習慣など、要因は人それぞれでしょう。そこで「こんなことをしていませんか?」と思い当たる原因を列挙して、対策を探るようには努めているんですが、それだけではなかなか予防に直結しません。患者さん自身の自覚と協力が必要なんです。父と同じ道に進み、地元に戻って開院して19年。これからも皆さんと一緒に、気軽に相談できる「かかりつけ医」として地域に寄り添って、誰もが自分の口の中は自分で守るという意識を持つように働きかけ続けたいし、そのために精一杯お手伝いさせてもらいたいですね。