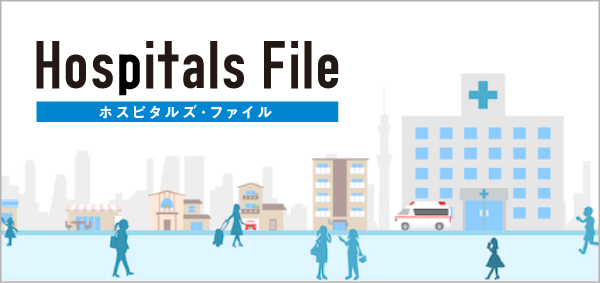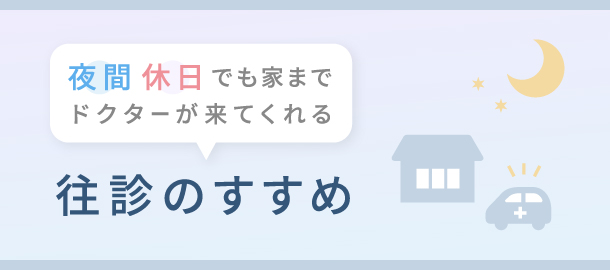藤末 洋 院長の独自取材記事
藤末医院
(川西市/川西能勢口駅)
最終更新日:2023/06/01

阪急宝塚本線の川西能勢口駅から東へ5分、国道176号沿いにある「医療法人社団雄敬会 藤末医院」。川西市が今のように発展する半世紀以上前に先代が開設し、息子である藤末洋院長が継承した。地域の人々の人生に寄り添い診療を行っている。待合室には患者からプレゼントされた花の鉢植えなども飾られ、地域との関わりが垣間見える。内科・泌尿器科を標榜。「泌尿器科が専門ではあるけれど、それに特化することなく、さまざまな患者の症状を受け止め全身を管理するプライマリケアを行っている」と話す藤末院長。その考えから在宅医療にも注力している。医師会活動や地域医療連携推進法人の活動も熱心に行う藤末院長に、地域への思いや高齢社会における医療の役割など話を聞いた。
(取材日2020年1月16日/更新日2023年2月22日)
プライマリケアに注力し、患者の人生とともに歩む
開設した時期や経緯について教えてください。

まだ川西市が田舎町で医師が数人しかいなかった1948年に、父が開設しました。その父が1995年に急に倒れて亡くなってしまったんです。当時、私は勤務医としてやりがいを感じて仕事をしていたのですが、入院中の父に「在宅で診ている患者さんを診てきてくれ」と言われて訪問したところ、私が行くことで患者さんやご家族がとても安心してくれたんです。そのときに「この患者さんたちを困らせてはいけないな」と思い、継承する決意を固めました。38歳の時ですね。兵庫医科大学を卒業して泌尿器科を専門とし、大学で泌尿器科助手や関連病院で透析を含めた全身管理を学んだ後に、海外での勤務、その後市立川西病院の泌尿器科医長になったばかりの頃で、まだまだ第一線で手術なども行い頑張ろうと考えていた時期でしたね。この診療所を継ぐのはもっと先のことだと思っていたので、継承には大きな決断が必要でした。
患者層は幅広いのでしょうか?
幅広いですね。中でもやはり高齢者が多い。継承した頃に50代だった方が、今は75歳ですから。かかりつけ医としてお付き合いさせていただいてる方が多いので、おのずと患者さんの年齢も高くなってきています。またご家族ぐるみで通院している方も多いですね。
診療において心がけていることはなんでしょうか?

地域の人がなんでも相談できて、その方の歩みに寄り添う診療を心がけています。なんでも診つつ、患者さんの訴えを受け止めた上で、必要であれば専門医療機関を紹介するようにしています。これからますます少子高齢化は進みます。増え続ける高齢者にどのように医療を提供するか。専門に特化し、今までの早期発見・早期治療・予防だけではカバーできなくなってきます。それを解決するためにも、病院と診療所の役割分担を考えネットワークを駆使して診療分野ごとに専門の強みを持つ医療機関と連携し、必要であればすぐに紹介する。診療所では、日々の全身管理を受け、気軽になんでも相談し、「何かあってもしっかり医療連携しているから大丈夫」と患者さんに安心してもらえるように。そうした体制づくりを心がけ、日々診療を行っています。
多職種チームの連携を深め、在宅医療の患者を支える
在宅医療は、高齢で通院できなくなった患者さんに対して行っているのですか?

基本的にはそうですね。サービスつき高齢者向け住宅や認知症対応グループホーム、ご自宅で在宅医療を受けている方などの所へ伺っています。在宅医療は、介護する方がいないとなかなか難しいんですよ。医師の力だけではできない。だから10年以上、この診療所内で、多職種連携のターミナル会議を行っています。月に1回、地域のケアマネジャー、ホームヘルパー、訪問看護師、薬剤師、患者家族などを招いて、在宅医療の患者と外来の高齢患者のカンファレンスを行うわけです。その他にもデバイス機器を使ってタイムリーに情報を密に共有できるICTを用いた連携システムも導入し、それぞれの情報や知識を提供し合って患者さんを支えています。訪問診療は午後から患者さんのもとへ伺い行っています。
地域医療に対する思いをお聞かせください。
少子高齢社会が進む中で、今、医療にパラダイムシフトともよばれる大きな変化が起こっているんです。当たり前のことが当たり前でなくなる。高齢になり通院できなくなる患者さんが今後増えてきます。人生100歳の時代に、どのように住み慣れた地域で人生に最期の時まで寄り添っていくかということが大きな課題ですね。在宅医療の現場ではさまざまな領域の疾患が複合的に起こるので、各専門の医師が連携することが重要です。またケアマネジャー、訪問看護、薬剤師、ホームヘルパーなど多職種で支える医療が連携して、多職種で支える医療が今後必要であることを啓発していきたいと考えています。
高齢化が進むにあたって、患者自身が備えておくべきことはなんですか?

「高齢になって重い病気になったときどのような治療を望むか?」などを、元気なうちから意思表示しておくことも大切です。今は元気でも病気は急にやってきます。介護や療養が必要になってから考えるのでは遅い。そうなる前に、どこへ相談するのか、終末期医療などについても家族と話し合って準備をしておくことも必要です。その一つのツールとして行政と医師会と協力をして人生会議(ACP)のための冊子を作ったんです。自分の人生の物語を記すシート。終末期になったらどのような医療を望むのか、生活も含めてどうありたいかなどを意思表示をしておく。自分の意思で判断し記しておくことが悔いのないよう自分らしく最後まで生きることにつながるのだと思います。
安心して人生を送れるよう、地域貢献に力を尽くす
どうして医師になろうと思ったのですか?

やはり父の影響が大きかったと思います。父は内科医でしたが、開業当時は、医師が少なく専門以外の領域も診ていました。雨がっぱを着て、雨の中オートバイで往診に行っている姿を見ていて、「必要とされる、信頼される仕事をしているんだ」と子ども心に感じていました。実際自分が医師になって、プライマリケアを行う医師となり「医師になって良かった」と感じる時は、患者さんが天寿を全うされたときに、ご家族から「先生に診てもらえて良かったです」「私も先生に最後まで診てもらいたい」と言われるときですね。医者冥利につきます。
休日はどのようにリフレッシュしているのですか?
自宅の庭で野菜を育てたり、花を育てたり。土を触るのが好きですね(笑)。今年はレモンが豊作で一本の木から300個収穫できたんですよ。国産無農薬レモンです。バラを育てるのも好きですね。すごく世話が大変なんですが、こつこつ手をかけて育てるのが好きなので苦にならない。そのバラを待合室に飾ることもあります。私が花を育てるのが好きなのを患者さんは知っているので、お花を頂くこともあるんですよ。今シャコバサボテンの鉢植えを待合室や玄関に置いていますけど、何度も株分けして植え替えを繰り替え、10年以上も花が咲き、年末の風物詩になっています。子育てと同じように、手をかけるほど反応してくれるので楽しい。気分転換にもなるし、癒やされています。
今後の展望についてお聞かせください。

ゲートキーパー・病気の門番という機能を持ったかかりつけ医として、地域に信頼され何でも相談される医師でありたいですね。患者さんが希望する限り、その方の人生とともに最期の見取りまで寄り添うつもりで診療し、患者さんが高齢になっても安心して頼ってもらえる存在に。また、いざというときに地域の方が困らないように、最後まで自分らしい人生が送れるように、地域の皆さんに対してサポートをしていきたい。市民医療フォーラムや講演会などいろいろ企画していき、一開業医ではできないことは病院や医師会や行政とワンチームになって地域に貢献したいと考えています。