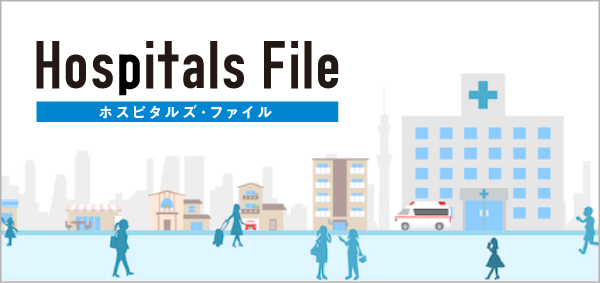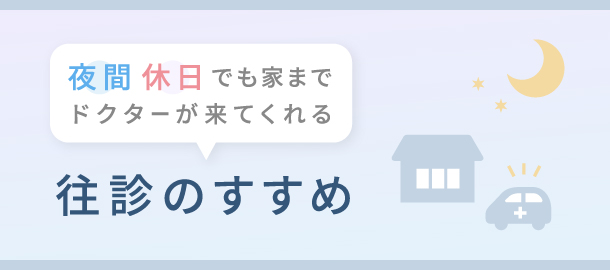小林 邦生 院長の独自取材記事
小林内科
(名古屋市北区/黒川駅)
最終更新日:2023/11/21

名城線黒川駅より徒歩5分。この地で40年以上診療を続ける「小林内科」は、小林邦生先生が父に代わり2009年に院長に就任した。小林先生の「患者さんがなるべく緊張しないように」という想いから、院内にはBGMが流れ、待合室には絵が飾られるなど、リラックスできる雰囲気になっている。「患者さんに気分が良くなって帰っていただけるよう、法人名の「忠恕(ちゅうじょ)」に込めた意味のとおり、真心と思いやりを日々心がけていきたい」と話す小林先生に、診療で心がけていることなどについて詳しく聞いた。
(取材日2016年11月2日/情報更新日2023年7月31日)
消化器領域を得意とし、内科全般について幅広く診療
患者さんは、どんな年齢層の方が多いですか?

若い方もみえますが、多いのは50代~80代前後の方ですね。開院して41年たちますが、ずっと通ってくださっている方が多く、中には診察券番号1番の方もいらっしゃいます。近くにお住まいで歩いて来られる方が多いのですが、春日井市や豊山町から来る方や、父の代から通っている方で引っ越し先から通っている患者さんもいらっしゃいますよ。
先生のご経歴についてお聞かせください。
研修医を終え最初に赴任したのが名古屋市立緑市民病院だったのですが、医療技術全般を上司の先生たちに教えていただき、その経験が今の自分の糧となっています。その後磐田市立総合病院に赴任したのですが、そこでは救急医療に力を入れていて、当直の時は眠れないほど忙しかったです。当院を継ぐまでは、消化器内科で内視鏡や大腸を専門にしていました。その後愛知医科大学病院に赴任し、大学病院では専門分野を分けるのですが、胆のうや膵臓に関して詳しく調べるグループがあり、胆のうがん、膵臓がん、胆管結石や膵炎などをメインに診ていました。石があれば側視鏡という特殊な内視鏡を使って取り除き、詰まってしまった場合はチューブステントを挿入したり、出口が狭い時は切開して取り出したりしていました。1人ではできない熟練を要する手段で、大変だったことが印象的でした。
勤務医時代と開業された今とでは、どのような違いがありますか?

今は内科全般のことを診ますから、頭のてっぺんから足の先までさまざまな症状でおみえになる方が多くいらっしゃいます。そのため、勤務医の頃のように胆道や膵臓だけに限って診れば良いのではなく、全体を診る必要があります。病気だけではなくて、患者さんの抱えている問題や悩みなども含めて考えるようにしていますね。また、医学部で習うのは西洋医学ですが、薬だけ出してもそれだけではなかなか患者さんを治せないという壁にぶつかることがありました。普段の食事や生活スタイルを含めて改善できるところはないかと探したり、今は西洋医学をベースに他のいろいろな医学を取り入れようと日々勉強しているところです。また、管理栄養士さんも在籍していただいております。
健康づくりは、体と心の両面からアプローチ
先生はホリスティック医学という分野を勉強されているそうですが、それはどのようなものですか?

病気だけを見るのではなく、人間を丸ごと診るというスタイルの医療です。江戸時代の書物で日本固有の風土に合う生活様式や食事について書かれているものがあるのですが、これを現代語版にした先生が、ホリスティック医学を広めた医師の一人であり、その先生との出会いが、この分野に興味を持ったきっかけでした。関東地方にいらっしゃる先生で、外来の見学にも行ったこともあります。私も心がけていることなのですが、患者さんを迎え入れる時に自ら立って呼び入れてあいさつをしたり、必ず聴打診をするなど、西洋医学をベースにすごく丁寧な診察をされていたのが印象的でした。私は、「手当て」というのは医療の原点だと思っています。手を当てるという、医療器具も何もない時代から手を当てて患者さんを診るということをしていたんですね。ですから、嫌がられない限りはできるだけ聴打診を行っています。
昔の医療でも、今に生かせる部分があるのですね。
そうです。それが現代にそのまま通じるわけではないですが、野菜などは、昔と大きくは変わっていないでしょうし、人間の体も大きくは変わっていません。平安時代に書かれた医学書には、自然界のあらゆるものを使って創意工夫されている処方がいろいろ載っていたりするので、参考になるものは取り入れていきたいと考えています。西洋医学は病気を悪いものとし、体の中で病気と戦うと捉える傾向が強いのですが、東洋に存在した医療は心の調和や体の具合を整えることで健康を保つという考え方になります。がんなど治らない病気の場合でも、決して「患者さんが戦い続けなければいけない」という考え方だけではないということを勉強しています。
こちらのクリニックの内視鏡検査について教えてください。

胃や大腸の内視鏡検査をメインにやっています。胃の内視鏡検査は経鼻か経口で、どちらにするかは患者さんと相談して決めています。大腸ポリープは、大きくなければ日帰りで切除しています。経鼻のカメラのほうが管が細く患者さんへの負担が少ないので、鼻の病気がなければ経鼻のカメラを使うことが多いですね。一方、経口カメラは、ハイビジョン並みの画質が得られるのが利点です。経口の場合は、口腔内や喉に当たらないように工夫して挿入しています。
地域の人々の健康を守るために貢献していく
診療の際に最も心がけていらっしゃることはどのようなことでしょうか。

人間には持って生まれた自然治癒力というものがあるので、それをなるべく引き出してあげるよう努力しています。もちろん中には医師が薬を処方したり、処置をしたりして、病気の治癒をめざすということもありますが、西洋医学だけで治せないものを「治らない」とせず、自然に治るように持っていくということに今後、力を入れようと思っています。孔子の書物に出てくる一文に「夫子の道は忠恕(ちゅうじょ)のみ」という言葉があります。小林内科を医療法人にする時、法人名を何にするか家族で相談していたのですが、当時私は高校生で、漢文の授業で忠恕という言葉を習ったことを伝えたのです。「孔子先生のめざす道は一つの信念で貫かれている。それはまごころと思いやりだけだ」という意味なのですが、法人名にぴったりだねと採用してもらいました。その言葉のとおり、まごころと思いやりを持つよう日々心がけていきたいと思っています。
先生は現在、名古屋市北区医師会の会長も務めているそうですね。
昨年名古屋市北区医師会の会長を頼まれたのです。頼まれた時は、そんな大役はなかなか引き受けられないと思ったのですが、当院に通っていらっしゃる患者さんだけでなく、地域の方の健康のためにちょっとでも役に立てるのならと思い引き受けました。日々の診療だけではなく、地域の人々が少しでも病気に苦しまずに済むよう貢献していきたいと考えています。現在は、北区医師会でパーソナルヘルスレコードを推進する取り組みを行っています。「じぶんカルテ」と題して、患者さんが自分の健康に関する情報を正しく主役することで適切な医療を受けられるようになることで、最適な医療を受けられるようになっていけば、皆さんが幸せになれるのではないかと考えています。他にも心不全に対しての地域ぐるみの取り組みなど、地域に貢献できるよう頑張っていきたいと思っています。
最後に今後の展望と、読者へのメッセージをお聞かせください。

今の延長になりますが、西洋医学をベースにしてさらにいろいろな医学を勉強し、良いところを取り入れて行きたいと思っています。何かを「あれは駄目だ」と頭ごなしに否定するのではなく、良いものがあれば先入観を持たずに柔軟に取り入れていきたいですね。肝臓・胆のう・膵臓内科については専門的な設備がないと開業医レベルで治療を完結させるのは難しいのですが、大学病院での経験や知識をもとに、膵臓や肝臓について詳しく診ることができます。困った時に相談していただいて、「こういう病院がありますよ」とコーディネートできるような架け橋としての役割も果たしたいですね。体の不調について、「大きな病院に行くのは大げさな気がするけれど、何かしたほうがいいのかな」という時に、窓口として当院に来てもらえればと思います。いろいろな医療機関がありますから、自分に合ったところを見つけることをお勧めしたいですね。