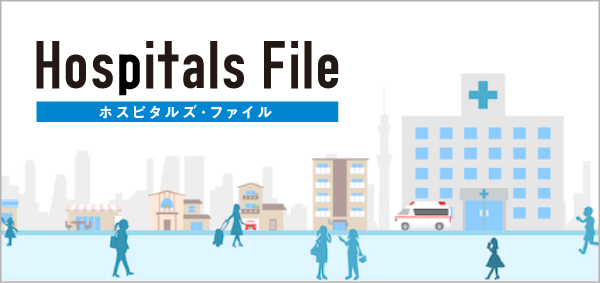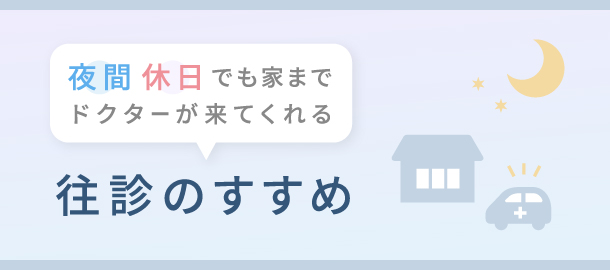動悸・息切れは重大疾患のサイン
血圧コントロールが治療の鍵に
かなやファミリークリニック
(杉並区/方南町駅)
最終更新日:2023/12/14


- 保険診療
東京都杉並区にある「かなやファミリークリニック」の金谷翼院長は、家族で通いやすい内科のかかりつけ医としての役割を担う一方、血圧コントロールを得意とする循環器内科の医師の一面も併せ持つ。勤務医時代、入院するレベルの高血圧患者を数多く診てきた経験があるからこそ、大動脈乖離や脳出血などの重い病気のリスクに対し、詳細な検査と薬のきめ細かい調整によって適切に対処することができる。動悸、息切れ、胸の痛みといった症状の訴えに、クリニックではどのような治療を行っているのか。また、患者があらかじめ知っておくべき高血圧に関する知識とは。金谷院長に初歩から解説してもらった。
(取材日2023年10月24日)
目次
軽度の高血圧は運動や食事管理で改善をめざし、さらに高い場合は降圧薬で心筋梗塞や大動脈瘤の予防を図る
- Q動悸や息切れがあるとき、どんな疾患の可能性が考えられますか?
-
A

▲生活習慣と関連のある循環器疾患を専門としている
動悸、息切れは近い症状に思われがちですが、実際には別々の病気が関係していることが多いです。まず動悸の場合は、不整脈、つまり脈の乱れから来ている可能性が高いですね。不整脈には脈が速くなる頻脈と、逆に遅くなる徐脈がありますが、動悸がするのは頻脈のときです。また、期外収縮といって、本来の脈とは別の拍動が入ってきてしまうと、それを動悸として感じることもあります。そのほか、不安神経症やパニック障害のような精神疾患による動悸も見られます。一方、息切れも不整脈の場合がありますが、例えば通勤中に階段を上がる時など、以前は平気だった運動で息切れを感じるようになったら、狭心症や心筋梗塞、心不全などが疑われます。
- Q動悸、息切れのある人が受診しないでいると、どうなりますか?
-
A

▲「まさか」が起こらないように早めの受診を促している
先に挙げた不整脈や心不全は、高血圧症が関係していることの多い状態です。また、脂質異常症がある場合も、心筋梗塞などのリスクを高めます。高血圧症も脂質異常症も多くは生活習慣に起因しており、これを放置すると、さらに危険な状態になりかねません。例えば、大動脈解離や大動脈瘤。前者は大動脈が中から裂けてしまう病気で、心臓に近い場所で裂けた場合、突然死の可能性が高いです。後者は大動脈にできたこぶが破裂するもので、こちらも死につながります。大抵の人が破裂するまで気づかないのも大動脈瘤の恐ろしいところです。そのほか、くも膜下出血や脳出血も、頭の血管が高血圧に耐えられなくなって起こります。
- Qこちらでは血圧のコントロールをどのように行っていますか?
-
A

▲金谷院長は血圧コンロトールを得意としている
血圧は、家庭で測った「上の血圧(収縮期血圧)」が基準値の135mmHgを超えている場合に、高血圧の部類と判断します。当クリニックでは、同じ高血圧でも135〜150未満の患者さんには薬は使わず、まず運動および食事管理を勧めています。日頃から適度に体を動かし、塩分控え目の食事を心がけることで、基準値内の血圧をめざすのです。一方で、家庭血圧が150を大きく超えている方には、すでに紹介した病気のリスクが大きいので、血圧を下げる降圧薬を使用します。いずれにしても、血圧のコントロールは、患者さんが自身で血圧を記録するプロセスが重要なため、診察時にしっかりと説明を行い、ご理解いただくように努めています。
- Q不整脈や心不全を予防するには、どうすればいいですか?
-
A

▲患者のライフスタイルに合った方法を提案している
やはり運動の習慣づけと食事の見直しから始めていただきたいです。ただし、いきなりマラソンのような激しい運動をするのはやめましょう。かえって危険ですし、無理をしても続かないものです。お勧めは、散歩や水泳。泳ぐのが苦手なら、プールの中を歩くだけでも相当な運動量になります。食事は、どれぐらい減塩が必要かとよく聞かれますが、まず日本人の食事はだいたいにおいて塩分過多であるという認識を持ってください。例えば、みそ汁を毎食飲むのもそうですし、ラーメンのスープを飲み干したら、それだけで1日に必要な塩分をオーバーしてしまいます。今は減塩してもおいしい食事が可能ですから、いろいろ工夫してみてほしいと思います。
- Q血圧が心配な患者を診るとき、先生が大切にしていることは?
-
A

▲継続した治療に尽力し、患者に寄り添っている
治療方針についてよくお話しして、患者さんに納得して積極的に治療を受けていただくことが非常に重要です。薬を理由なく中断したり、定期受診をやめてしまったりすると、せっかくの治療の意味がなくなってしまいます。そうならないためにも、初診の方はもちろん、再診であっても、まずしっかりと患者さんの訴えを聞くこと。その上で身体所見、つまり、その時の患者さんの体の状態を詳しく診察して、何が起きているのかを把握するという、医師の基本に忠実であるように努めています。それは治療に必要であるだけでなく「あなたのことをちゃんと診ていますよ」というメッセージを伝え、患者さんに信頼してもらうための一歩でもあると考えています。