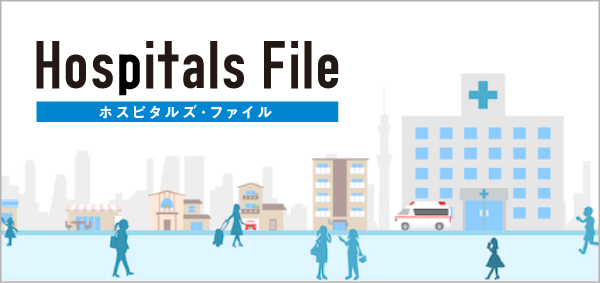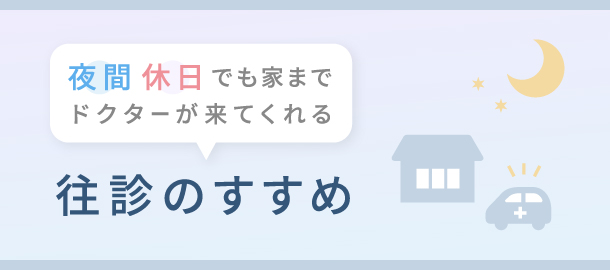大塚 寛樹 院長の独自取材記事
あいら中央眼科
(姶良市/帖佐駅)
最終更新日:2021/10/12

イオンタウン姶良からほど近い「あいら中央眼科」。外観も内装もスタイリッシュで、ガラス張りの待合室からは周囲に施された植栽の四季折々の風景を楽しめる。院長の大塚寛樹先生は眼科の医師として、網膜剥離や加齢黄斑変性症といった網膜硝子体疾患の治療や手術を中心に研鑽。同院では眼科疾患全般に広く対応するとともに、小児の眼疾患の治療や白内障手術に力を入れている。患者とのコミュニケーションを重視し、「まずは患者さんのお話をしっかりとお聞きしてから、病状や治療方法について丁寧に説明するよう心がけています」と優しく語る大塚院長に、医師をめざしたきっかけから今後の展望まで幅広く聞いた。
(取材日2021年3月10日)
かかりつけ医として、子どもから高齢者まで幅広く診療
医師をめざしたきっかけや眼科を選んだ理由をお聞かせください。

小学生の頃、私の地元に医療過疎地域で活躍されている先生が講演にいらっしゃいました。医療への取り組みについてのお話にとても感銘を受け、「医師になりたい」という思いが芽生えました。眼科を選んだのは、内科的な治療にも外科的な治療にも幅広く対応できるところに魅力を感じたから。開業も視野に入れており、一人の患者さんに日常的なフォローから手術や術後の管理まで幅広く関わることができる診療科であることも決め手の一つでした。鹿児島大学病院の眼科に入局後は、網膜剥離や加齢黄斑変性症といった網膜硝子体疾患の治療を中心に研鑽。手術が欠かせない分野で、手術を正確にスピーディーに行うことに情熱を注ぎました。当時の経験は今日の診療に大いに役立っています。
開業にあたってこの地を選ばれたのはなぜですか?
私は鹿児島で生まれ、小さな頃より地元鹿児島で働きたいと思っていましたので、鹿児島大学医学部に進学し、卒業後も鹿児島大学病院の眼科に入局しました。勤務医時代には、姶良市の青雲会病院や霧島市にある病院でも勤務し、この地域にお住まいの患者さんも多く担当しました。「患者さんと距離の近い開業医になりたい」と考えていましたので、「なじみもあり医療的ニーズも高いこの地域に貢献したい」と、選びました。姶良市は近年人口も増加し、著しい発展を遂げています。青雲会病院に勤務していた頃はこの辺りにもまだ田畑が広がっていたのですが、建物が増え、町並みも随分と変わりました。
どんな患者さんが来院されていますか?

小さなお子さんからご年配の方まで、幅広い年齢層の患者さんに来ていただいています。お子さんでは、近視や弱視の治療が多いですね。近年、小さな子どもの近視や乱視を調べるレフラクトメータという検眼装置が普及し、3歳児健診の際などに早期発見されるケースも増えています。3歳前のお子さんでも「顔を傾けて物を見ている」「上目遣いに物を見ている」などのお子さんの様子から、ご家族が連れてこられることもあります。ご年配の方では、白内障や加齢黄斑変性症の患者さんが多いです。加齢黄斑変性症の場合、薬剤を眼内に入れる硝子体内注射やレーザーによる治療を主に行っています。また冬の終わりから春にかけては、花粉症による目のかゆみや充血を訴えてこられる方も多いですね。点眼薬を処方するとともに、アレルギー検査で原因物質を特定するなど、患者さんの症状改善に向け、サポートするよう努めています。
子どもの病気の治療や白内障の日帰り手術に力を入れる
力を入れている診療についてお聞かせください。

お子さんの病気の治療や白内障手術に力を入れています。小さなお子さんの場合、待ち時間が長くなると集中力が切れ、正確に検査できなくなってしまうこともあるため、予約優先制を採用。待ち時間が比較的少ないため、無理なく検査を受けていただけます。白内障手術に関しては、患者さんの生活状況を把握し、術後の見え方や日程などを相談の上、できる限り患者さんのご希望に沿うよう調整しています。勤務医時代に多くの手術を経験したことから、「瞳孔の開きが悪い」「水晶体が硬い」など一般的には手術が難しいケースでも、当院にて白内障手術を受けていただける可能性があります。基本的に日帰りで行いますが、入院での手術を希望される場合は、近隣の病院と連携して対応しています。また、目の疾患は糖尿病などの全身疾患とも深く関わっているため、他の医療機関と連携して、安心して治療に臨んでいただける体制をとっています。
診療機器も充実しているようですね。
網膜硝子体疾患を専門にしていることから、網膜疾患や緑内障の診断に使う光干渉断層計(OCT)を導入しています。また、鹿児島県内ではまだ数少ない広角眼底カメラもいち早く導入しました。一般的な眼底カメラよりも広範囲の撮影が可能で、眼底や血管の状態を詳しく観察できるんです。瞳孔を開く目薬を使う従来の眼底検査の場合、目が見えにくくなるため、検査後は車の運転などを控えていただかなくてはなりませんが、このカメラであれば、瞳孔を開くことなく検査が可能ですので、患者さんの負担も少なくて済みます。もちろん病状によっては従来の眼底検査を行う必要がありますが、広角眼底カメラを使うことでその頻度を減らすことができます。
目の健康を保つにために気をつけるべきことは?

若い方をはじめ、多くの年代で、デジタルデバイスを使う機会が増えています。そうした機器を長時間使うと目に負担がかかります。研究段階ではありますが、視力の低下につながる可能性も示唆されているため、特にお子さんの使い方には注意が必要です。ご年配の方に気をつけていただきたいのは、緑内障や加齢黄斑変性症といった病気。眼圧が高いと緑内障のリスクが高まるのですが、自覚症状はあまり見られないため、年に1回は眼圧検査や眼底検査などを受けていただきたいですね。また、加齢黄斑変性症による物のゆがみや緑内障による視野の欠損などは両目で見ると補完し合うため、見落としやすいのが特徴。時折片目で物を見るなどして、見え方をチェックすることをお勧めします。
患者一人ひとりに寄り添う、丁寧な診療を心がける
診療で心がけていることは何ですか?

最も大切にしているのは、患者さんお一人お一人と十分にコミュニケーションを取ること。まずはお話をしっかりとお聞きした上で、病状や治療方法について丁寧に説明するよう心がけています。また、患者さんの立場に立って診療するようにも努めています。地域のかかりつけ医として、一人ひとりの患者さんとじっくりと向き合い、長くお付き合いさせていただきたいと思っています。通院されている患者さんのご家族が来院してくださったときには、患者さんからの信頼を感じ、うれしくなります。
クリニックの外観や内装にもこだわりを感じます。
病院に行くと緊張する方も多いのではないでしょうか。少しでもそんな不安をやわらげ、皆さんにリラックスして診療を受けていただけるよう、病院らしくない雰囲気のクリニックをめざしました。周りに植栽を施し、春には色とりどりの花々、秋には紅葉と、待合室から四季折々の風景を楽しめる造りになっています。また、目の病気を抱えた患者さんが来院されますので、内装は落ち着いた色合いにし、椅子もシックなデザインでありながら消毒しやすいものを選ぶなど素材からこだわりました。患者さんからの評判も上々です。
休日はどのようにリフレッシュされていますか?
5歳と8歳の子どもがいますので、休日は家族で日帰り温泉に出かけたりしてリフレッシュしています。また、診療日には、ここまで30分ほどかけて車で通勤しているのですが、その時間が良い気分転換になっていると感じています。行きは朝礼でスタッフに話す内容について考えたり、帰りはその日に来院された患者さんについて思い返したり。考えをまとめ、気持ちを切り替えるとても良い時間になっていますね。
今後の展望と、読者へのメッセージをお願いします。

私のモットーは、お一人お一人丁寧に手術を行うこと。そのため、1日の手術件数を制限するようにしています。手術の日程なども含め、できる限り皆さんのご希望に合わせられる体制を整えていきたいと思っていますので、ご都合など遠慮なくお申しつけください。専門とする網膜硝子体疾患に限らず、地域のかかりつけ医として幅広い眼科疾患に対応するため、常に新しい知識や技術を学び、それを患者さんに還元していくことをめざしています。目に関するお困り事があれば、どんなことでもお気軽にご相談ください。