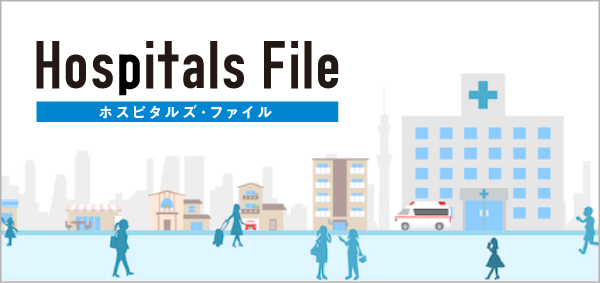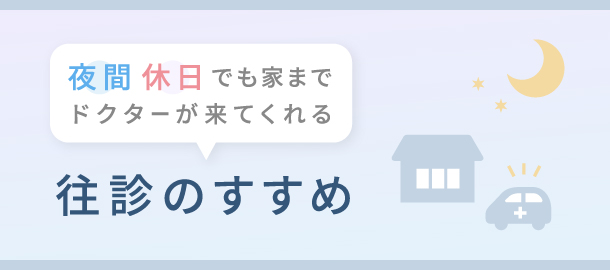三原 裕嗣 院長の独自取材記事
四日市内科ハートクリニック
(四日市市/中川原駅)
最終更新日:2021/10/12

近鉄四日市駅近く松本街道沿いにある「四日市内科ハートクリニック」は2017年に開業。三原裕嗣院長は心臓疾患を専門とし、東京やアメリカで先端医療を学んだスペシャリスト。心臓超音波検査(心エコー)を得意としている。同院では「地域医療を発展させ地元に貢献したい」と、心臓リハビリテーション、心臓の在宅医療など、これまで地域に十分に行き届いていなかった医療を導入することに力を注ぐほか、病院や地域のクリニックと連携を取り、適切な提案を心がける。医師である祖父母や父から受け継いだ医療人としての真摯さが魅力の三原院長。患者の将来を見据えた心のこもった治療に信頼を置く患者は多い。そんな三原院長からさまざまな話を聞いた。
(取材日2019年4月22日)
心臓病を中心とした診療で、地域医療の発展に力を注ぐ
開業前、東京の救急病院で経験を積まれたそうですね。

もともと学生時代は救急医療をやりたいと思っていました。救急というのは非常に広範囲の知識がいるということで、内科系の研鑽をしっかり積んで進みたいと思い、大学卒業後は東京に移りました。私は四日市出身で大学まで名古屋に通っていましたので外にも出たいという希望がありました。とにかくたくさんの経験ができる場所をと心臓病の研鑽に最初に選択したのが、心臓外科手術の症例を数多く扱っている榊原記念病院です。救急の場では、消化器系や循環器系の病気、特に心臓の病気はより深く勉強する必要があり、患者さんの状態を瞬時に把握できる心臓エコーの重要性を実感しました。このほか、伝統のある病院の考え方やチーム医療の大切さ、患者さんの対応やリスクコントロールについて、また、手術後の心臓リハビリテーションを通して患者さんが元気になるまで、責任を持って診ることの大切さなども学びました。
そんな中、開業のきっかけは何でしたか?
5年間勤務した東京の病院では、いろんな方から求められて医療を提供することにとてもやりがいを感じていましたが、一方で、地元で開業医としてやってきた祖父母や父の背中を想う自分がいました。そんな折、祖母の葬儀があって、改めて祖母が医療だけではなく多くの地域貢献をしてきたことを感じたんです。私も医療の枠にとどまらない、何か地域全体に貢献できるようなことをしたいと思うようになり、地元の患者さんを責任を持って診ていくことの魅力を認識しました。その後四日市に戻り、市立四日市病院でカテーテル治療や、救急医療に近いところで心臓疾患の患者さんに向き合う中で、一流の病院にはあるのにこの地域の病院にはないことを何とかしてやりたいという思いが強くなったんです。心臓リハビリテーションもその一つで、取り入れたいと想い開業に至りました。
クリニックの特徴を教えてください。

診療内容としては循環器内科・内科・小児科・アレルギー科です。アレルギーに関しては、私自身子どもの頃から喘息があったのと、苦しむいろんな患者さんに関わってきた経験から、スギ花粉や鼻炎など舌下免疫療法を取り入れ、根本的に抑えていく治療も行っています。専門とする心臓病の循環器診療では、私だけでなく看護師や理学療法士、ほかの医師も含めてチームで質の高い医療を提供できるようにしたいと考えています。また、生活習慣病に対しては、管理栄養士など他職種のスタッフが加わり、看護師からも生活全般への指導も行っています。医師は私のほかに小児科を専門とする父、あと同じ循環器や内科が専門の下郷卓史先生には開院時から非常勤で協力してもらっています。下郷先生は心不全が専門で、心臓リハビリテーションにも豊富な知識を持つ医師です。皆で一丸となり、より良いリハビリテーションを提供していきたいと思います。
新鋭の心臓エコーを活用。精度にこだわった診断を
心臓リハビリテーションに注力される理由は何ですか?

心臓病の患者さんは、やみくもに運動をして一定以上負荷をかけ過ぎると、逆効果の場合もあるんですね。きちんと安全性を管理して、どれぐらいの運動をしていいのかを評価し、そのレベルで運動をしていくことが大切です。足は第二の心臓というように、心不全の方は筋肉を使わないと心臓病の状態が悪くなってしまうことがあります。心臓リハビリテーションというのは心電図をつけて、不整脈が出たりしないかを監視しながら自信を持って運動をしていただくというものなんです。退院後、どう動いていいかわからず心配だからと運動しなくなると、どんどん体力が落ちてしまいます。150日間は保険診療で通えますので週1~3回ぐらい利用し、無理なく運動することで徐々に動ける範囲を広げていってほしいですね。当クリニックでは医師と理学療法士が運動プランを提案し、チームとしてサポートしています。
3Dエコーなど、新鋭の検査機器を導入されていますね。
医療の質というのは、場所によって変わるべきではないというのが私の考えです。心臓専門と謳っている以上、来てくださった患者さんに対して大規模病院と同じようなレベルの医療を提供したいですし、「世界の標準レベル」というのが私の念頭にあって、やるべき医療をきちんと行うことが必要だと思っています。いい機械は患者さんの状態を把握し適正な評価に有用ですから、その分の投資は必要と思います。性能の悪いエコーではいくら頑張っても見えませんし、鮮明に映るエコーで見ることで的確な診断ができ、正しい方向に患者さんを導けると考えていますので、医療機械の精度や質は本当に大事ですし、いい医療を提供したいという思いは強いですね。
専門とする心臓エコーの重要性をお伺いします。

弁膜症の場合、今はカテーテルでの治療も始まりました。ただ、胸を開かない分、外科医師は実際の組織に触れられません。ですから、瞬時の変化が画像でわかる心臓エコーの役割は非常に重要です。私はこれまで、カテーテル治療の場面で手術医に提案をするエコー専門の医師としてハートチームに加わってきました。現在ではその経験を生かし、ウェブカンファレンスといったかたちで実際に治療をしている患者さんの画像の相談を受けることも多くあります。今までライフワークとしてやってきたエコーの知識や経験を生かしながら、この地区の医療に貢献できるというのはやはり大きな喜びですね。
在宅医療にも注力。患者を生涯にわたり支える医療を
治療で心がけていることは何ですか?

症状や条件は患者さん一人ひとり違いますが、患者さんのことを考えた心のこもった医療を行いたいと思っています。医療も患者さんの話を聞くだけ、優しさだけでは駄目で、患者さんのため時には厳しく言わなくてはいけない場合もあります。生活習慣病は生活習慣をきちんと指導することが大切です。例えば、高血圧の方にすぐに薬を使い血圧を下げるのは簡単ですが、その方のライフスタイルを考えると、最初に塩分制限をきちんと行って、運動指導をすることのほうが将来のためなる場合もあります。患者さんにとって何がいい医療なのか、そこを常に考えるよう心がけています。
今後は在宅医療にも力を注いでいきたいそうですね。
心不全は心臓が悪いことで水がたまって足がむくんだりする病気で、特に高齢の方に多く、それを地域でどう対応していくのかが課題になっています。四日市市は在宅医療については先進的な地域ですが、心臓に関してはまだその認識が広がっていません。在宅医療というのは救急に近い部分もあって、息が苦しいとなった時に家に行って処置をする必要性が出てきます。心臓病が悪化した場合、通常は入院治療します。高齢で認知症のある方は入院すると認知症がより進んでしまったり、入院を契機に元気がなくなってしまうこともよくあるんです。ですから、入院治療ばかりが良い治療ではなく、むしろ住み慣れた自宅で医療を受けたほうがいい場合もあります。往診・訪問診療を通して、そんな患者さんの受け入れ体制をつくっていき、少しでもこの地域に住む方々のお役に立てたらと思います。
最後に、読者へメッセージをお願いします。

心がけているのは、患者さんの不安を早く解消して、その後の人生のために何が必要かを考え診療することです。最近では、手術後の通院を近隣のクリニックで希望している、小児の心臓を診る先生を探している、といったお声をよくお聞きします。当院は、成人に限らず小児の心臓病治療についてもきちんと診させていただきますので気軽にご相談ください。内科や循環器系において、どこに行っていいのかわからないという場合にも、まず当院を頼っていただきたいですね。