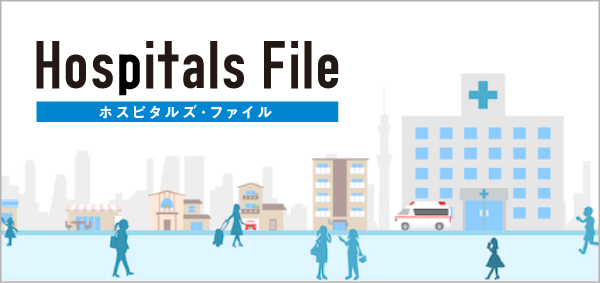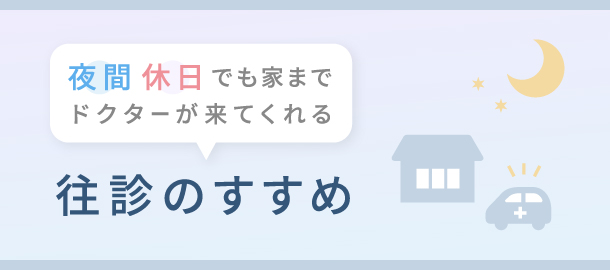木原 康之 院長の独自取材記事
きはら内科クリニック糖尿病内科
(北九州市小倉北区/城野駅)
最終更新日:2023/06/23

城野駅より徒歩2分のビル内にある「きはら内科クリニック糖尿病内科」。産業医科大学で准教授、北九州総合病院で主任部長などを歴任した木原康之院長が、糖尿病やその合併症を診療するために開業したクリニックだ。「社会活動に支障を来さないよう糖尿病をコントロールしていくためには、治療を中断しないことが何より大切」と語る木原院長。自院での診療だけでなく、地域における糖尿病治療体制の充実や糖尿病に対する偏見をなくすことをめざす啓発活動にも力を入れている。長年、糖尿病患者に向き合ってきた木原院長に、診療への想いや今後の展望などについて聞いた。
(取材日2022年8月24日)
治療の続けやすさを追求する糖尿病のエキスパート
最初に、クリニックの特徴について教えてください。

糖尿病の患者さんを診療するために、当院を開業したといってもいいかもしれません。糖尿病のほか、合併症として多く見られる高血圧症、脂質異常症などの慢性疾患の診療も行っています。糖尿病は、治療を中断することが一番の悪化原因と考えています。自覚症状がなかったり、症状が落ち着いていたりすると、通院をやめてしまう方も少なくありません。受診をしないまま気がついたら、血糖値が悪化していたという事態は何としても避ける必要があります。ですから、当院では患者さんに治療を続けてもらうために、予約が取りやすいよう配慮しています。仕事の都合などで、予定していた日に来られず通院間隔が空いてしまうこともあるかと思います。そうすると、何か言われるのではないかと気にされる方もいるかもしれませんが、来院できるときにぜひ受診していただければと思います。
糖尿病の療養のための指導を行うスタッフも常駐しているそうですね。
血糖値が悪化している場合は、インスリンを使わざるを得ないケースもあります。インスリンを導入する際は、ご自身の病気について理解を深めるために1週間から10日程度の「教育入院」がよく行われています。社会活動に支障を来さないよう、若い人こそ糖尿病をしっかりとコントロールして合併症を回避するべきなのですが、多忙で入院の時間がとれず、インスリンの導入がどんどん遅れてしまうという状況になりかねません。当院は、糖尿病の療養のための指導を行うスタッフが常駐していますので、入院せず外来でもインスリン治療を始めることができます。私とスタッフが使い方や注意点をきちんとお伝えしますので、ご安心ください。教育入院を希望される方は、お近くの対応医療機関と連携しながら治療を始めることもできます。
こちらで開業されたのはどうしてですか?

前職では、このクリニックのすぐ近くにある北九州総合病院で内科主任部長を務めておりました。患者さんの診療も行っていたのですが、次第に研修医の指導や各種委員会の出席など、管理に関する仕事の比重が増えてきたんです。もっと現場に立って、多くの患者さんを診療したいという思いが強まり、ニーズが高い糖尿病の診療をメインとするクリニックの開業を決意しました。こちらの場所は、駅やバス停が徒歩2分以内にありますし、ビルに直結する広い駐車場もあります。公共交通機関でも車でも、患者さんが来院しやすいと思い、この場所を選びました。お近くの方だけでなく、北九州市外から来られる方も多くいらっしゃいます。
消化器・代謝内科での経験を生かして広い視野で診察を
先生は、長年この北九州で診療をされてきたのですね。

生まれも育ちも北九州なんです。子どもの頃は体が弱くてよく病院に行っていました。そこで目にする医師の姿に憧れを感じたのが、医師をめざしたきっかけかもしれません。大学も八幡西区にある産業医科大学です。大学では、消化器・代謝内科の恩師の勧めもあり、膵炎や膵臓がんなど膵臓の疾患を専門にしていました。大学院生時代に2度にわたってアメリカ留学の機会もいただき、膵臓の内分泌に関する研究を行ったほか、分子生物学的な実験方法についても学びました。産業医科大学に約20年間、北九州総合病院に約6年間勤務し、アメリカに留学していた時期を除いて、ずっと北九州に拠点を置いています。高校の同級生で、こんなにずっと地元に残っている人は珍しいんじゃないかな(笑)。
糖尿病の治療に専門的に携わるようになったのはどうしてですか?
膵臓には、血糖の調節をするインスリンを作る役割があり、膵臓が悪い人は、糖尿病のコントロールが悪い傾向があります。それで、膵臓に関する研究・診療と並行して、糖尿病の研究・診療も行っていました。膵臓の病気は、数としてはそれほど多くはないんですね。それでも専門性の高い大学病院では患者さんが集まってきますが、地域の医療機関では膵臓疾患の患者さんより糖尿病の患者さんが圧倒的に多いんです。大学病院を離れてからは、次第に糖尿病の治療にシフトしていきました。膵臓を専門としたことで、多くの方が悩んでいる糖尿病との接点が生まれたわけで、恩師にはとても感謝しています。
消化器・代謝内科に長く携わってこられた経験が、糖尿病の治療に生かされているんですね。

消化器・代謝内科での経験に加え、大学病院でさまざまな診療科と接点があったことが、今の診療に役立っていると思います。近視眼的にならず広い視野を身につけられたからです。初診で糖尿病でクリニックにかかられる方は、ほとんどが糖尿病だけなんですが、まれに膵臓がんが原因で血糖値が悪くなっている方もおられます。また、糖尿病にかかると体重が減っていきますが、糖尿病に加えてがんで体重が減っている可能性もあるんですね。そこを、糖尿病が悪いんだなと思い込んで診ていると、発見が遅くなってしまいます。先入観を持たず、患者さんの変化やいろいろな病気の可能性を見逃さないよう心がけています。
患者の頑張りを後押しする声かけを
診療の際に心がけていることはどんなことですか?

しっかりと問診をして、患者さんの話に耳を傾けることですね。今は電子カルテなので、患者さんのほうをずっと見て話をするわけにはなかなかいかないのですが、診察室に入ってこられた時は顔色を見て体調に変化がないか確認しています。そして、検査結果を見て、数値が悪くなっていたら生活習慣で変わったことはないのか、改善していたら何かご自分で取り組まれたことがあるのか、お聞きするようにしています。きっと患者さんも努力されていることをお話ししたいですよね。けれど、ご自分からは言い出しにくいかもしれません。ですから、患者さんの頑張りに対してこちらから声かけをして、モチベーションを保つお手伝いをしたいと思っています。
糖尿病はずっと付き合っていかないといけないので、前向きに治療に取り組めることが大切ですね。
そうです。生活習慣について指示するのは簡単ですが、それを実行するとなるとなかなか難しいこともありますよね。例えば、2~3ヵ月間頑張れば病気が消えるということであれば頑張れる方は多いでしょうが、そうはいかないのが糖尿病です。今はやりの言葉でいうと「サステナビリティ」というのでしょうか、持続可能な取り組みであることが大切なんですよね。そして、持続可能なことは患者さんそれぞれ違います。その方が持続的に症状改善に向けて努力ができるよう、患者さん一人ひとりに向き合っていきたいですね。
今後力を入れていきたいことと、読者へのメッセージをお聞かせください。

患者さん自身に糖尿病のことを理解していただくこと、そして糖尿患者さん以外の方にも、糖尿病という病気への理解を深めていくことがとても大事だと考えています。患者さんや医療関係者などによって運営されている「日本糖尿病協会」では、講演会やウオークラリーを開催したり、世界糖尿病デーには各地でライトアップをしたりしてきました。新型コロナウイルス感染症の流行で、患者さんとの交流や一般の方への啓発活動に制限がある状態が続いていますが、今一度、行政や地域の医療関係者とともにこうした活動に力を入れていきたいです。糖尿病治療はチーム医療です。糖尿病の療養のための指導ができる看護師や管理栄養士、薬剤師、理学療法士の数をもっと増やしていくための活動も進めていく必要があるでしょう。糖尿病は、治療を中断せず続けていくことが何より大切です。私たちが全力でサポートしますので、どうか諦めず診療に来ていただければと思います。