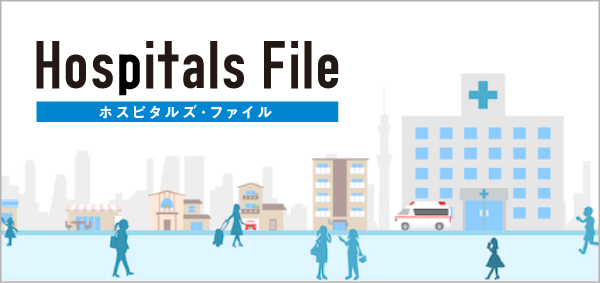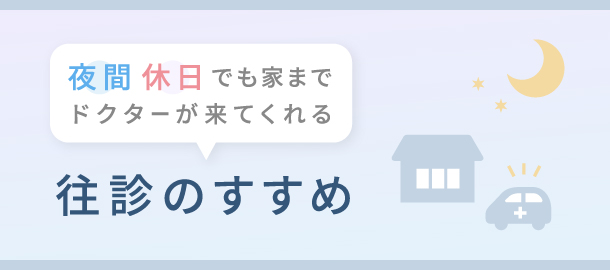原 秀憲 院長の独自取材記事
はらクリニック
(尼崎市/尼崎駅)
最終更新日:2021/10/12

阪神尼崎駅から徒歩10分の場所にある「はらクリニック」は、内科・神経内科・形成外科を標榜する在宅医療を主体としたクリニック。患者一人ひとりに寄り添いたいと考えた原秀憲院長が2010年に開業、「ありのままを受け入れる」をモットーに診療にあたっている。同クリニックではデイケア、通所リハビリテーション、ケアプランセンターなどの各部門も設け、「外来診療・在宅医療・リハビリテーション」を提供。患者はもちろん家族の気持ちもくみ取りながら療養生活を支える。“理想の治療”にこだわらず、患者それぞれに合う治療を提案したいとする原院長に、開業の経緯や在宅医療による「生活を見る」重要性、今後の展望などを聞いた。
(取材日2019年5月14日)
患者に寄り添いたい。開業を決めた「100%の真実」
神経内科に進まれた理由を教えてください。

近年の病気というと慢性疾患が主体となっており、循環器内科や消化器内科の領域もそうですし、例えば糖尿病や高血圧などの生活習慣病は特に知られていますが「病気とともに生きる」時代になっていると思うんです。その中で神経内科領域はいわゆる難病と呼ばれる疾患で、治療法が確立されていない病気が大半。困っていらっしゃる患者さんがとても多い現状を知り、神経内科に進もうと決意しました。また私が神経内科に入局した当時は今よりも未知の部分が大きく、志す人も少なかったので「みんなが手を出さない分野に行こう」という気持ちもありましたね。
実際に神経内科に進んでみていかがでしたか?
神経内科の患者さんの多くは、次第に歩けなくなっていく疾患を抱えています。外科や循環器内科に進んだ同期の医師たちは、手術や入院治療を施して自分の足で元気に帰る患者さんを見送っていましたが、私の担当する患者さんは基本的に慢性疾患ですっきりと回復するケースはあまりおられない。正直に言うと「この道を選んで良かったのか」と悩みましたね。しかし当時、内科の教科書を読み返した際、医学の歴史の中で病気を完全に克服した時代はなく、人間は常に病と共存しながら生きていることにあらためて気づかされました。神経難病は治療法が確立されておらず苦しむケースも多いのですが、それも一つの人生。百人百様の患者さんの人生に寄り添っていくことこそが、実は臨床医にできる唯一の仕事ではないかと大学病院時代の先輩から言われたこともあり、「神経内科に進んで良かった」という思いに変わりました。
開業までの経緯を教えてください。

医学部卒業後は大学病院や総合病院で経験を積んだほか、大学院への進学や臨床研究で学会発表もしてきました。しかし研究では集められたデータ上の95%という大部分を見て結果を検討し、残りの5%は切り捨てる「95%の真実」です。一方で、患者さん一人ひとりに向き合う臨床はその方の症例が「100%の真実」。大きい視点でデータを見ることも大切ですが、神経難病は患者数も少なく、一例一例がそれぞれ違う。先ほどもお話ししたとおり臨床医の仕事は患者さんに寄り添うことだと思っていますので、それならば開業して患者さんと向き合うほうが、私の性に合っていると考えたんです。もともと私は実家の隣にあったクリニックの先生に憧れて医師の道を志したこともあり、子どもの頃に見た光景を実現できたらと思い、地元・尼崎で開業しました。
生活の質向上へ、在宅診療で「生活を見る」重要性
貴院の特色を教えてください。

当院は在宅医療を主としています。神経内科の患者さんの多くは徐々に歩くことができなくなり、これまでどおりの外来への通院が不可能になっていきます。それならば、外来で待っているよりも私が患者さんのご自宅に伺おうと考えました。また、国際生活機能分類という、健康状態や心身機能、障害の状態などをベースにした健康度を測る考え方があります。その考えを活用し、例えばパーキンソン病を患っていて外出は難しくても「どういう自宅設備ならより良く暮らしていけるのか」「電動車いすなど移動手段をサポートできるものがあるのか」などを整理することにより、患者さんの生活の質の向上をめざすことができます。しかしこれは患者さんの実際の生活を見ないと提案できないことですから、できる限り往診に行くべきだと考え、在宅医療主体のクリニックとしました。
実際に往診をして、何か気づきや変化はありましたか?
例えば認知症に関して言えば、在宅医療を始める前は、認知機能の検査結果をもとに「認知症か、否か」を診断していただけでした。でも実際にご自宅に伺うと、新しいことを記憶できないために自宅がゴミ屋敷化している方もおり、患者さんが本当に必要としているサポートが何かを考えるため「生活を見る」ことの重要性を知りました。診療は私一人で伺いますが、住宅の改修を検討しているご家庭なら理学療法士を伴い、患者さんの病状に合わせて手すりをつける場所を提案したり、介護を必要とされている方にはケアマネジャーも同伴し介護サービスの利用やケアプラン作成なども行っています。
在宅療養の患者さんに接する際に心がけていることは?

在宅の患者さんは、病院から退院した後は自宅で、というケースが多いと思います。「自宅でこれまで同様の医療が受けられるのか」など不安があると思いますが、そこに寄り添っていくということを常に心がけています。ですから当院では退院前のカンファレンス(検討会)から参加し、退院当日に必ず往診します。退院前から介入して体制を整え、病院から在宅へシームレスに移行できるように心がけていますね。また、揺れ動く気持ちに寄り添うことも大切にしています。例えば家族で話し合い「救命・延命は不要」という方針を共有していても、患者さんの容体が急変した際にご家族が翻意し救命を望まれることも少なくありません。私はこの揺れ動く当然の気持ちに寄り添い、伴走者としてサポートしたいと考えています。
患者のありのままを受け止め、実現可能な治療を提案
診療のモットーを教えてください。

「ありのままを受け止める」ことです。糖尿病であれば食事制限と規則正しい生活が医学的な正解でしょう。しかしなぜ糖尿病になったか考えれば、ご本人の体質や膵臓の能力もありますが、例えば介護のため不規則な生活であるとか営業職で夜のおつき合いが必須など、さまざまな事情があると思うんです。「インスリンは1日4回」「食事制限して規則正しい生活」「夜のつき合いはやめる」など理想だけを言い出したら、生活が立ち行かなくなってしまい、医学を守ったがゆえに人生が実現できなくなる方も出てくると思うんです。「医療」は医学の社会的実践であると考えていますから、患者さんの生活に医学を反映させ、生活の質を向上させることがゴール。医学はあくまでツールでしかありませんから、「できることを考えてやっていきましょう」というスタンスで患者さんに接しています。
今後の展望を教えてください。
新しいことや新しい分野に取り組むというより、今やっていることの質を高めていきたいと考えています。現在、当医療法人はクリニックのほかデイケア、通所リハビリテーション、ケアプランセンターを運営しており、外来診療・在宅医療・リハビリテーションの3つがうまく回り始めています。外来から在宅療養になった患者さんでも、リハビリテーションを組み合わせることによって、また外来に戻ってこれるような医療を提供したいと考えています。まだ「在宅療養は最後」というイメージが強いですが、一生寝たきりかといえばそんなことはありませんし、在宅医療は一つの経過です。再び外来通院に戻っていけるような体制をつくっていきたいと考えています。
読者にメッセージをお願いいたします。

医学はあくまで本人の生活の幸せを高めるためのツールでしかありません。「四苦八苦」という言葉がありますが、仏教で四苦は「生・老・病・死」を指し、人間にとって必ず起こるものです。6年間の医学部教育は西洋医学の「生が善」「病・死は悪」という二項対立の考え方でしたが、多くの人が加齢とともに起こる生活習慣病や認知症、がんといった疾患を抱えながら生きていくのが現状ですし、これをたたきつぶすことはできないわけです。「生活習慣が悪いから病気になった」と言えば簡単ですが、「どうしてその生活習慣になっているのか」という社会的背景を考えないと意味がありません。百人百様の人生のために医学があるので、当院では患者さん一人ひとりと向き合い、受け止め、お互いに話し合いながらやっていきたいと考えています。