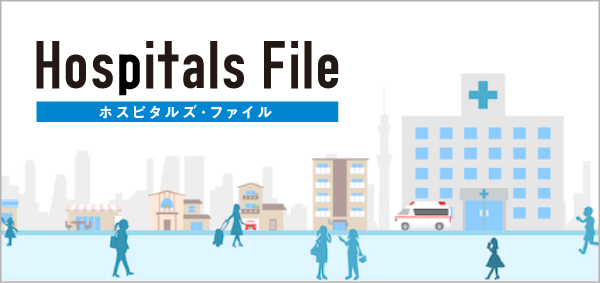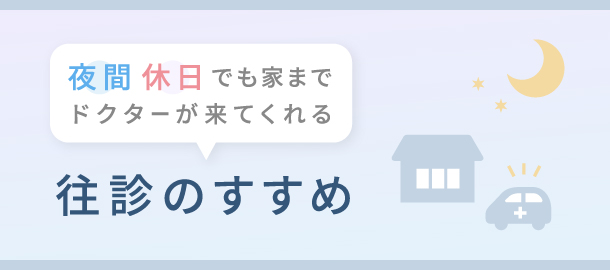高 富栄 院長の独自取材記事
コこころのクリニック
(神戸市長田区/西代駅)
最終更新日:2023/12/28

新長田駅から徒歩約8分、西代駅から徒歩約5分の「コこころのクリニック」。ロゴマークにデザインされた2つの顔は、ともに取り組むという意味の「co-workthrough」や「個」などからCとOをモチーフに作られたもの。精神科を専門とする高富栄(こう・ぷよん)院長が2018年に開業した同院では、不登校やうつなど心の問題に寄り添い、ゆっくりと着実に社会へ戻っていけるよう支援している。「不登校の部分だけを解消しようとしたり、自分の想いを押しつけるような診察はしません」と、穏やかな笑顔で話す高院長。経験豊かな公認心理師とともに年代や状況に合ったアプローチで、同院ならではのプレイセラピーや集団精神療法を行っている。こだわりの詰まった診察室で、診療への思いを聞いた。
(取材日2023年11月22日)
「焦らず・一緒に・ゆっくり」をテーマに寄り添う
クリニックの名前に込められた想いなどをお聞かせください。

「コ」にはさまざまな意味が込められているんです。私の名前が高(こう)ということもありますが、ホームページのアドレスにも入れているクリニックの第一義“一緒に取り組む”という意味の「co-workthrough」、個性の「こ」、子どもの「こ」、ほかにcommunityやcollaborationもありますね。子どもから大人まで、必要とあらばいつでも一緒に治療に取り組みますよ、という想いで診療にあたっています。特にお子さんは自分で「これがストレスで体調が悪い」なんて言葉にできませんから、いろいろな手段を使いながら探っています。そのためにプレイセラピーの部屋を広く設けて、治療や行動観察に使っています。ドイツ語で多訴を意味する「klagevoll」からクラゲホールと呼んでいるのですが、おかげでクラゲがうちのキャラクターのようになっています(笑)。
このエリアに開業されたきっかけや主な患者層を教えてください。
開業前にこの町で外来診療のお手伝いをしたことがあり、魅力を感じていました。同時に、復興の町として生まれ変わった分、新たに転入された方が多い印象がありましたから、核家庭で問題を抱えた場合に困る方もいらっしゃるだろうと思ったんです。震災に関する研究に関わったこともあり、そういう背景も気になっていましたし、旧来の方も新たに来られた方も、精神面のフォローが必要じゃないかと。当院は、不登校の患者さんが多いです。学校に行けない、行きたくない、朝起きられない、それゆえ昼夜逆転してしまっている、ゲームに依存している、などです。特に小学5年生と中学2年生の層が多く、その学年は勉強につまづきやすいんです。何とか頑張って行くものの体に兆候が出てしまうというケースが多いですね。
不登校についてのお考えをお聞かせください。

不登校になると、どうしてもそれが悪いことだと捉えられがちです。かといって、治療目標を登校だけにしてしまうと集団に対するなじみにくさなどを抱えたまま無理をすることになり、根本を解決できていない場合もありますよね。ですから、私のクリニックではまず不登校を問題のように考えず、あくまで「きっかけ」として焦らず背景を探ります。社会参加のかたちは学校以外でも見つけられますし、学校に行かなくても生きられるけれど生きていなければ学校にはいけません。まずは健康的な心で生きることが優先です。「登校させる」という簡単なストーリーではなく、きちんと社会参加して定着していくことを軸に、ご家族にもお話ししています。
プレイセラピーや集団精神療法を通して根本的治療を
院内環境でこだわった点はありますか?

精神科では、机やパソコンを挟んで医師と患者さんが話す診察室が多いと思います。私はまずそこを見直し、変えてみました。患者さんとの間には極力ものを置かず、目を見て会話できるスタイルにしています。プレイセラピーの部屋には、いろいろな種類のおもちゃを用意しました。その子によって人形を使ったり、ボールを使ったり、カードゲームを使ったり、時にはおしゃべりだけして過ごすこともあります。与えられた時間内でどう遊ぶかは、こちらが指導者にならないように気をつけていますね。学校空間で傷ついた子どもたちは自分を出すことを恐れています。なかなか「丸」をもらえず、注意されてばかりの子も多いですから、そういう子どもたちが自分を表現する勇気を取り戻す場であってほしいと思っています。
小児・青年・成人それぞれどんなアプローチをされているのでしょうか?
小児は遊びが言葉代わりなので、プレイセラピーを重視しています。発達検査や心理検査も原因探しの助けになりますね。大人の方は、集団でSST(ソーシャル・スキル・トレーニング)をやっていただくことが多いです。いろいろな人と仲間意識を持って課題に取り組んだり、他の参加者の行動を吸収してもらったりするんですが、世代が離れている人と関わることで疑似家族体験ができるのもねらいです。そして、精神科の受け皿が少なく苦労されているのが、青年層。小児でも社会人でもない彼らは、一対一のカウンセリングだけでなく集団精神療法の枠組みで治療に取り組みます。複数の公認心理師と医師である私とでおしゃべりをしながら言葉で自分を表現したり、相手の話をきちんと聞けるようにトレーニングして、社会性に気づいてもらうんです。言葉での自己表現は青年期の治療のキーワードになりますね。
親御さんに感じることがあればお教えください。

親御さんには、ぜひお子さんの良い面や新しい可能性に気づいてもらいたいという想いで言葉がけをしています。どの方もお子さんが心配という一心で来られますが、「学校に行ってほしい」、「試験で良い点を取ってほしい」、ということにとらわれすぎている方も見受けられるんですね。けれど、学校でもらえる「丸」ってすごく範囲が狭かったりするんですよ。その子が答えていることも十分社会では通じるのに、教育現場ではいろいろな都合でごく一部しか正解とされないことがある。それを外すと叱られたり笑われたりすることがありますから、一生懸命社会参加したのに傷ついて帰ってくる、学校が怖くなる、自分が表現できなくなる。私としては、ご家庭では学校と違うものさしでお子さんを測っていただけたらな、と思います。
学校や地域と連携して治療を進めたい
患者さんと向き合う時に気をつけていることはありますか?

開業当初から、自分の治療を押しつけないよう気をつけています。勤務医時代に他職種のスタッフや地域の支援者と協力しながら良い形の治療ができていたので、そのスタンスは生かしていきたいんです。患者さんと医師だけの会話で終わらず、なるべく公認心理師や看護師、精神保健福祉士、地域の支援者から見解を取り入れるよう意識しています。先ほど年代によって治療のアプローチが違うことをお話ししましたが、共通してめざしているのは患者さんに“自分を好きになってもらうこと”です。ご本人の背景にある問題をきちんと捉えてもらい、何が得意で何が苦手かをできるだけ理解していただいて、その上で自分を好きになってもらうことが第一だと考えて接しています。
経験豊かな公認心理師さんが多くいらっしゃるそうですね。
公認心理師の多さは、当院の特徴の一つと言えると思います。先ほどからお話ししているプレイセラピーに深く関わってもらったり、心理検査や面談をお願いしたり、教育者の経験がある公認心理師には経験を発揮してもらったりしています。これは今後のプランとして考えていることですが、公認心理師と地域の学校をつなぐ役割を当院で担えないかな、と思っているんです。私自身があちこちの学校に顔を出せれば一番ですが、体一つでは限界があるので、公認心理師を派遣することで学校と一緒になって不登校の子をフォローできるのではないかと思案中です。まだまだアイデアの段階なので、実現させたいですね。
読者の方へメッセージをお願いいたします。

私が精神科医になったのは、答えのない世界でその人なりの答え探しを手伝うことにやりがいを感じたからです。私という医師、そして当院を育ててくださったのは関わってくださった皆さんです。だからこそ、ともに心の病に取り組みたいんです。クリニックのロゴにある2つの顔、これは目線を同じ高さに合わせるとハートのような形になるんですよ。そこにも、そんな想いを込めています。今、子育てや仕事や介護や学校のことで悩まれている方、ぜひ一度それを言葉にして一緒に考えてみませんか? 一人で悩まず、お手伝いさせていただければと思います。